
複数当事者訴訟
栗田 隆

 |
民事訴訟法講義
複数当事者訴訟関西大学法学部教授
栗田 隆 |
 |
多数の者が同一の公共の利益の実現という主観的意図のもとに訴えを提起する場合には、9条1項ただし書の適用による費用の節減が期待されるが、そうなるとは限らない。例えば、林地開発行為により自己の水利権、人格権、不動産所有権等が害されるおそれがあることを主張して、開発区域周辺の複数の住民が開発許可処分の取消しを求める訴えを提起した場合には、訴えにより主張する利益は全員に共通であるとはいえないから、訴訟の目的の価額は各原告の主張する利益によって算定される額の合算額とすべきであるとされる(最高裁判所平成12年10月13日第2小法廷決定(平成12年(行フ)第1号) )。
1.主債務者は、答弁書を出すことなく全ての期日を欠席し、保証人は債権者の主張を争い、裁判所は主債務の不存在の心証を得た場合。 2.保証人の住所・居所が不明なため、保証人に対しては公示送達による呼出がなされ、保証人は、答弁書を出すことなく全ての期日を欠席したが、主債務者は債権者の主張を争い、裁判所は主債務の不存在の心証を得た場合。 |
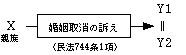 第三者の提起する婚姻無効または取消しの訴え(民744条、人訴法12条2項) 人訴法24条1項により判決効は第三者に拡張されるが、婚姻当事者はこれに含まれない。利害関係の強さから見て、婚姻当事者双方を被告にする必要があり、また一方を訴訟当事者とすることなく下された判決の効力をその者に拡張することは許されない(前記(β))。
第三者の提起する婚姻無効または取消しの訴え(民744条、人訴法12条2項) 人訴法24条1項により判決効は第三者に拡張されるが、婚姻当事者はこれに含まれない。利害関係の強さから見て、婚姻当事者双方を被告にする必要があり、また一方を訴訟当事者とすることなく下された判決の効力をその者に拡張することは許されない(前記(β))。 合一確定の要請と上訴審
固有必要的共同訴訟において、原審が合一確定の必要があることを見逃して、共同訴訟人のうちのある者と他の者とについて内容が異なる判決をした場合には、誰が上訴を提起したかにかかわらず、上訴審は、判決の合一確定を実現するために、職権で、原判決を是正することができる。共同訴訟人の1人が上訴を提起し、他の者は提起しなかった場合に、後者に不利に変更することも許される(後者が上訴人の地位に就くとすれば、不利益変更禁止原則に抵触する措置となるが、その原則よりも、合一確定の要請が優先する)。
最高裁判所 平成22年3月16日
第3小法廷 判決(平成20年(オ)第999号)が、上記のことを「相続人の地位を有しないことの確認請求」について認め、次のように説示した:「原告甲の被告乙及び丙に対する訴えが固有必要的共同訴訟であるにもかかわらず,甲の乙に対する請求を認容し,甲の丙に対する請求を棄却するという趣旨の判決がされた場合には,上訴審は,甲が上訴又は附帯上訴をしていないときであっても,合一確定に必要な限度で,上記判決のうち丙に関する部分を,丙に不利益に変更することができる」。
意義
訴えの主観的予備的併合とは、数人の請求または数人に対する請求が論理上両立し得ない関係にある場合に、それらの請求に順位をつけて、それらを併合することをいう。例:
(C)順位付単純併合説 否定説が指摘する問題点を考慮して、この併合形態における申立人の意思の合理的解釈として、主位的被告に対する請求が認容されれば予備的被告に対する請求は不要であるとの趣旨の申立てと解するのは適当ではなく、むしろ、単に認容判決を受ける順序を指定したにとどまり、したがって主位的被告に対する請求を認容する場合には、これと両立し得ない予備的被告に対する請求を棄却しなければならないとの見解が主張された。この立場にあっては、この併合形態は、客観的予備的併合との差異を明確にするために、順位付単純併合(ないし順位的併合)と呼ばれることになる。裁判所は、原告の付した順位に拘束され、その順に請求認容の可能性を判断すべきである。
現行法上、本来の意味(主位請求が認容されれば予備請求については審判を求めないという意味)での主観的予備的併合は、許されない([高見*2001a]700頁以下)。他方、順位付単純併合は許されてもよいが、それにどのような意義を与えるかは、問題である。同時審判申出訴訟を見てから考えることにしよう。
選択的単純併合
なお、不両立の関係にある複数の請求のうちのいずれかの請求の認容を求めるという形で請求を単純併合することも肯定してよい。これは、請求原因事実の主張のレベルで主張に矛盾が生じないように選択的に主張したことに応じて請求レベルで表明される意思にすぎない。選択的に併合された請求のうちの一つのみが認容され、他は棄却されるのは、原告の意思に基づくというより、併合された請求が不両立の関係にあること自体に基づく。
ヒント:41条は事実上併存しえないだけの場合には適用がないとの見解を前提にしても同時審判申出が可能になるように努力すること[53]。 |