
民事訴訟法講義
訴訟参加
関西大学法学部教授
栗田 隆
栗田 隆

 |
民事訴訟法講義
訴訟参加関西大学法学部教授
栗田 隆 |
 |
| 債権者Xが保証人Yに対して保証債務の履行を求めて訴えを提起した。それを知った主債務者Zが、Yからの求償権行使を回避するために、主債務が存在しないことを主張して、Yに補助参加した。 |
| 債権者Xが債務者Yに対して提起した金銭支払請求訴訟に、保証人Zは補助参加するだけの利害関係を有するか。判例の定立した判断枠組みにしたがって考えてみよう[26]。 (a)「訴訟の結果」として、まず債権者勝訴の場合を想定しよう。請求認容判決が確定すると、主債務者は、既判力の標準時前の事由で債務の存在を争うことができなくなる。しかし、その判決の既判力は、保証人に[及ぶ|及ばない]ので(115条1項)、保証人の地位がこの判決から受ける影響は、[大きい|小さくない|小さい|あまりない]。 (a')ただし、保証人がすでに保証債務を履行したために主債務も消滅しているような場合には、債権者が勝訴すると、主債務者の財産状況が一層悪化し、保証人の求償権行使は[困難になる|容易になる]。そのような場合には、Xの請求を認容する判決が確定するという訴訟の結果により、Zの法的地位に影響を及ぼすおそれは、[大きい|小さくない|小さい|あまりない]。 (b)「訴訟の結果」として、次に債務者勝訴の場合を想定しよう。この判決が確定した後で、債権者が保証人に保証債務履行請求の訴えを提起した場合に、保証人は、「主債務が存在しないことが債権者・主債務者間の訴訟で確定しているから、債権者Xは保証人Zに対しても主債務の存在を主張できない。従って、Xは、保証債務の附従性により保証債務の存在を主張できない」と主張することになろう。この主張の第一段は、いわゆる判決の反射効の主張であるが、反射効の理論を承認するか否かにかかわらず、通常であれば、ZはXY間の請求棄却判決を援用して、Xとの訴訟を有利に進めることができる。少なくとも、XのZに対する訴訟提起の意欲をそぐことができる。したがって、この判決がZの法的地位に及ぼす影響(Zの地位の向上)は、[大きい|小さくない|小さい|あまりない]ということができる。 以上の分析から、Zは、XY間の訴訟に補助参加するのに必要な利害関係を有していると[いえる|いえない]。 |
| 債権者から保証債務の履行を求められた受託保証人が主債務者に事前の通知をしたところ、主債務者から弁済ずみであるとの返事がきたので、支払わないでいた。ところが、債権者が保証債務履行請求の訴えを提起してきた。主債務者が直ちに補助参加して主債務の消滅を主張したが、裁判所は主債務の存在を認めて、請求認容判決を下した。保証人が主債務者に対して求償請求の訴えを提起した。主債務者は、主債務は前訴の口頭弁論終結前に弁済により消滅しており、保証人が敗訴したのは訴訟追行がまずかったからであり、主債務がなかった以上、求償に応ずる義務はないと主張した。どうなるか。 |
| ある物について、XがYに対して所有権確認の訴えを提起した。その物が自己の所有物であると主張するZがこの訴訟に独立当事者参加し、XとYに対して、その物がZの所有に属することの確認の訴えを提起した。 |
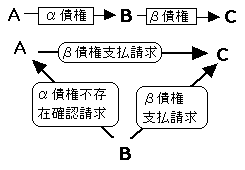 |
| 1. 裁判所が、α債権が存在しないと判断し、かつ
2. 裁判所が、α債権が存在すると判断し、かつ
|
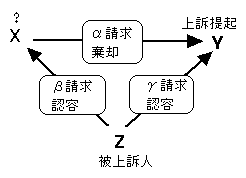 [設例2.1]において、第一審裁判所が目的物はZの所有物であると認定して、Xの請求を棄却し、Zの請求を認容したところ、Yのみがこれに不満を持ったとしよう。Yは、Zを被控訴人にして、Zの自己に対する請求を認容した部分の取消しを求めることになる。他方、ZのXに対する請求を認容した部分については、これもYにとっては不満であり、Yはこの部分の取消しを求めることができるとすることも考えられてよいのであるが、他人間の請求に関する部分に直接に取消申立てをすることは、認められていない(認めなくても、次のbにより同じ結果がもたらされる)[11]。このことを前提にして、各当事者に上訴審で次のような地位が与えられる。
[設例2.1]において、第一審裁判所が目的物はZの所有物であると認定して、Xの請求を棄却し、Zの請求を認容したところ、Yのみがこれに不満を持ったとしよう。Yは、Zを被控訴人にして、Zの自己に対する請求を認容した部分の取消しを求めることになる。他方、ZのXに対する請求を認容した部分については、これもYにとっては不満であり、Yはこの部分の取消しを求めることができるとすることも考えられてよいのであるが、他人間の請求に関する部分に直接に取消申立てをすることは、認められていない(認めなくても、次のbにより同じ結果がもたらされる)[11]。このことを前提にして、各当事者に上訴審で次のような地位が与えられる。
| 1. Xが脱退し
2. Yが脱退し
|
裁判所はどのような判決をすべきか。その判決はどのような効力を有するか。 (ヒント:ZのXに対する請求についての判断に迷う場合には、この請求はなかったものとして(片面的参加であったとして)解答してもよい) |
| XがYに対してα債権を有している。その給付訴訟の係属後・事実審の口頭弁論終結前に、Xがα債権をZに譲渡し、その通知をYにした。訴訟はどうなるか。 |
| 土地の所有者Xが、権原なしに建物を建築して土地を不法占拠しているYに対して、建物収去・土地明渡しの訴えを提起した。その訴訟の係属中に、Yがその建物をZに譲渡して、引き渡した。訴訟はどうなるか。 |
| 債権者からの執行を逃れるために、Xが自己の不動産をYに譲渡し、所有権移転登記をした。執行のおそれがなくなったので、XがYに返還を求めたが、任意に応じないので、訴訟を提起した。訴訟中にYが目的物をZに譲渡した。訴訟はどうなるか。 |
| 5脱退 X──(1請求)─→Y 3引受申立 ‖ │↑ (2承継) ││ ↓ ││ Z←─(3請求)─┘│ ──(4請求)──┘ 数字は、時間的順序を意味する。 |
| X──(損害賠償債権)──>Y 被害者 加害者 未成年者 ‖ ‖ A 法定代理人 Xの法定代理人Aが自己の名で提起した損害賠償請求訴訟において、 原告名をAからXに変更する。 |
| 賃貸人 賃借人 X──(1建物明渡請求権)──→A会社 │ └──(2建物明渡請求権)──→Y個人(A会社の代表取締役をしている) XはA会社と賃貸借契約を締結したつもりでAに対して明渡請求の訴えを提起したが、 訴訟係属中に、その賃貸借契約の当事者はA会社ではなく、その代表取締役であるY個人であることが判明したので、被告をA会社からY個人に変更する。 |
| 大阪地判昭和29.6.26下民集5-6-949[百選*1998a]40事件 |
| 事実の概要 原告Xは、「株式会社栗田商店代表取締役栗田末太郎」を振出人とする約束手形を所持している。振出人Y(株式会社栗田商店)が本店を移転し、商号をY'(栗江興業株式会社)に変更したため、手形所持人は、株式会社Yは存在しないものと錯覚し、やむなく訴状の被告欄に「株式会社栗田商店こと栗田末太郎」と表示して訴えを提起した(この表示は、「株式会社栗田商店を名乗る栗田末太郎」が被告であることを意味する)。 その後、Yの本店の移転および商号変更の事実が明らかになったので、Xが訴状における被告の表示を「栗江興業株式会社右代表者栗田末太郎」に訂正すると申し立てた。これに対して被告側が、これは当事者の変更にあたるとして争った。 裁判所は、当事者の変更と表示の訂正の区別、および当事者の確定方法について表示説をとるべきことを明らかにした上で、次のように述べて本件の当事者欄記載の変更は、表示の訂正にすぎないとした。 |
| 判旨 当事者の確定にあたっては「訴状全般(単に当事者の表示欄のみでなく請求の趣旨・原因その他)の記載の意味を客観的に解釈して何人が原告であり、被告であるかを決する」べきである。本件の場合には、前記のような事情があることから、「当初より原告Xが右手形の振出人を被告とする意思を有していたことを認めうることはもちろん、訴状の記載上も振出人を被告としたものと解し」うる。 |
| 大阪地判昭和53.6.30無体裁集10-1-237 |
| 事実の概要 昭和19年設立の株式会社公益社(旧公益社)が昭和38年に設立された株式会社に葬祭請負に関する営業を譲渡し、自らは霊柩車による運送を主目的とする会社となった。両会社は、本店所在地も代表取締役も同一である。昭和48年に株式会社高槻公益社等の同業他社に対して商号使用禁止の訴えを提起するに当たって、訴訟代理人が訴状の請求原因欄に、「原告は昭和19年に設立された」と書いてしまった。第7回口頭弁論期日において、原告が、訴状の当事者の表示欄における原告会社名の直後に「(ただし、葬儀行為を営業目的とするもの)」との文言を補充した。被告は、これは任意的当事者変更にあたり、許されないと主張した。裁判所は、次のように判示して許されるとした。 |
| 判 旨 「訴状の記載全体を通覧し、また原告代理人の証拠提出活動等の挙動を総合判断すると、本件各訴訟における原告は専ら自己の主営業である葬儀請負業に関し、その同業者である被告らが不正競争行為をしていると主張して本訴を提起したものであり、本訴の訴旨はほかならぬ葬儀請負業界における競業秩序維持を求めるところにあることが明白で、その趣旨につき他意は認め難いところである。そうすると、本件原告はまさに昭和38年設立にかかる葬儀請負業を主目的とする「公益社」であつて、昭和19年設立にかかる霊柩車運送を主目的とする「旧公益社」ではないと解すべきである。もつとも、各訴状の請求原因一項の前段部分だけを精読すると、「原告は昭和19年に設立された。」と主張している部分があり、あたかも「旧公益社」が原告であるかのように受けとれる部分も存するが、他方その後段では原告が葬儀請負を業とする会社であることを明示している点からすると、右前段部分の記載は代理人が調査不十分のため両者を誤つて混同した結果であると解するのが相当で、右のような点をもつて前記の説示判断を左右すべきではない。」。 |
1. Zは、見ず知らずのYから訴訟告知を受けた。訴訟告知書には、次の趣旨のことが記載されている。「ZがXに対して負っている債務について、Zの委託を受けてYが連帯保証人になった。Xが、Zから債務の弁済がなかったと主張して、Yに保証債務の履行を求める訴えを提起した。そこで、Zがこの訴訟に補助参加するように、訴訟告知をする。訴訟は、まだ第一回口頭弁論期日前の段階にある」。Zは、「Xから金を借りたことはあるが、既に弁済済みである。Yに保証人になることを頼んだ覚えはない」との趣旨を記載した書面を上申書として裁判所に郵送の方法により提出し、あわせて同趣旨の書面をYに送付し、補助参加はしなかった。Zの証人尋問の申請がなされないまま、Y敗訴判決が確定した。Yが保証債務を履行し、YがZに対して、求償の訴えを提起した。ZはYに対して、主債務が存在しなかったことを主張できるか。なお、求償訴訟において証拠調べをすれば、保証委託がないこと、およびZがすでにXに債務を弁済済みであったことが証明されるものとする。 2.Yの過失のある運転によりXが負傷し、XがYに対して損害賠償の訴えを提起した。Yは、Xが交通事故により受けた傷はそれほど大きくなかったのに、Xの持病と搬送された病院の医療過誤により損失が拡大したと主張するとともに、Xに生じた損害を争うことについて補助を求めて、病院を経営するZに訴訟告知をした。しかし、ZはYの側に補助参加することなく、逆にXの側に補助参加して、Yの主張をことごとく争った。裁判所は、YとZの共同不法行為を認め、Xの持病を否定し、Yに5000万円の支払を命じた。Yは、Xに支払った賠償金について、Zに対して求償請求の訴えを提起した。この訴訟においても、YとZの共同不法行為が認定された。問題は、Xに生じた損害額である。Zは、Xには持病があり、稼働能力が低かったことを考慮すれば、YとZがXに賠償すべき金額は2000万円であったと主張することは許されるか。Zが前訴においていずれの側にも補助参加していなかった場合はどうか。 |
問題1
問題2