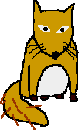 |
民事執行法概説債権執行1/3関西大学法学部教授
栗田 隆 |
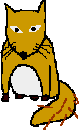 |
第1章 強制執行
第2節 金銭執行
第4款 債権およびその他の財産権に対する強制執行
第1目 債権執行等
復権執行に関する 文献 判例
| 「差し押さえる債権」あるいは「差し押さえられた債権」を「差押債権」という。「被差押債権」と言ってもよいのであるが、差し押さえられた動産を「差押物」(123条3項)と言うのにならって、「差押債権」と言うことが多い。 |
| 執行 執行 第三 債権者 債務者 債務者 X─(α債権)→Y─(β債権)→Z Y←(γ債権)─Z X←───(δ債権)─────Z 転付命令によりXがβ債権を取得する。 X────(β債権)────→Z 順相殺:Zがγ債権をもってβ債権と 相殺すること。 逆相殺:Xがβ債権をもってδ債権と 相殺すること。 |
| 1.第三債務者への転付命令の送達 | |他の債権者Aによる差押え・配当要求(α) | 2.即時抗告(債務者への送達から1週間以内) | |他の債権者Bによる差押え・配当要求(β) | 3.転付命令の確定=債権移転の効力が1の時点に遡及⇒(α)(β)とも無効。 ∵転付債権者に独占的満足を与えるためである。 |