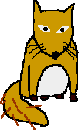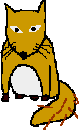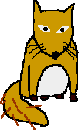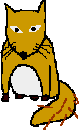債務名義(引渡命令)に表示される請求権
債務名義とは、「強制執行により実現されるべき請求権の存在を公証する一定の格式ある文書」である。
では、引渡命令は、どのような請求権を公証(表示)しているのであろうか。この点については、次のような見解がある(三上威彦・別冊ジュリスト177号103頁参照)。
- 実体法により認められている通常の請求権であるとする見解
これは、さらに2つの見解に分かれる。
- 二元説 債務者については、売買による引渡請求権(債権的請求権)であり、その他の占有者に対しては所有権に基づく引渡請求権(物権的請求権)であるとする見解。
- 一元説 全ての相手方(債務者及びその他の占有者)について、所有権に基づく引渡請求権であるとする見解。この見解は、さらに、(a)
引渡命令の発令のためには請求権の発生要件の全てが充足されることが必要であるとする立場([水元*2020a]305頁、[条解*2019a]831頁・834頁(水元))と、
(b)発令要件と請求権成立要件とを区別し、執行債務者については「不動産占有の有無は審査の対象としない」
(成立要件のうちの占有は引渡命令の発令要件に含まれない)とする立場([中野=下村*民執]581頁)とがある[53]。
前者は、請求権の成立要件を発令要件の中に取り込んでいる(一体化させている)という意味で「一体説」と呼ぶことができ、
また、執行債務者についても占有の有無の審査が必要であるという意味で「占有審査必要説」と呼ぶことができる。
後者は「分離説」あるいは「占有審査不要説」と呼ぶことができ(相手方が執行債務者以外の者である場合については、占有の審査が必要であることは言うまでもない。
そうでないと「占有者」という発令要件が充足されない)。
- 83条1項は、通常の実体法上の請求権(上記Aで挙げた債権的請求権や物権的請求権)とは別個の特別の請求権を規定するものであり、
特別の請求権を公証するものであるとする見解(特別の給付請求権説)。
この請求権の根拠規定は83条であるが、発生した請求権(引渡命令に表示される請求権)を(α)
執行法上の請求権と見る見解と、(β)実体法上の請求権であり、実体法上の請求権を発生させる限りで83条は実体規定であると見る見解とがある。
- 引渡命令は買受人に引渡請求権を新たに付与する形成の裁判であり、新たに形成された引渡請求権が公証されているとする説(形成裁判説。[注解*1986b]245頁(中山))。
上記の議論に関連する次の具体的な問題がある。ただし、引渡制度の機能を考慮する必要があるので、請求権の性質決定からこれらの具体的な問題の結論がストレートに引き出されているわけではない。
- 買受人が競売不動産の第三者に譲渡した場合に、
- 買受人は引渡請求権を失うのか。
- 第三者は引渡請求権を取得し、引渡命令に承継執行文を得ることができるのか 通説は肯定する(三上威彦・別冊ジュリスト177号103頁、[浦野*1985a]382頁、[水元*2020a]300頁など)。
しかし、否定説もある([注解*1986b]335頁(中山))
- 競売不動産を譲渡したことは、買受人に対する請求異議事由になるのか 多数説は異議事由にならないとする(三上威彦・別冊ジュリスト177号103頁はほとんど異論を見ないと述べる)。
これに対して、一元説を徹底させ、執行担当の授権が明示的になされている場合は別としてそうでない限り、異議事由になるとする見解([水元*2020a]300頁)がある。
特別の給付請求権説等の不採用 上記の見解のうち、B説やC説を採ると、引渡命令に対する請求異議訴訟において存否が争われるのは、
実体法により認められた請求権ではないから、
買受人は、請求異議訴訟で敗訴しても、通常の実体法上の請求権を主張して引渡請求の訴えを提起することができることになる[48]
(C説について[注解*1986b]330頁以下(中山一郎))。しかし、それでは紛争解決機能が低下する。引渡命令は通常の実体法上の請求権を公証するものと解すべきである。
一体説と分離説の対立 一元説にあっては、買受人は執行債務者に対しても所有権に基づく引渡請求権を主張することになるが、この請求権は申立人が所有権を有することと、
相手方が目的物を占有していることを成立要件とするのであるから、理論としては、一体説が簡明である。分離説では、執行債務者に対する請求権を物権的請求権としつつ、
債務者の占有の審査を不要としているので、売買契約に基づく債権的請求権が存在すれば発令することができるとしているかのように見え、
その点で「物権的・一元的な把握を必ずしも貫徹していないように見受けられる」([水元*2020a]296頁注13)と批判され、それにも一理ある。
占有審査不要説は、この批判にどのように答えるのか。判決手続においては、訴えにより主張された請求権の存否が判断され、請求権の発生要件が全て満たされないと、給付を命ずる判決が下されることはない
(もちろん、発生要件が充足されても、被告からの抗弁(賃借権の主張)に理由があれば、請求は認容されない)。引渡命令についても同様に考えれば、
そこに表示される請求権の成立要件の充足が発令手続において確認されるべきであり、執行債務者が競売不動産を占有していることも審理対象となる。
しかし、引渡命令は、請求権の存在を確定するものではなく、執行債務者は請求異議の訴えにより請求権の存在を争うことができること、買受人が迅速に引渡しを得ることができるようにする必要があり、
引渡命令の発令手続はそのための簡易な債務名義作出手続であることを重視すると、物権的請求権の発生要件の全部を審査対象とせずに、その内の重要な一部のみの充足を確認して発令することもできてよいことになる。
換言すれば、引渡命令に表示される請求権の発生要件と引渡命令の発令要件とは別個であり、執行債務者に対する引渡命令は、
物権的請求権の発生要件のうちの所有権の取得(売却許可決定の確定と代金の完納)の要件の充足を確認して発せられるものである。
したがって、占有審査不要説が一貫しないと言うよりも、もともと制度設計が物権的請求権説で一貫されていないと言うべきであり、一貫されていない理由は、解決されるべき問題が単純ではない
(引渡命令に表示される請求権を物権的請求権としつつも、買受人が執行債務者から迅速に引渡しを得ることができるようにするために、引渡命令を迅速に発する必要がある)からである。
また、占有審査不要説は、執行債務者については占有の有無を審査せずに発令することができるとしているにすぎず、執行債務者を「不動産の占有者」とみなしている([水元*2020a]296頁注13・305頁注44)のではない。
妥当性の検討 要するに、請求権の成立要件と引渡命令の発令要件とを区別して、引渡命令の制度の特質に基づき、前者が完備しなくても引渡命令を発令することができるとする制度設計も可能であり、
分離説も解釈論として成り立ちうる。問題は、一元説を前提として、占有審査必要説と占有審査不要説のいずれが妥当な結論を導くかであろう。いくつかの事例を想定して、それぞれの妥当性を検討してみよう。
(イ)事件の記録上、債務者以外の者(第三者。債務者の占有補助者でないとする)が不動産を占有していることが明らかであり、かつ、
- 占有者が買受人に対抗することができる占有権原(賃借権等)により占有していることが明らかな場合 (a)占有審査不要説によれば、次のようになる。(a1)この場合には、債務者に対する引渡命令は発せられる;
ただ、執行の現場で第三者が占有していることが明らかになれば、引渡執行は不能となる;第三者に対する引渡命令は83条1項ただし書により発せられない。
これで特段問題はないと考えることもできるが、次のように考えることもできる。(a2)第三者の占有が継続している限り、
債務者に対する引渡命令を発しても、買受人は競売不動産の占有を得ることはできないので、債務者に対する引渡命令が発する必要性は乏しい;のみならず、実務においては、
買受人がその引渡命令を占有者に提示して、法的知識の乏しい占有者が裁判所からの命令があるから諦めなければならないと誤解させるという弊害が指摘され、
この場合には債務者に対する引渡命令を発令しないとの取扱いも;これらのことを考慮すると、この場合にも債務者に対する引渡命令を発することができるとすることは、
行き過ぎである;
この場合には、第三者が競売不動産を退去していること立証が必要であり(ただし、現在は債務者が占有していることまでの立証は不要)、
その立証がなければ債務者に対する引渡命令は発せられないとすべきである。(b)占有審査必要説によれば、事件は前記(a2)とほぼ同様な軌跡を辿るが、
債務者に対する引渡命令を得るには、競売不動産の現在の占有者は債務者であることの立証も必要となる。
- 占有者が民法395条の保護を受ける場合 占有者は6カ月間明渡しを猶予されのであるから、買受人は、占有者に対する引渡命令を得て、その引渡命令により彼から引渡しを受けるべきである。
その点を除けば、1で述べたことが基本的に妥当する。
- 占有者が買受人に対抗することができる占有権原を有するとはいえず、かつ、民法395条の適用を受けない場合 この場合であっても、
第三者に対する引渡命令が発せられて、それが執行されるべきである。それに加えて債務者に対する引渡命令も発することができるかが問題になる。(a)占有審査不要説ではどうか。
一方で、(a1)83条が「債務者又は不動産の占有者」と規定しているので、最初から双方に対する引渡命令を発することはできず、占有者(第三者)に対する引渡命令をまず発し、
それを執行しようとしたところ、第三者が既に立ち退いているため、第三者に対する引渡命令では引渡しを得ることができないことが明らかになった段階で債務者に対する引渡命令を発することができる、
とする立場が考えられる。他方で、(a2)第三者が立ち退いていることが判明してから買受人に債務者に対する引渡命令を申立てさせるのでは、
買受人に迅速に引渡しを得させるという理念が損なわれることを根拠に、第三者と債務者の双方に対する引渡命令を当初から発することができるとする立場が考えられる。
さらに進めば、(a3)買受人が、第三者がすでに立ち退いていて現在の占有者は債務者であると主張するのであれば、その点(債務者の直接占有)を審査することなく、
執行債務者に対する引渡命令のみを発することを許してよいとすることもできよう(買受人の前記主張が誤っていて、実際には第三者がまだ占有している場合には、
あらためて第三者に対する引渡命令を得る必要があるが、買受人がそうすることなく、債務者に対する引渡命令を第三者に示して、第三者の誤解をよいことに第三者から引渡を得たとしても、
大きな利益侵害があったとはいえないとの評価を前提にする)。(b)占有審査必要説によれば、事件は、(a1)とほぼ同様な経過をたどる(占有審査不要説と異なり、
債務者が直接占有者になっていることの証明も必要である)。
(ロ)事件の記録上、執行債務者以外の占有者が存在するとはいえない場合 これは、執行官による現況調査報告書及び評価人の評価書によれば、執行債務者以外の占有者がいない場合を指す。
現況調査や評価人による調査の後に第三者が占有する可能性があり、第三者の直接占有開始が事件の記録に表れるとは限らないので、実際にいる場合といない場合の双方を含む。
(a)占有審査不要説に従えば、買受人の所有権取得(売却許可決定の確定と代金の完納)のみを審査して、直ちに引渡命令が発せられる。
執行の現場で第三者の占有が明らかになれば、債務者に対する引渡命令でその者の占有を排除することはできないので、
その者に対する引渡命令を新たに取得することが必要になるが、通常は執行官がその者の特定に必要な情報(氏名等)を入手するので、引渡命令の発令は容易になる。
(b)占有審査必要説は、この場合でも債務者が競売不動産を現に占有していることの審査が必要になる(引渡命令発令時点では第三者が占有している可能性が残されているからである)。
買受人は、債務者の占有を立証するする必要があり、引渡命令の発令が遅れる。
(ハ)事件記録に、「占有者が執行債務者(又はその占有補助者)であるか第三者であるか不明である」との趣旨が記載されている場合 (a)占有審査不要説によれば、執行債務者に対して引渡命令が直ちに発せられる。
その後の展開は、(ロ)と同じである。(b)占有審査必要説によれば、占有者が債務者であるか第三者であるかの立証に成功するまで引渡命令の発令は遅れるのみならず、
最悪の場合には、占有の立証がないことを理由に、債務者に対する発令申立ても第三者に対する発令申立ても棄却されることになる。
以上の通観すると、占有審査不要説を原則とするのが妥当であろう。その方が、買受人に対抗できる占有権原を有する者がいない場合に、代金を納付した買受人に迅速に占有を得させることができるからである。
ただ、(イ)1の場合にまで、債務者に対する引渡命令を発令して良いかは問題である。買受人は、自己に対抗できる占有権原を有する者が存在すること前提にして買受申出をしているのであるから、
不動産の現実の引渡しを得ることが遅くなるのは承知のはずである。そうであるならば、発令時にその占有者が存在しなくなり、予想外に速く現実の引渡を得ることができるようになった場合に、
当該占有者が現在はいないことを立証させ、その立証に手間取って引渡命令の発令が遅れたとしても、その不利益は彼に甘受させてもよいであろう。同様なことが、イ2の場合についても妥当する。
したがって、発令要件は、次のように設定することが考えられる。債務者に対する引渡命令については、彼の占有は審査事項にならないのが原則であるが、
例外的に、事件の記録上、占有者(第三者)が買受人に対抗することができる占有権原を有することが明らかな場合及び民法395条の保護を受ける場合には、
それらの者が競売不動産から退去していることを主張・立証することが必要である。
このように発令要件を設定すると、買受人の代金納付後に占有者が不動産を債務者に引き渡してしまった場合の処理が問題になる。
しかし、例えば占有者(第三者)の占有権原が賃借権である場合には、買受人は、代金納付の時点で賃貸人になり、賃借人に対して建物退去の場合には自己に引き渡すように求めることができるのであるから
(前述のように、前所有者(執行債務者)からの指図による占有移転は必要ない)、占有者が債務者に引き渡すという事態まで想定しなくてもよいであろう。もしそうした事態まで想定しなければならないようであれば、(イ)の
1及び2場合についても、買受人は代金納付後直ちに(86条2項により6カ月以内に)債務者に対する引渡命令を申し立てることができるという所に戻らなければならない。
なお、債務者を相手方とする発令手続において買受人に対抗することができる占有権原を有する占有者が存在する場合には発令されないという要件(消極的要件)の充足が問題になる場合に、
その消極的要件は、債務者の保護というより占有者の保護のためのものであるのに、占有者は手続上の当事者になっていないので、その保護の趣旨を貫徹しようとすると、
この消極的要件の充足は職権調査事項かつ職権探知事項とする必要があるが、判断資料は「事件の記録」に限定されているのであるから、問題はなかろう。
法定地上権が成立する場合 債務者に対する発令要件を代金完納(及びその前提としての売却許可決定の確定)とすると、そして83条1項を度外視すれば、法定地上権が成立する場合でも債務者に対して引渡命令を発することができることになる。
引渡命令により建物収去の強制執行はできないとの立場に立てば、実害はそれほど大きいとは言えないが、それでも、建物直下の土地以外引渡命令が執行されることになる。これを避けるためには、
債務者は請求異議の訴えを提起しなければならず、その訴訟が実質的に法定地上権の範囲を確定する役割をもつ。
それでは、債務者の負担が重すぎないかと考えれば、83条1項ただし書がこの場合に適用されないかが問題になる。民事執行法制定当初の同項ただし書は、債務者を対象とする規定ではなかった。
しかし、平成8年改正後の同項ただし書は「買受人に対抗することができる権原により占有していると認められる者」となっており、「占有している[と認められる]者」の中に債務者を含めることは可能である。
いずれに提訴責任を負わせるのが公平であるかの問題になるが、法定地上権が成立することが事件の記録上明らかな場合には、買受人に提訴責任を負わせるのが公平に合するように思われる[52]。
債権的請求権 執行債務者と買受人との間には前者を売主とする売買契約があるのであるから、売買契約に基づく引渡請求権(債権的請求権)を引渡命令に表示される請求権と考えることもできないわけではない。
では、一元説はなぜ債権的請求権を除外するのか。その理由は、それほど明瞭ではないが、次のように考えてよいであろう。
(α)債権的請求権説では、法定地上権が成立する場合でも引渡命令が発せられることになるから、採用できないとする見解([条解*2019a]831頁(水元))がある。
しかし、この論法で行けば、買受人が債権的請求権を主張して引渡請求の訴えを提起すれば、法定地上権が成立していることは抗弁とならず、請求が認容されてしまうことになろう。
しかし、それは不当な結論である。通常の土地の売買契約において、売主のために地上権設定契約が同時に締結されていれば、売買契約に基づく現実の引渡しを求める請求権(「現実引渡請求権」と呼ぶ)は発生しないと解すべきである[54]。
競売により法定地上権が成立する場合にも、現実引渡請求権が生じないとの条件で売却されたと見るべきである。
したがって、上記の理由付けも債権的請求権説を否定する強い理由になるとは思われない。(β)強制執行は債務名義に基づいてなされるものであり、債務名義に表示されている権利(執行債権)の存否には依存せず、
債務名義成立後に執行債権が消滅していた場合でも、買受人は強制競売により有効に所有権を取得する;しかし、執行債権者自身が買受人になった場合にまでそのように考えてよいかは、別個の問題である。
この買受人は、執行債務者に対して所有権を主張することができない、あるいはそもそも所有権を取得していないと考えることができる。そのように考える場合でも、執行債務者に対する引渡命令は発せられる。
これに対して執行債務者は、前記の事情を主張して、請求異議の訴えを提起したときに、引渡命令に表示されている請求権を物権的請求権としておけば、買受人の所有権取得を直接問題にすることができ、
中間確認の訴えにより買受人の所有権の存否を訴訟物とすることができる(その説明が容易になる)。(γ)執行債務者が競売不動産を占有していない場合には、
彼に対する引渡命令の執行をしても意味がない(引渡執行に際して他の者が占有者として登場すれば、執行官は執行をおこなうことができない)から、
請求異議の訴えにより引渡命令の執行力を除去することができるとしておくのがよい(その方が法律関係が簡明になる)。引渡命令に表示されている請求権を物権的請求権と考えるとそれが可能であるが、
売買契約に基づく債権的請求権と考えるとそれができない。
特定承継人
(α)引渡命令が確定した後に買受人が競売不動産を他に譲渡すると、譲受人は、承継執行文を得て(23条1項3号・27条2項)、引渡命令の執行を申し立てることができる。
この場合に、承継の有無は27条2項・32条・33条・34条所定の手続の中で確認され、それは引渡命令の発令手続とは別個の手続であり、別個の手続において特定承継の有無を確認することは、
引渡命令の発令手続の簡素化の要請に反しない。(β)引渡命令の発令申立て後・確定前に譲渡がなされた場合には、譲受人が申立手続に参加して(民執法20条、民訴法49条・47条)、
自己を名宛人とする引渡命令を得るのが本来である。しかし、競売手続の付随的手続にすぎない発令手続において特定承継の有無を審理する負担が生じないようにする必要があり、承継参加は許されない。
その代償として、相手方は買受人が所有権を譲渡したことを理由に引渡命令の発令を争うことはできないとすべきである。また譲受人は、債務名義成立前の承継人であるが、
それでも承継執行文を得ることができると解すべきである(23条1項3号が拡張的に適用される。買受人は、承継人の法定訴訟担当者として発令手続を追行すると見ることもでき、その場合には、23条1項2号により執行力が拡張されると見てもよい)。
(γ)買受人が引渡命令の申立てをする前に、競売不動産を譲渡していた場合も同様である。
競売不動産の譲渡と請求異議の訴え
引渡命令に表示されている請求権は、所有権に基づく引渡請求権であるので、買受人が競売不動産の所有権を有さなくなれば、その請求権を有さなくなり、
買受人が引渡命令に基づいて引渡執行をすることは許されないのが本来である。このことを買受人Aが競売不動産を他者Bに譲渡した場合について考えてみよう。
(α)確定した引渡命令に譲受人Bが承継執行文の付与を得たとしよう。その後に、相手方が買受人Aの所有権喪失を理由にAに対して請求異議の訴えを提起しても、
Bとの関係でその債務名義の執行力を排除することはできない。したがって、Aが不動産の譲渡を認め、強制執行の申立てをする意思のないことを明示している場合には、
相手方は、Aに対して請求異議の訴えを提起する利益を有しないと解してよい。
同じことは、承継執行文がBに付与される前であっても、概ね妥当する。
ただ、(β)Bに承継執行文が付与される前は、A自身が単純執行文を得て強制執行の申立てをする可能性があるので、相手方がAに対して請求異議の訴えを提起すること自体は適法としてよい。
その場合に、「買受人は不動産を譲渡して現在は所有者でない」との異議事由をどのように取り扱うかが問題になる。次の2つの選択肢が考えられる。
(β1)Aが不動産を譲渡して現在は所有者ではないことを理由とする請求異議の訴えが提起されて異議が認容されても、既判力の標準時前の譲受人であるBとの関係では、
引渡命令の執行力は排除されず、Bは依然として承継執行文を得て強制執行を申し立てることができる。(β2)請求異議の訴えにより執行力が排除された債務名義に承継執行文を付与することは、
一般論として(異議事由が何であるか、異議認容判決の既判力の標準事前に譲渡が立ったか否かに関わらず)適切ではないことを前提にして、相手方は、買受人が不動産を譲渡したことを異議事由にすることができない。
いずれをとるべきであろうか。金銭の支払を命ずる判決の確定後に原告が金銭債権を譲渡した場合を考えてみよう。AがBに債権を譲渡したということができるためには、
Aから債務者に譲渡通知がなされること(又は債務者の承諾)が必要である(民法467条)。その譲渡通知がなされた後では、債務者は、前記(α)のような場合を除き、
Aに対して請求異議の訴えを提起し、債務名義の執行力を排除することができるとしておく必要があり、前記(β2)のような選択肢を採ることはできず、(β1)の選択肢が採られるべきである。
そうであれば、所有権に基づく引渡請求権を表示する債務名義一般についても、(β1)の選択肢を採るべきである。
最判昭和63年
最高裁判所 昭和63年2月25日 第1小法廷
判決(昭和62年(オ)第491号)判決は、次のように説示する:「不動産の引渡命令の発付を受けた買受人が当該不動産を第三者に譲渡したとしても、
引渡命令の相手方は、右買受人に対して提起する引渡命令に対する請求異議の訴えにおいて、右譲渡の事実をもつて異議の事由とすることはできない」。
理由が示されていないので、どのような考えに基づくのか明瞭でない。一方において、引渡命令に表示される請求権は所有権に基づく物権的請求権ではなく、
買受人に与えられた独自の請求権であり、競売不動産の譲渡によっても失われないと理解することもできる。他方において、引渡命令に表示されているのは、
物権的請求権であることを前提にすると、前述(「競売不動産の譲渡と請求異議の訴え」後段)のとおり、一般の債務名義であれば正当な異議事由となる請求権喪失を異議事由にならないとしているのであるから、
引渡命令に限定しての説示と見るべきである([下村*2005a]174頁は「引渡命令の効力維持の必要」に基づくものであると説明する)。
この事件において買受人から第三者(買主)への所有権移転登記はすでになされているが、引渡しについてどのような合意がなされていたのかよく分からない第三者が一般人であれば、引渡しの強制執行などはしたくないので、
転売人である買受人に執行させ、買受人から任意の引渡しを得るとの条件で買い受けることが多いであろうことは、容易に想像できる。
したがって、代金の一部の支払が留保されていて、買受人が執行債務者から引渡しを受けて第三者に引き渡すのと引き換えに代金の残額が支払われるとの合意がなされていたと推測してよいであろうか。
最高裁は、競売の促進のために、その需要に応じようとした。この需要に応ずるためだけであるならば、転買人からの授権があること要件にした任意的執行担当を認めることで足り、
また、前記の推測からすれば、任意的執行担当の合意が黙示的になされていた理解できる。しかし、最高裁は、こうした問題に立ち入ることを避け、理由のない結論だけの判決をした。
判旨を上記の理由に基づく引渡命令に特有のルールとして正当化することができるかはなお問題であるが、最高裁判例として通用させるのであれば、上記の理由に基づくものとして通用させるべきであろう。