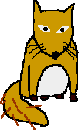
民事執行法概説
不動産の強制競売 2/4
栗田 隆
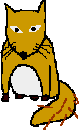
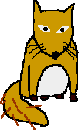 |
民事執行法概説不動産の強制競売 2/4関西大学法学部教授
栗田 隆 |
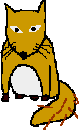 |
注意 リンクされている民法の条文は、平成29年改正前のままである。
条文番号等は、適宜改正後のものに書き直している。
なお、以下では「賃借権を引き受ける」といった表現がよく用いられるが、これは、「賃借権という負担を引き受ける」の簡略表現であり、「賃借権という負担の付いた不動産を取得する」の意味である。「担保権を引き受ける」等についても同じである。
執行裁判所の競争相手
不動産市況に依存することであろうが、すでに競売開始決定がなされ差押えの登記がなされた不動産であっても、不動産業者が転売目的で買い受けることがある。不動産業者は、期間入札の公告より前になされる配当要求の終期の公告(49条2項)から競売物件に関する情報を入手するとのことである。そして、競売申立債権者に買取価格を提示して任意売却を促す。債権者は、裁判所が定める売却基準価額より2倍以上の買取価格が提示されれば、これに応ずる(正確には、債務者にその価額で任意売却をするように説得する)とのことである[57]。
執行売却の競争相手として任意売却が存在し、その競争は競売開始後もこうした形でも生ずる。任意売却による買取りを債権者に申し出る不動産業者は、執行実務では、「任意売却業者」と呼ばれる(ここでは「転売業者」と呼ぶこともできるものとする)。こうした任意売却業者が執行売却によることなく不動産を買い取ると、執行裁判所の売却する不動産は減少するので、任意売却業者は執行裁判所の競争相手と位置づけることができる(こうした不動産業者は、同時に執行売却において買受申出人となるので、執行裁判所の顧客でもある)
小さな政府の思想からすれば、 公的機関と民間事業者との間にこうした競争関係が存することは、一般論としては好ましいことである(公的機関の仕事が減少し、これに投入される税金が減少すれば、なおよい)。ただし、次のような問題も指摘されている。(α)競売不動産の所有者(債務者)に多数の任意売却業者が接近して売却の勧誘を熱心にし、生まれて初めて財産の差押えを受けて途方に暮れているのが通常であろう債務者をさらに困惑させる。その結果、(β)その後に執行官・評価人が調査に訪れても、非協力的態度をとることがある[58]。
とはいえ、こうした競争相手が現れるのは、権利関係が比較的単純な事件(特に所有者が占有者である事件)であろう。 賃借人が存在する不動産の任意売却では、賃借権は、抵当権に後れるものであっても、買取人引き受けられるので、賃借権の消滅を前提に売却する方が高額での売却が見込むことができる場合には、執行売却を選択せざる得ない。また、執行売客であれば買受人に対抗できない権原により占有する者(所有者、使用借人、抵当権に後れる賃借人さらには無権原占有者)が任意売却の交渉において明渡しに消極的な態度を示せば、引渡命令制度を利用することができる執行売却の方が、高額での売却を期待できよう。