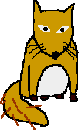
民事執行法概説
不動産の強制競売 4/4
関西大学法学部教授
栗田 隆
栗田 隆
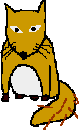
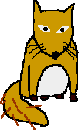 |
民事執行法概説不動産の強制競売 4/4関西大学法学部教授
栗田 隆 |
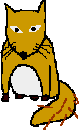 |
| | 割付額 | 抵当権者 | 一般債権者 |
|---|---|---|---|
| 土地α | 1000万円 |
1000万円 |
0円 |
| 土地β | 1000万円 |
1000万円 |
| | 割付額 | 抵当権者 | 一般債権者 |
|---|---|---|---|
| 土地α | 500万円 |
500万円 |
0円 |
| 土地β | 1500万円 |
1500万円 |
| | 第1順位抵当権者 | 第2順位抵当権者 |
|---|---|---|
| 土地α | A:1000万円 |
B:2000万円 |
| 土地β | B:2000万円 |
A:1000万円 |
| | 論 点 | 請求異議の訴え(民執35条)・定期金賠償の変更の訴え(民訴117条) | 配当異議の訴え |
|---|---|---|---|
| 90条関係 | この解決方法がとられるべき場合 | 債務名義を有する債権者に対して債務者が異議を述べる場合(90条5項) | 左の場合以外(90条1項)
|
| 1週間以内に執行裁判所に対して次のことをしないと、配当異議の申出の取下げが擬制される(90条6号) | 起訴の証明、及び、執行停止を命ずる裁判の正本の提出(民執36条・民訴403条1項6号)。 | 起訴の証明 | |
| 91条関係 | 次の事由が生ずると配当等の額に相当する金銭が供託される(91条1項) | 39条1項7号の執行一時停止文書(91条1項3号) | 配当異議の訴えの提起(91条1項7号) |
| 92条関係 | 原告である債務者が勝訴したときに拡大的処理(絶対的処理)がなされるべきことを定める規定 | 92条2項前段・91条1項3号(原告は債務者であるので、常に拡大的処理となる) | 92条2項後段・91条1項7号(債務者が原告の場合に拡大的処理となる) |