破産債権2
栗田 隆
|
破産法学習ノート
破産債権2関西大学法学部教授
栗田 隆 |
物上保証人の求償権・代位権
弁済者代位制度について
| 主債務者/主債務 債権者に対して第一次的に給付をなすべき債務者/その者が負っている債務。通常は、保証人との対比で用いられるので、
「主債務」は、「保証人によって保証された債務」と同じであり、「被保証債務」と言い換えることができる。 |
(債権額100万円) (破産) |
例えば、債権者(X)が、複数の債務者(YとZ)から全部で100万円を受領することができ、かつ、各債務者に対して、その全部(100万円)の支払を請求できるという債務関係を全部債務関係と言う。 保証債務関係や連帯債務関係がそうである。
全部債務関係にある債務者の全員又は一部の者について破産手続が開始された場合の取扱いは、次のようになる[CL3]。 なお、事例の単純化のために、委託を受けた保証の場合を主に取り上げることにするが、内部的負担割合の問題 (特に、そのことに由来する求償権の問題(連帯債務者について民法442条参照))を除けば、以下の説明は、連帯債務者やその他の全部義務者にも妥当する。
(注)弁済額等:=弁済等による債務消滅額 |
平成29年改正後の民法502条は脇に置いて説明しよう。債権者Xは、それぞれの破産手続にその開始時の債権額を基準にして債権を届け出て、配当を受けることができる。 例えば、Yの破産手続開始前にZがXに保証債務の一部履行として10万円を支払っている場合に、破産手続開始時には、XのYに対する債権額は90万円になっており、 債権額を90万円にしてYの破産手続に参加することができる(1項)。 XがYの破産手続に90万円の債権額で参加した後で、Zが追加的に一部弁済(60万円)した場合でも、 XがYの破産手続において行使することができる債権額は、手続開始時の債権額90万円のままである(2項)。 これを「開始時現存額主義」[48]という[65]。
超過配当が生ずる場合の処理
前記の例で、Yの破産手続における配当率が6割の場合には、開始時現存額の90万円を基準にすると、Xは54万円の配当を受ける立場にある。
Xに54万円を配当すると、Xは、Zから代位弁済を受けた金額(10万円+60万円)と合わせると、総計で124万円を受領することになり、当初の債権額を超過することになる。
超過分の24万円は、保証人に帰属すべきものである(破産財団に帰属するとの見解もあるが、賛成できない)。その実現方法として、基本的に次の2つの方法が主張されている。
なお、破産手続開始後にZがXに弁済した時期は、議論の単純化のために、債権届出期間内であるとしよう
(この時期であれば、将来(すなわち、Xが全額の満足を受けた時に)行使可能となる求償権の届出をすることについても、
将来生ずる原債権の移転(名義変更)を届け出ることについて、時期を失しているということはない)。
最高裁判所 平成29年9月12日 第3小法廷 決定(平成29年(許)第3号)は、B説をとるべきことを宣明した(ただし、債権者に対する保証人の不当利得返還請求の問題は、当該事件では直接問題になっておらず、その可能性を示唆にするにとどまる)。 しかし、B説は、Zの利益(超過配当分24万円の受領)の実現にとって迂遠であり、かつ、Xについて破産手続が開始されている場合には、ZはXの他の債権者と割合的満足を強いられることになるので、 Zの利益保護が不十分になる。A説を採用すべきである。ただし、Zが破産手続に参加していない場合には、最終的にはZが受領すべき超過分をXに配当し、ZがXにその返還を求めることができるとすべきである。
供託による解決 上記の説明では、債権者と保証人との間で争いがあるか否かを考慮していない。これを考慮して場合分けをすると、問題解決の議論の様相は若干異なってくる。 超過配当額をどうするのかは、債権者と保証人との間の取合いの問題であり、他の破産債権者への配当額に影響を与えない問題であると位置づけてよく、債権者と保証人との間で解決してよいと思われるからである。 したがって、まずは保証人の破産手続参加を肯定すべきである(前記Aで述べたことが基本的に妥当する)。これを前提にして、解決方法は次のように整理される。
上記のいずれの場合であっても、配当表の記載に不服のある者は、裁判所に対して異議を申し立てることができる(200条)。前掲最決 平成29年の事案では、破産管財人は、b3に該当するとして、配当表の記載を変更し、これに対して債権者が異議を申し立てた; 裁判所は、「債権者が主債務者の破産手続に参加した場合には、破産手続開始後に破産債権の一部を弁済した保証人(求償権者)は, (α)当該債権について超過部分が生ずるときに配当の手続に参加する趣旨で予備的にその求償権を破産債権として届け出ることができず(104条3項ただし書)、 また、(β)当該配当の段階において,債権者が有した権利を破産債権者として行使することができず(104条4項)」としたが、実体法上の法律関係に即した処理を否定するものであり、適切でない。 ただ、この事件においては、開始時現存額を基準にした配当を債権者に与えると普通破産債権部分の残存額を超過することが問題にされたのであり、 配当金を劣後的破産債権部分にも充当すると超過額は生じない事案であった。配当金を債権者と求償権者のいずれにどのように与えるべきかの問題であり、 両者の間では普通部分と劣後部分の区分は問題にする必要はなく、劣後部分も含めて債権者が満足を得て余剰があれば求償権者に与えるべきであるとの立場からすれば、 この事件は、b3に該当し、配当金はその全額が債権者に与えられるべき事案であった。したがって、結論自体は正当であった。
超過配当の問題を一般化すると、最後配当の除斥期間満了後・配当額の支払前に債権者が保証人の財産から満足を得、保証人がその旨の通知(民法463条3項)を破産管財人にした場合にどうするか、 債権者は劣後的破産債権部分についても求償権者に優先するとの立場に立つと、劣後部分(破産手続開始後の損害金)は日々発生するので、その計算の負担を破産管財人に負わせてよいのかといった問題が生ずる。 破産手続が開始されていなければ、債務者は損害金額も計算して債権者に弁済し、次に求償権者に弁済をすべきであることを考慮すると、破産管財人にその事務作業を負わせてもよいと思われる。 これを前提にすると、最後配当の除斥期間満了後・配当額の支払前に債権者が保証人の財産から一部満足を受けた場合にも、その一部満足も考慮して超過配当が生ずるかどうかを破産管財人は判断すべきである。 突き詰めれば、債権者が全額の満足を得た時点で破産債権(原債権)の移転(代位による移転)が完了するのであり、 破産債権の他の形態での移転(転付や譲渡)がいつまで許されるかの問題と同様に扱ってよい。詳細は、[栗田*2018b]参照。
保証人Zの破産手続が開始された後で主債務者Yが一部弁済した場合(Yの破産財団から配当がなされる場合を含む)にも、同様に、Xは、Zの破産手続開始時の債権額を基準にして配当を受けることができる。 ただし、この点については、YがZに対して求償権を取得することはないことに鑑み、手続開始後の一部弁済額を控除した金額を基準にしてXに配当を与えるべきであるとする見解もある[70]。 しかし、それは、104条の規定の文言に合致しないし、また、責任財産の集積により債権回収を確実にするという全部義務制度を破産法上も尊重すべきであるとの立法趣旨と調和しない。
破産手続開始前の代位弁済による求償権
平成29年民法改正により、一部弁済による代位に関する民法502条も改正され、(α)同条3項にいう
「当該権利の行使によって得られる金銭」の中に「原債権への破産財団からの配当金」も含まれるのか、 (β)「原債権者の権利は。・・・代位者が行使する権利に優先する」の中の
「代位者が行使する権利」に代位取得した原債権の一部の外に求償権も含まれるのかが問題になる。
いずれも肯定するならば、一部代位弁済の場合における求償権の処遇は、改正前と異なることになるが、かなりの議論を要する問題である。その議論は後ですることにして、
ここでは、両方とも肯定されることはない(少なくとも一方は否定される)ことを前提にしよう。すると、民法改正後も改正前と同様に、破産手続における求償権の処遇は、次のようになる。
主債務者Yの破産手続開始前に保証人Zが主債権者Xに弁済をしたことによりYに対して取得した求償権は、Xが全部の満足を受けているか否かにかかわらず、Zが破産債権として行使することができる。 このことは、この求償権がZの一般債権者の満足に充てられる責任財産になり、また、Zがその求償権を通常の順位の債権として(Yの破産手続においてXの債権と同順位の債権として)処分することができることを意味する。 したがって、開始時現存額主義は、全部義務者の一人の破産手続開始前に共同義務者が債権者に弁済をしたことにより取得した求償権との関係では、 その求償権の財産的価値を尊重し、求償権の処分を可能にする制度であるということができる(当初債権額主義との相違点)。
破産手続開始後の代位弁済による求償権
Yの破産手続開始後にZがXに弁済することによりZがYに対して取得する求償権(破産手続開始の時点においては、将来の事後求償権)あるいは代位により取得する原債権の行使については、
Xが破産手続に参加していない場合(3項本文)と、参加している場合(3項ただし書・4項)とに分けて規定が置かれている。
(1)債権者Xが参加していない場合(104条3項本文) 共同債務者Zが破産手続中に弁済をして現実に求償権を取得してからその届出をすることができるとしたのでは、 その弁済が債権届出期間経過後になってしまったときに、彼の費用負担で特別の債権調査を行うことになり、彼の負担が重くなる。 そこで、代位弁済前でも将来の事後求償権を届け出て、その全額について破産手続に参加することができることが明示された(3項本文)。 将来の請求権を届け出た者が配当を得るためには、その請求権が最後配当の除斥期間満了前に行使可能になっていることが必要である(198条2項)。このことは、将来の求償権にも妥当する。 すなわち、Zが最後配当の除斥期間満了前に弁済をしなければ、配当から除斥される。
(2)債権者Xが参加している場合(104条3項ただし書) 債権者が全部義務請求権を届け出ている場合には、 共同債務者は、将来の求償権について配当を得ることはできない。 破産者の1つの給付義務(開始時の現存額における給付義務)に対して複数の者からの給付請求権の行使を認めるべきではないからである。 3項ただし書は、参加を認める本文の適用を排除する形でその趣旨を規定した。
破産手続開始後に共同債務者が債権者に弁済をした場合には、これにより生ずる求償権と代位取得する原債権(民法500条)の取扱いが問題になる。
(2a)破産手続開始後における共同義務者の弁済が債権者の全額の満足に至らないときは、債権者は、依然、手続開始時の債権全額を破産債権として行使することができる(2項)。 他方で、一部弁済者は、一部弁済により取得する求償権について配当を得ることもできない[CL8]。 また、彼は、債権者に代位することができない(104条4項、 最高裁判所平成14年9月24日第3小法廷判決(最高裁判所平成12年(受)第1584号)[5])。 なぜなら、(α)彼は、全部義務者としての義務をまだ果たしていない段階では、 債権者が全額の満足を得ることを妨げる結果になるような権利行使をすべきではなく、 (β)その意味で、全部義務者の求償権は、債権者の債権に後れるべき性質のものだからである。 このような結果に終ることを想定して(あるいは最後配当終了時から回顧して)、 「共同債務者は、債権の全額の満足に至らない場合には、 破産手続開始後の一部弁済により取得した求償権を破産手続において行使することはできず、また、債権者に代位することもできない」と言う。設例:
(2b)破産手続開始後に破産者の共同債務者が債権者に弁済することにより、債権者が全額の満足を得たときは、共同債務者は、原債権者優先原則に制約されることなく求償権を行使することができる。 のみならず、弁済者代位による原債権移転の効果が破産手続との関係でも生じ、債権者による債権届出の効果(届出期間内に届け出られている場合には一般の債権調査を受けることができるとの効果、 その債権が確定している場合には確定の効果)を利用できるようにすることが便宜にかなうので、4項において、自己の求償権の範囲で原債権を行使することができる旨が明示されている。 この場合に、原債権の行使は、届出名義の変更の届出(113条1項)により行うことができる。
(2c)破産手続開始後に破産者の共同債務者が債権者に一部弁済をして破産者に対して求償権を有している場合に、破産財団からの配当により債権者が全額の満足を得るときにも、 共同債務者は、原債権者優先原則に制約されることなく求償権を行使することもできるとすべきである。破産法104条4項の「その債権の全額が消滅した場合」の要件は充足されるのであるから、 債権の消滅原因が求償権者(共同債務者)からの弁済等ではないので同項が直接的な適用はないとしても、その類推適用を肯定してよいと思われるからである。設例:
ただし、最高裁は、これと異なる考えを採用している。事案は、主債務者の破産手続開始後に物上保証人の財産から一部弁済がなされた事例であるが、そこで示された説示は上記1の場合にも妥当しよう。
この解決は、債権者が配当時に現存する債権額を超えて受領した配当金(過大配当金)を債権者が保持することを容認するものではなく、 その帰趨は債権者と保証人との間の不当利得の問題として解決すればよいことを前提にしている。しかし、債権者についても破産手続が開始されている場合には、 保証人は過大配当金を部分的にしか回収できないことになる。 保証人に主債務者の破産手続に参加することを認め、保証人が過大配当金を破産管財人から直接受領することができるようにする方がよい。
この立場に立つと、破産手続後に保証人が多くの弁済をなし、配当率の高さと相俟って超過配当が生ずる見込みがある場合に、債権者が全額の満足を得た時点で保証人が行使できる原債権を届け出ることは許される。 104条3項ただし書は、二重請求を防止することを目的としており、この届出を禁止するものではない。
問題となるもの
104条4項により原債権を行使する場合の求償権の届出の許否と要否
破産者の共同債務者が104条4項により原債権を行使する場合に、同項が「求償権の範囲内において」原債権を行使することができると規定しているので、
事後求償権(以下「求償権」と略す)の行使について、次の2つの問題が生ずる。
(a)許否の問題 求償権者は、原債権の外に求償権を破産債権として行使することができるか。この問題については、次の2つの見解がある。
次のように考えたい。(B')保証委託契約において求償債権の利率を被保証債権の利率よりも高く定めることは許容されており、破産手続開始後の利息債権は劣後的破産債権になるが、 劣後的破産債権に配当がなされる場合がないわけではないことを考慮すると、求償権額が被保証債権(原債権)額を上回る場合には、求償権の行使を認める必要がある。また、原債権が単に届け出られただけであり、 まだ確定しておらず、債権届出期間が満了していないため求償権を届け出てもその調査に格別の負担が生じない場合には、求償権者は、求償権も破産債権として確定されることにより、 求償権自体について時効期間の延長(民法169条1項)の利益を得ることができる(原債権が確定しただけではこの利益は得られない。最高裁判所 平成7年3月23日 第1小法廷 判決(平成3年(オ)第1493号)参照)。これらのことを考慮すれば、債務者の破産手続開始後に代位弁済をした求償権者が原債権の外に求償権を行使することは、 一般論としては肯定すべきである。いずれか一方のみを選択的に行使することができるとすべきか、双方の届出(原債権については届出名義の変更の届出)をすることができるとすべきかは迷う (もちろん、後者にあっては、二重配当が生じないように、原債権と求償権の関係を明示して届け出るべきであることを前提にする)。 しかし、求償権自体は優先的破産債権ではないが代位取得した原債権は優先的破産債権である場合には、両債権を破産債権として届け出ることは認めるべきであろう (求償権については、時効中断の必要があり、原債権はより多くの配当を得るために行使する必要がある)。そして、両債権を重畳的に届け出ることに特に問題があるとも思われない。 両債権の関係を明示して原債権の届出名義の変更の届出をすると共に求償権を届け出ることも許されると解したい (原債権のうち劣後的破産債権部分への弁済により生ずる求償権は、 劣後的破産債権になる)[80]。
(b)要否の問題 求償権者は、求償権の範囲内で原債権を行使するために、原債権の届出あるいは届出名義の変更とともに求償権も破産債権として届け出て、 破産債権者間で確定させておくことが必要であるか。これはあまり議論されていない論点である。次の2つの立場が考えられる。
条文の文言は、不要説に有利である。そして、実務は不要説に立っているように見える(最判平成7.3.23民集49-3-984は、 ≪破産手続において確定した原債権の時効期間が民法174条の2[平成29年改正後の169条1項]によって10年になる場合でも、これにより求償権の消滅時効まで10年になるのではなく、 求償権が短期消滅時効により消滅すればその確保のために代位取得した原債権も消滅する≫との趣旨を説示している。これは、不要説を前提にして初めて生ずる問題である)。
迷いはあるが、破産法がこの問題について明確な規定を置いているとは言い難いこと、実務は不要説で運用されていることを考慮すると、不要説で良いであろう[57]。 この立場に立っても、求償権について民法169条1項の適用の利益を得るために、原債権の代位取得者あるいは代位取得する予定の者が、 現在の求償権又は将来の求償権を届け出て確定させることは許されるとすべきである。
債権者X───全部義務請求権α─→主債務者Y | | └────全部義務請求権β─→保証人Z |
Zは、XのYに対する債権20万円分を代位弁済により取得したが、これをYの破産手続において行使できるか。 |
「将来行うことのあるべき求償権」の届出
被保証債権者が破産手続に参加しているが、破産手続終了時までに全額の満足を得ることが見込まれる場合に、
保証人は破産手続開始後の弁済によりすでに取得している求償権又は近い将来に取得する求償権を届け出ることができるかが問題になる。
破産法104条3項ただし書・4項の規定を考慮して、この届出はしばしば「予備的届出」と呼ばれる。 しかし、届け出られた求償権について配当を得ることについて条件が付されていることを認めた上での届出であり、
届出自体は無条件であると解する立場もある。
この点について、次のような見解がある。なお、被保証債権者が全部の満足を受ける場合の最後の満足は、次のようにいろいろなものがあり得るものとする:
保証人の財産からの満足(任意弁済あるいは担保権の実行)、主債務者である破産者の財産からの満足(被保証債権の全額の満足に至るまでの破産配当、担保権の実行)。
104条2項から4項の規定は、物上保証人に準用される[27]。すなわち、
主債務者の破産手続開始後に物上保証人が責任を果たしたが、債権者は未だ全額の弁済を得ていない場合に、104条5項・4項は、物上保証人の求償権を債権者の主債権に劣後させている。しかし、 その根拠は、それほど強くない。すなわち、人的保証人が一部弁済をしたにとどまる場合の求償権については、債権全部についての弁済義務を果たしていないから、 その求償権は主債権に後れると説明することができるが、 物上保証人は、物上保証に供された財産の範囲でのみ責任を負っており、それが主債権の満足に充てられたことにより、責任をすべて果たしているからである。 しかし、責任の集積により債権の効力を強化するとの目的に奉仕する点では、人的保証人などの全部義務者と異ならないとの理由で([小川*2004a]153頁)、 物上保証人の求償権は、全部義務者の求償権と同列に置かれ、主債権者の債権に後れるものとされたのである。
ここで強調されるべきは、次のことであろう。
小 括
受託保証人が主債権者に弁済したことにより代位する被保証債権(原債権)と求償権との関係を整理しておこう。
問題を明確にするために、求償権の利率は被保証債権の利率よりも高いものとする(例えば、前者は10%で後者は4%とする)。
受託保証人が被保証債権の一部を弁済したにすぎない場合には、これらの2種の債権と主債権者が有する残存債権との間の弁済の優先関係が問題となる。 問題となる場面は、
これから弁済がなされる場合の原資が何であるかに従い、(α)被保証債権のために主債務者の財産上に設定されていた抵当権が実行される場合と、
(β)主債務者が破産してその一般財産(破産財団)から弁済される場合、(γ)主債務者が未だ破産していない場合に、
強制執行によりその一般財産から弁済される場合とに分けることができる。
表に整理しておこう。
| 弁済原資と手続 | 主債権者の残存債権と保証人が代位取得した債権との関係 | 主債権者の残存債権と事後求償権との関係 | 主債権者の残存債権と将来の事後求償権との関係 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| (α)担保執行の配当財団(担保財産) | 主債権者の残存債権が優先する。 | [求償権は被担保債権ではないので、問題にならない] | |||
| (β)破産財団 | (β1)破産手続開始前に保証人が一部弁済 | 平成29年民法改正前にあっては、平等(破産法104条1項。開始時現存額主義)。 改正後は、同法502条3項により原債権者が優先すると解される。 | 平成29年民法改正前にあっては、平等(破産法104条1項。開始時現存額主義)。 改正後は、民法502条3項により原債権者が優先すると解する見解もある。 | [β2・β3参照] | |
| (β2)破産手続開始後に保証人が一部弁済 | 主債権者が破産手続に参加する場合 | 主債権者の残存債権が優先する(104条2項) | 主債権者の残存債権が優先する(104条2項) | ||
| 主債権者が破産手続に参加しない場合 |
(*1) |
事後求償権による破産手続参加が可能(104条3項はこのことを前提にしている)(*2) |
将来の事後求償権による破産手続参加が可能(104条3項) | ||
| (β3)破産手続開始後に保証人が全額弁済 | 主債権者の残存債権はない。保証人は、破産手続に参加して、求償権を行使することも、求償権の範囲内で原債権を行使することもできる (104条4項)。(*3) | ||||
| (γ)強制執行の配当財団(一般財産) |
(*4) |
(*5) |
|||
純然たる第三者が代位弁済をした場合
開始時現存額主義は、破産手続開始後に一部弁済をした共同債務者と債権者との利害の調整を図るための規定であるので、
共同債務(あるいは共同責任)を負わない第三者が破産手続開始後に一部弁済をした場合には適用されず、
原債権者の破産債権行使額は減少する。 その代位弁済により原債権の一部が代位される(移転する)場合には、弁済者がその原債権の一部を破産債権として行使する
(原債権が破産債権として届け出られている場合には、届出名義変更の届出(103条)で足りる)。
γ債権が生じない場合
破産手続開始決定を受けた共同債務者が他の共同債務者に対して償還義務を負わない場合の処理は、簡単になる。 例えば、債権者Xに対する主債務者Yの100万円の債務をZが保証している場合に、
破産手続開始決定を受けたのがYではなくZであり、Zの破産手続開始前にYがXに20万円を弁済していたとしよう。 Xは、Zの破産手続に開始時の債権額80万円で参加することができる。
主債務者Yは、連帯保証人Zに対して求償権を有するわけではないので、XがZの破産手続に参加しない場合でも、Zの破産手続に参加することはできない。
もっとも、主債務者と保証人との間に保証委託契約があり、保証人の破産がその契約の不履行と評価される場合は別である。
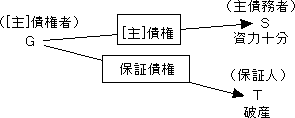 105条の規定の趣旨
105条の規定の趣旨
保証人は、主債務者とともに全部義務を負い、その点では連帯債務者などと異ならない。しかし、(α)単純保証人の催告の抗弁権・検索の抗弁権及び(β)保証債務の附従性
(民法448条)を考慮すると、「保証人について破産手続開始の決定があったときは、
債権者は、破産手続開始の時において有する債権の全額について破産手続に参加することができる」(105条)と規定する必要がある
(ただし、105条の規定の趣旨として、(α)の排除のみをあげ、したがって同条は単純保証人にのみ適用があると文献も多い[32])。
単純保証人の催告の抗弁権・検索の抗弁権の消滅 単純保証人は、破産手続外での債権者の取立てに対して、催告の抗弁権、検索の抗弁権を有する (民法452条・453条)。しかし、単純保証人が破産した場合に、これらの抗弁権の行使を認めると、 債権者の破産債権行使が遅滞し、不利益を受ける可能性がある。そして、単純保証人について破産手続が開始されたという異常事態を考慮すると、 主債務者が履行遅滞に陥っていない場合でも、債権者は、これらの抗弁権の対抗を受けないとすべきである。105条の第一の意義は、 このことを明確にする点にある。 換言すれば、同条にいう「破産手続に参加する」は、「破産債権を届け出る」の意味である。
なお、主債務者について破産手続が開始された場合には、単純保証人について破産手続が開始されていなくても、 単純保証人は、催告の抗弁権・検索の抗弁権を有しない(民法452条ただし書及び453条)。
保証債務の期限の到来 105条の規定の意義を次の場合について考えてみよう:主債務者(S)について資力の不安がなく、その債務の期限が未到来である状態で、 保証人(T)について破産手続が開始され、この手続に債権者(G)が参加した。債権者(G)は、Tが無資力に陥ったことを理由に、 Sに対して、資力を有する者を新たに保証人に立てることを要求することができる(民法450条2項)。 Sは、それに応じなければ、期限の利益を失う(民法137条3号)のが通常である。 しかし、常にそうなるとは限らない(民法450条3項参照。当事者は別段の合意をすることもできる)。また、代担保が提供されても保証人は免責されないままとなる場合もあり得る。 このように、保証人について破産手続が開始されても、主債務の期限が到来していない場合に、債権者は保証人の破産手続に参加できるのかが問題となる。 民法448条の附従性の原則に従えば、債権者は主債務の弁済期が到来するまで、保証人の破産手続に参加できないのが本来であるが、破産法は参加を認めた。 破産法150条により、履行期に関し民法448条の適用が排除されるのである ([注解*1985a]117頁(加藤哲夫)、[注解*1998a]153頁(加藤哲夫))[29]。 ただし、このことを103条3項により根拠付ける文献も有力である([伊藤*破産・民再v2]210頁)[40]。
主債権者が保証債権を届け出た場合の処理
債権者から債権届出があった場合には、保証人の破産管財人は、そのことを主債務者に通知し、主債務者から破産手続開始前に主債務の弁済をした等の通知を受けた場合には、
それを債権確定手続の中で主張しておくべきである(民法462条・463条参照)。
保証人の破産財団から主債権者に配当がなされると、主債務者に対する事後求償権が破産財団に属する。主債務の弁済期前に配当がなされた場合については、この求償権の内容が問題になるが、 受託保証人の求償権については平成29年改正民法459条の2が特則を設けて明確にした。
この規定は、(α)受託保証人について再生手続が開始され、民事再生法86条2項により準用される破産法105条により主債務の弁済期前に保証債務の履行がなされる場合には、 求償権の取立てを急ぐ必要はないので、素直に適用することができる。(β)破産手続が開始された場合にも、求償権の内容は、同条により規律されることになるが、 その金銭化については、難しい問題がある[34]; なぜなら、事後求償権は、保証人の破産手続において主債権者に配当がなされた時点で生ずるものであり、最後配当がなされるまでは求償権全体の金額は確定しないのに、 破産財団に属する財産として最後配当前に換価することが望ましい(最後配当をした後で求償権を行使して追加配当をする事態は、避けることが望ましい)からである。
新設された第3項は、 次のように規定している:「前2項の場合に債権者が行使する権利は、その債権の担保の目的となっている財産の売却代金その他の当該権利の行使によって得られる金銭について、 代位者が行使する権利に優先する。」。この規定の趣旨については、次の2つの理解が可能である。
ここでは上記の理解のいずれが正当であるかの問題には立ち入らずに、専ら代位弁済者が債権者に対して代位弁済義務を負う場合を想定して議論を進めることにしよう。
原債権の行使
規定の文言上、代位者が代位取得した権利に3項の適用があることは明らかである(そのことは、「その債権の担保の目的となっている財産の売却代金」によく現れている)。
代位者が代位取得した債権自体を行使して債務者の一般財産から満足を得る場合に、一部弁済前に存在していた一個の債権について代位者と債権者は、
502条1項・2項・3項により規律される特別の共同関係に立つ(連帯債権関係とは異なるが、これに比較的近い)。
2項の規定により、債権者は、一部弁済のあった部分を含めて破産債権者として債権全体を行使することができる(異論の余地はあろうが、以下ではこのことを前提にする)。
このことは、一部代位者が破産手続に参加しない場合に特に重要である。
(a)1項では、一部代位者が原債権自体を行使する場合にも、原債権者の同意が必要であるかのように規定されている。しかし、疑問である。 確かに、抵当権の実行については、原債権者の換価時期の選択権を尊重するために、原債権者の同意が必要であるが、原債権の行使については、 原債権者の利益は3項の優先権規定により十分に保護されるのであるから、これについてまで原債権者の同意が必要であるとするのは行き過ぎである。 1項の同意は、原債権者の利益が3項の規定のみでは十分に保護されない場合に必要になるものと解したい。
ともあれ、1項は、代位者の権利行使について「債権者とともにその権利を行使する」と定めているので、また、債権調査の手続と配当手続を簡明にするために、 原債権者と一部代位者は、破産手続開始時の原債権額並びに一部代位弁済があったこと及びその金額を明らかにして、共同して届け出ることことを原則とすべきである。 原債権者と一部代位者との間で一部代位の事実自体あるいはその金額について争いがあるため共同届出ができない場合には、 一部代位者は、一部代位の原因事実を及び共同届出をすることができなかった事情を明らかにして、 単独で届け出ることができると解すべきである。債権調査は、一部代位前の原債権自体について行うことになる。 原債権が一部代位者に分属する割合ないし金額については、 代位者と原債権者間で争えば足り、争いが配当時までに解決されないときには債権者を確知できないことを理由に供託をすれば足りよう。 もっとも、一部代位者の主張にしたがっても、3項の規定により原債権者が配当金を全て受領すべき場合には、供託することなく原債権者に配当金を交付すべきである。
(b)一部代位者が破産手続に参加しない場合には、原債権者は、原債権の一部について代位弁済を受けていることを明示して原債権全部の届出をすることができる(2項)。 原債権が優先的破産債権であるような場合には、原債権者が残債権全部の満足を得てなお余剰が生ずる場合もあろう。そのような場合には、一部代位者もできるだけ破産手続に参加しておく方がよいが、 参加していなかったときに余剰をどのように処理するかの問題が生ずる。予想される解決方法は、次の2つであろう:(α)連帯債権の場合と同様に、原債権者が原債権全体に対する配当金全額を受領して、 余剰金を一部代位者に交付する(余剰金の分配は、原債権者・一部代位者間で解決すべき問題とする);(β)破産管財人は、原債権者の取分のみを原債権者に交付して、残余を一部代位者のために供託する。 後者の選択肢を採るためには、一部代位の事実が破産管財人に知られていることが必要であるが、一部代位者からの届出がなければその事実が破産管財人に知られているとは限らないこと、 その事実が破産管財人に知られているとしても、原債権者の取り分が予め確定されているわけではないことを考慮すると、(α)の選択肢をとるべきであろう。
求償権の行使
代位者が債務者の破産手続開始前の一部弁済により債務者(破産者)に対して求償権を取得していて、これを破産債権として行使する場合(以下この項において「求償権行使の場合」という)はどうであろうか。
この場合も(a)の場合と同じ結果になるべきであるが、法律構成は、3項にいう「代位者が行使する権利」をどのようにとらえるかに依存しよう。
(A)民法502条3項にいう「代位者が行使する権利」は、1項にいう「その権利」を指し、したがって501条柱書にいう「債権(の効力)」すなわち「債権者が有していた債権」を指し、 他方、501条2項にいう「自己の権利」(代位者の求償権)を含まないとの構成(原債権限定説)。この構成をとると、502条3項は求償権行使の場合を直接の適用対象とするものではなく、 一部代位者は同条1項から3項にかかわらず、求償権に基づき原債権者と同順位で配当に与かることができるとの結論を得る余地が出てくる。
(B)しかし、それは今回の改正が予定する結論とは思われない。この構成をとっても、債権者は502条2項により一部代位弁済前の原債権を行使することができ、 一部代位者が求償権を行使すると二重の権利行使になるので、いずれかの権利行使のみを認める必要があるが、502条3項の規定の趣旨により、債権者の原債権行使が優先されるべきであるから、 債権者が原債権全体を行使する限りにおいて一部代位者は求償権を行使することはできないと解すべきであろう[82]。
改正過程においては、当初は、「保証人が取得する求償権は,債権者の有する原債権に劣後し,債権者が原債権の全額の弁済を受領するまで, 保証人は求償権等を行使することができないことを条文上明確にするかどうかについて, 更に検討してはどうか」との提案がなされていた(「民法(債権関係)部会資料 33−3」320頁)。この提案に対しては、意見照会の回答中で、 賛成意見もあったが、 「保証人が保証債務の一部を履行することにより,代位取得した担保権を単独で行使できないことについて異存はないが, 求償権等を行使すること自体についてまで制限しなければならない理由はないので,反対する。(大阪弁)」等の反対意見ないし慎重な検討を求める意見も出され(同前322頁)、 この提案は改正案に取り込まれなかった。そうした経緯からすれば、原債権限定説をとるべきであるが、 しかし、保証債務の履行を完了していない保証人よりも主債権者の利益を優先させるべきであるとの規定の趣旨は尊重されるべきであり、 求償権の行使を制約することが保証人に看過しがたいの不利益をもたらす場合は別として、そうでない限り、主債権者が原債権をもって破産手続に参加するときには、 一部弁済をしたに留まる保証人が求償権を破産債権として行使することは制約されると考えることは、解釈論として可能であろう(民法502条3項の類推適用。以下「原債権優先説」という)。 平成29年民法改正後は、上記の範囲では、破産法104条1項にいう「破産手続開始の時において有する債権」は、 ≪債権者と一部代位弁済者とに共同的に帰属する原債権全体≫(民法502条2項により債権者が単独で行使することができる「その債権」 又は同条1項により原債権者と代位者とが共同して行使する「その債権」)になるため、 破産法104条1項の改正なしに当初債権額主義が実現されることになると思われる。 もっとも、他の場合にも原債権優先説を貫徹することができるかは、問題であり、それとのバランスにおいて破産手続参加の局面でも原債権優先説を採ることはできないとの見解も可能であろう。 議論がいずれに収斂するかは予測しがたい。
他方、主債務者が一部弁済をした後で保証人について破産手続が開始された場合については、主債務者の一部弁済により保証債務は一部消滅し、 かつ、主債務者が保証人に対して原債権を代位取得したり、求償権を取得することはあり得ないから、民法502条3項の存在を前提にしても、 主債権者は保証人の破産手続へは開始時の現存額をもってのみ参加することができる。 当初債権額主義は、この場合でも主債権者は保証の破産手続に当初債権額で参加することができるとするものである。 この場合にも、主債権者が当初債権額でもって保証人の破産手続に参加することができるとするためには、破産法の改正が必要である。
したがって、民法502条3項により、当初債権額主義がある程度までは実現されることにはなるが、完全に実現されるわけではない。
破産者の共同債務者(保証人等)の求償権と 弁済者代位により彼が取得した債権(原債権、被代位債権)との関係についての議論は、錯雑としている。 破産手続との関連で、両者の関係を確認しておこう(主として、受託保証人を念頭において説明する)。
(1)消滅時効 求償権の根拠が破産手続開始前に生じた共同債務関係(保証委託関係、連帯債務関係など)にある場合には、 破産手続開始後の全額の弁済により破産者に対して求償権を取得した者は、求償権を破産債権として行使でき、さらに、原債権を行使することもできる。 代位弁済者に移転した原債権及びその担保権は、 求償権の従たる権利にすぎず、求償権が時効等により消滅すると、原債権も当然に消滅する(最判昭和61年2月20日・民集40巻1号43頁)。
時効の完成猶予・時効更新については、次のようになる:求償権者が裁判所になす原債権の届出名義の変更申出は、 「求償権について、時効完成猶予効の肯認の基礎とされる権利の行使」として、 その時から破産手続終了までの間、求償権の消滅時効完成を猶予する効力を有する; 求償権の消滅時効は、破産手続の終了の時から更新される(再進行する)が、その期間は従前のままである。 原債権者の届出債権が債権調査を経て確定し、民法169条により消滅時効期間が延長されても、 求償権の存在まで確定されたわけではないから、その時効期間まで10年に延長されるわけではない(平成29年民法改正前の先例であるが、 最判平成7.3.23民集49-3-984がこの趣旨を述べている)。 なお、ここにいう「時効期間」が166条1項に関して1号の期間を指すのか2号の期間を指すのかは明瞭ではないが、1号の期間を指すものと解すべきであろう; もし2号の期間を指すのであるとすれば、民法169条による時効期間の延長は多くの場合にあまり意味を有さないことになるからである[95]。
上記のことを考慮すると、債権者に弁済をした保証人は、原債権と求償債権の双方を破産債権として届け出て、双方について破産債権としての確定を得ることができるとすべきである (届出の際に双方の債権の関係を明示すべきであることは、いうまでもない)。
(2)原債権に認められた優先的権利[CL2] 原債権に優先権が認められている場合に、 破産者のために弁済をした者の求償権にもその優先権を認めることは、一つの合理的な規律であり、これを肯定する立法例もある([CL2]参照)。 その趣旨の明文の規定を有しない我が国において、原債権が租税債権である場合に、その趣旨の主張が代位弁済者からなされた公表裁判例は1件あるが、 裁判所は、求償権が優先権をもつことを否定した(神戸地判平成14年1月23日(平成13年(ワ)第62号))[63]。
我が国では、私債権を被担保債権とする抵当権について接木説(優先弁済効を享受する債権(被担保債権)が原債権から求償権に入れ替わるとする説)が否定されていることもあって、 議論はもっぱら「原債権について代位前に存在した優先権は、求償権者による代位取得後も維持されるか」という形でなされている。下級審判例及び学説は分かれていたが、 最高裁は、(a)雇用契約上の債権及び(b)注文者の請負人(倒産者)に対する前渡金返還請求権について、これを肯定した[104]:
その理由付けは、両判決ともほぼ同じである:(α)弁済による代位の制度は,代位弁済者が債務者に対して取得する求償権を確保するために, 法の規定により弁済によって消滅すべきはずの原債権及びその担保権を代位弁済者に移転させ,代位弁済者がその求償権の範囲内で原債権及びその担保権を行使することを認める制度であり, 原債権を求償権の確保のための一種の担保として機能させることをその趣旨とするものである;(β)したがって、弁済者代位により財団債権を取得した者は, 同人が破産者に対して取得した求償権が破産債権にすぎない場合であっても, 破産手続によらないで財団債権を行使することができる(再生手続との関係では、再生法177条2項の参照が指示される); (γ)このように解しても,他の破産債権者は,もともと原債権者による上記財団債権の行使を甘受せざるを得ない立場にあったのであるから, 不当に不利益を被るということはできない(24日判決の金築補足意見は、反対に解すれば、 他の債権者が「棚ぼた的に利益を得ることになる」と指摘する)。
(3)原債権の非免責性 253条1項ただし書各号の非免責債権について債権譲渡あるいは弁済者代位により債権が移転した場合については、 まだ判例はないようであるが、非免責債権の取得者も非免責性を主張できるとすべきである([杉本*2007a]228頁)。
β1
|
β2
|
|
代位弁済
|
||
消滅時効完成
|
||
求償権行使
|
代位弁済 求償権行使 |
|
時効の援用
|
債務者の委託に基づかない代位弁済の場合
無委託保証人が代位弁済する場合あるいは純然たる第三者が債務者の委託なしに代位弁済をする場合にも、上記のことが妥当するが、それに加えて、代
位弁済がなかった場合よりも債務者が不利になってはならないという配慮もなされるべきである。
この配慮により、(α)原債権が破産免責の効力を受ける場合には、代位弁済者の求償権にもその効力が及ぶとすべきである。
また、(β1)債務者の意思に反して保証あるいは代位弁済がなされた場合に、求償権発生後・その行使前に原債権が時効により消滅すべきであった場合には、求償権も消滅すると解すべきである
(無委託保証人の求償権について、462条2項参照)。(β2)その他の保証あるいは代位弁済については、原債権の消滅時効完成後・債務者による時効援用前に弁済がなされた場合も、同様とすべきである
(無委託保証人の求償権について、462条1項参照)。
租税債権は、公法上の債権であるので、特別の考慮が必要となる。まず、(α)租税債権を代位弁済した保証人が納税者から求償を得るために原債権たる租税債権を取得して行使することができるかが問題になり、 (β)できるとして、原債権の優先的特質が維持されるかが問題となる。いずれの問題についても、未だ最高裁判例はない。見解は分かれている([杉本*2007a]及び[長谷部*2011a]がアメリカ法の紹介も含めて詳しい)。
しかし、(α)(β)の双方とも肯定すべきである([上原*2006a])。なぜなら、代位弁済により租税徴収に大きく貢献しているのであるから、 その限度では租税債務の保証人には優先性(財団債権性と優先的破産債権性の双方)の保護を受けるだけの公共性があると言うべきだからである[35]。 また、前記最高裁判決の理由付けは、基本的にこの場合にも妥当する。特に(γ)の理由付け(「棚からぼた餅」論)を考慮すると、 租税債権を代位弁済した者が優先的に求償を得ることができないとすることは、政策論として妥当でない([栗田*2012b]170頁以下参照)。
現行法の下で優先権否定説を前提にした場合の現実的な解決は、次のようになろう: 保証人は、納税者から保証委託を受ける際に、自己の求償権又は弁済者代位により取得する租税債権について優先権を主張できないことを前提にして、 納税者から担保を徴収することができるのであれば担保を徴収し、それができなければ、保証料を高く設定する[33]。
議論の状況
104条3項の規定については、種々の問題がある。
受託保証人の事後求償権を例にとって、(1)同項本文の趣旨と(2)同項の求償権が停止条件付請求権等の配当に関する規律
(198条2項・214条1項4号。
以下単に「停止条件付債権の配当規律」という)に服するかに関する見解の状況を見てみよう。
(3)ただし書により破産手続参加が許されないことの意味については、次のような見解がある。
(4)破産手続において、受託保証人の事前求償権の行使が許されるかも問題になっている。 [杉本*2004a]119号116頁は、否定説をとる (破産法104条「3項本文によって弁済前の事後求償権を将来の請求権として権利行使する余地を認める以上、 事前求償権行使は破産手続において一切封じられていると解釈すべきである」と説く)。しかし、民法460条1号は、主債務者が破産手続開始決定を受けたことを事前求償権の発生原因としており、 その発生原因が存在する以上、その行使も許されると解すべきである。
(5)全部義務債権者が破産手続に参加した後で、破産者の共同義務者が全部の弁済をした場合に、彼は代位取得した原債権を行使できるが、その外に、事後求償権も行使できるかが問題となっている。 法文は、この求償権の行使を否定していないが、これを否定する見解もある(前述「6.1 全部義務を負う債務者の破産の場合」中の「104条4項により原債権を行使する場合の求償権の届出の許否と要否」参照)。
私 見
(a)議論の前提の確認――求償権額と代位債権額との関係 (α)1000万円の主債務を保証した受託保証人に対して主債権者が保証債務履行請求の訴えを提起した場合に、
主債務者はすでに300万円を弁済済みであったが、このことを保証人に通知していなかったために、また、保証人が主債務者に対して訴訟告知をしたにもかかわらず補助参加がなされなかったために、
保証人に対して1000万円の支払を命ずる判決が確定し、その後に主債務者に対して破産手続が開始されたとしよう。主債権者が主債務者の破産手続おいて行使できる債権額は、
保証人に対する判決にかかわらず700万円である(なお、保証人が判決に従い債権者に1000万円支払った場合の主債務者に対する求償権は、1000万円と解すべきである。
なぜなら、改正後の民法459条1項かっこ書は、463条2項の通知が怠られたために保証人が善意で超過支払をした場合や、超過支払を命ずる伴決を受けた場合には、適用がないと解すべきだからである。
その点は別としても、前記の例では、主債務者が「保証債務の履行を命ずる判決の既判力の標準時における主債務の額は700万円であった」と主張することは参加的効力により禁止される)。
破産手続開始の翌日に保証人が強制執行を回避するために主債権者に1000万円を支払ったものとしよう(その支払の際に、主債務者の破産管財人に事前の通知をしたものとする)。
この場合には、保証人の求償権は、1000万円である。このように、主債権者の破産債権(104条4項により保証人が行使する債権)の額よりも、
破産手続において行使できる求償権の額の方が大きい場合があることは、認められるべきである。 他方において、(β)連帯債務者の場合に典型的に見られるように、
代位弁済者が取得する原債権の額よりも求償権の額の方が小さい場合もある
(債権者Xが連帯債務者Y・Zに対して1000万円の債権を有していて、Yの破産手続の開始後にZがXに1000万円を支払った場合に、
前述(「2.2.4 破産手続開始前の弁済による求償権と原債権」)の受領金額制限説を前提にするとXが取得した原債権額は1000万円であり、求償権額は500万円である)。
(β')求償権は債務消滅のために支出した財産の額について認められる(債務消滅額の方が小さい場合には、消滅額。民法459条1項)。
例えば、保証人が代物弁済によりa円の債務をb円の財産の支出により消滅させた場合には、求償権額はaとbの小さい額である。今、a
> b であるとすると、求償権額はb円である。民法499条によれば、保証人はa円の債権について債権者に代位する。
ただし、代位債権の行使により受領することができる金額は「求償することができる範囲内に限られる」(501条2項)ので、(β)と同じような問題が生ずる。
そして、(γ)両者の額が基本的に同じである場合もある。
ともあれ、受託保証人が破産手続開始後に保証債務を履行した場合については、彼が取得する求償権の金額と代位取得する原債権の金額とは、基本的に同じである。 保証債務履行後の時期に係る求償権の利率と原債権の利率との差異は、通常は重要ではなかろう。この時期についての利息債権は、劣後的破産債権になるからである。 また、原債権について破産手続開始後に生ずる利息も保証人は弁済しなければならないが、この利息部分に係る求償権は、劣後的破産債権に含めるべきであろう。 そうしなければ、破産手続開始から後の時点で保証債務が履行されると、それだけ普通破産債権として扱われる求償権額が増加するという不都合が生ずるからである (この不都合だけで十分な法的説明になり得るかの点はさておき、結論はこれでよいはずである)。 したがって、104条3項本文にいう「将来の求償権」のうち普通破産債権になる金額は、 「破産手続開始の前日における原債権額」に等しい(ただし、受託保証人が開始の前日に代位弁済すると、彼は、弁済額とともにその日の利息及び不可避な費用も請求することができ(459条2項・442条2項)、 この一日分の利息及び費用も普通破産債権になるので、「破産手続開始の前日に保証債務を履行したと仮定した場合の求償権額」と同じであるとはいえない)。
(b)代位弁済者が行使する権利 破産者と負担割合が平等な共同債務者が破産手続開始後に債権者に弁済したような場合に、 受領金額制限説を前提にすると、通常、「求償権額 < 代位債権額」であり、代位弁済により取得した原債権を行使する方が有利である (なお、取得債権額制限説を前提にすると、この場合には「求償権額 = 代位債権額」となる)。
他方、「求償権額 > 代位債権額」の場合には、求償権者には、次のことが認められなければならない。 なお、aとbとが重なり合う部分について、二重に行使することは許されないことはいうまでもない。
aは、104条4項で認められている。bについてはどうか。破産法104条3項は、 将来の求償権について破産手続参加を認める規定であるが、破産手続中に弁済をした場合には、求償権全額を現在の債権として破産手続において行使することも、許容されるべきである。 3項は、その趣旨を含んでいると理解すべきであろう。これを前提にすると、前記の設例で原債権が普通破産債権である場合には、保証人が求償権のみを行使する方が、 手続が単純になってよいであろう。
(c)104条3項ただし書 主債権者が破産債権を届け出ている場合でも、その後に保証人が判決に従い保証債務を履行する可能性を考慮すると、 保証人は104条3項本文に従い将来の求償権を破産債権として届け出て、債権調査を受けることができるとしておくべきである。 そのためには、3項ただし書にいう「この限りでない」即ち「破産手続に参加することができない」は、「破産債権を届け出て債権調査を受けることはできるが、 議決権を行使すること及び配当を受けることができない」を意味すると解すべきである。
(d)104条3項の適用範囲 104条3項は、 一般に無委託保証人の求償権にも適用されると解されている (例えば、[加藤*破産v5]282頁)。しかし、104条3項は、 将来の求償権が破産債権であることを当然の前提とした規定と見るべきであろう。 そして、破産法104条3項は、将来の求償権をすべて破産債権とみなすという趣旨の規定と理解するのも適当とは思われない。 将来の求償権が破産債権に該当するか否かは破産債権の通常の要件を満たしているか否かに従って判断されるべきである。主債務者の破産手続開始前になさた無委託保証に基づき、破産手続開始後に保証人が弁済した場合に、 その求償権が破産債権になるか否かは、無委託保証契約が主債務者のための事務管理に該当するか否かに依存する。事務管理に該当する場合には、求償権の発生原因は無委託保証契約であり、求償権は破産債権になる。 そうでなければ求償権の発生原因は代位弁済であり、求償権は破産債権ではない。 しかし後者の場合でも、彼は破産手続開始後の弁済により主債権を代位取得し、求償権の範囲内で行使することができるのであるから(104条4項)、 将来取得することのある主債権の全額について破産手続に参加することができるとすべきである 。それは、「104条3項は、無委託保証人が将来取得することの主債権(被保証債権)にも類推適用される」と説明されるべきものである[21]。
(e)104条4項 「求償権額 ≦ 代位債権額」の場合には、求償権の範囲内で、代位債権を行使することができる。 「求償権の範囲内で行使する」の意味については、次の2つが考えられるが、受領金額制限説が妥当である(前述「2.2.4 破産手続開始前の弁済による求償権と原債権」参照)。
文 献
主債務者について破産手続が開始されると、受託保証人は、事前求償権を破産債権として行使することができる(民法460条1号)。 この事前求償権[30]は、法文上現在の求償権と構成されていて、またそのようなものと理解されている。 ただし、主債権者が破産手続に参加する場合には、主債務者の一つの給付義務について2人の者から二重の権利行使がなされることになるので、 主債権者の権利行使が優先され、 受託保証人は配当に与かることができない。この事前求償権の法的性質については争いがあるが、沿革的には、主債務者が主債務を履行しないことにより保証人が損害を受けるおそれがある場合に、 その損害を避けるために認められた権利(損害回避・免責請求権、解放請求権)であるとみるのが正当であろう([國井*1988a]、[西村*1993a])。 ただ、そのような目的のために認められた権利ではあるが、日本法は、求償金を保証人に支払うことを求める権利と構成した[36]。 その上で、事前求償金を得た保証人が代位弁済を行わない場合に主債務者が損害を受けることがないように、主債務者に多様の対抗手段を与えている(民法461条)。 保証人は、この求償権により無条件で即時に求償金を得ることができるわけではない。
問題は、主債務者の破産管財人は、その対抗手段をどのように行使すべきかである[31]。 重要なことは、保証人が受領した事前求償金を主債権者に支払わずに費消することを回避することであり、主債務者が二重払を強いられることを阻止することである。 破産管財人は、民法461条により与えられた対抗手段を任意に選択して行使できるのではなく、この目標の達成に最も適切な方法を選択しなければならない、と解すべきである。 それは、主債務者について破産手続が開始されている状況では、受託保証人の事前求償権への配当金を主債務の弁済に当てて、保証人を免責すること(民法461条2項)であろう。具体的には次のようになる: 今問題にしている場合にあっては、破産債権者は保証人であるが、前記抗弁権の行使により原債権者が配当金受領権者になると解すべきである (破産債権者と配当受領者とが異なり得ることについて、「4.6 破産債権者と破産債権行使者と配当受領者との分離」参照); 破産管財人は、主債権者を配当金受領資格者と見てこの者に配当の通知をすれば461条2項の免責行為をしたことになり、 主債権者が配当を受け取らない場合には破産法202条3号の供託をすれば足りるものと解すべきである(義務履行地は破産管財人の事務所であり、 その地を管轄する供託所に供託する)[43][45]。
主債務者の破産手続中に受託保証人が一部弁済をする場合
主債権者が主債務者の破産手続に参加している場合の取扱いは、104条で明示的に規定されている。では、主債権者が参加していない場合に、受託保証人が債権者に一部弁済をしたときはどうなるか。
債権者Gが有する破産債権を破産手続開始後にHが取得する予定である場合に、Hは、その破産債権を取得する前でも、自己を届出名義人にして、その破産債権を届出ることができるであろうか。 破産法はこれを認める規定をおいていない。そのような届出を広く認めると手続的負担(破産債権者表の作成及び債権調査の負担)が重くなり、 また、通常は、Hがその債権を取得した後で、その債権を自己の破産債権として届け出れば足りるからである。
債権取得後に届け出ることを本則とすべきことは明らかであるが、次の場合はどうであろうか。
この状況では、Hが将来取得する予定である優先的破産債権をHが届け出ることを認めるべきであろう。なぜなら、被保証債権が優先的破産債権である場合でも、そのこと自体は求償権を優先的破産債権に高める根拠とはならず、求償権は普通破産債権にとどまるのが通常である; そのような場合に、保証人が事前求償権をもって破産手続に参加しても、債権者自身が破産手続に参加したのと同等の結果を得ることはできないからである。同様に、次の場合にも、将来取得する予定の債権の届出を認めてよいと思われる。
これらの場合に、債権者は、保証人(あるいは債権買取義務者)Hとの関係で、破産債権届出義務を負うということはできるが、その義務の存在を理由に、 Hが将来取得する予定の破産債権を届け出ることを否定するのは妥当とは思われない。これらの場合に、破産債権者との法律関係に基づき将来取得する予定の破産債権の届出を認めるべきことを前提にして、 その要件を一般的な形で設定するならば、次のようになろう:(α)ある者が破産手続開始前の法律関係に基づき破産債権者に対してその破産債権の取得の原因となるべき給付義務を負っていて、 (β)破産債権を将来取得したときにその破産債権を行使する必要があること。
もちろん、保証人が保証債務を履行しない場合には、彼に原債権への配当金を与える必要はないので、原債権の取得について時期的制限を設ける必要があるが、 前述のように将来の請求権と同様に198条2項の制限に服させれば足りる。
問題は、このような規律を主解釈論として張することの可否である。次の理由により、可能と考えてよい: 破産法は、将来の請求権の届出を認めており、届出人が届出債権を現在有していることを要求していない; 保証人は保証債務を負っており、その履行により原債権を取得するのであるから、原債権取得の蓋然性は事後求償権の取得の蓋然性と同等である。
見解の対立状況
無委託保証人の求償権は事務管理者の費用償還請求権の性質を有するとの通説的見解を前提にすれば、何が主債務者のために行われた事務であるかが問題になる。この点について、次のような見解が考えられる。
私 見
後者の見解が正当である。(α)たしかに、主債権者と保証契約を締結すること自体が事務管理に該当すると見ることのできる場合もあるが、
しかし、それはそのように見るのが適当な場合に限られるべきである。例えば、主債務者が保証人を立てる義務を負っており、保証人を立てなければ期限の利益を喪失する場合に、
ある者が主債務者からの委託なしに主債権者と保証契約を締結し、その旨を主債務者に直ちに通知し(民法699条)、保証契約の締結の結果 主債務者が期限の利益の喪失を免れたときは、
保証契約の締結自体が主債務者のための事務管理になると評価してよい (なお、保証契約の内容(特に保証料の支払が合意されている場合にはその額ないし率)も主債務者への通知に含まれるべきである。
主債権者が支払う保証料は、 主債権者との主債務者との間の新たな取引において、主債務者に転化される可能性があるからである)。
しかし、(β)主債務者から委託を受けていない保証契約の締結は、しばしば主債権者から保証料を徴して、主債権者の営利活動としてなされるのであって、
そのような保証契約は主債務者のための事務管理には当たらないと評価すべきである([栗田*2010c]67頁以下参照)。
特に、保証人が主債務者に保証契約の締結を通知することを予定していないような無委託保証契約については、その保証契約自体を事務管理ということはできない(民法699条本文参照)。
無委託保証委託契約が主債務者のための事務管理に該当しない場合には、次のことが認められるべきである。
(a)この種の無委託保証契約であっても、その保証人が保証債務の履行として弁済をすれば、保証人は求償権を取得する
(保証契約の履行としての弁済であるので、弁済が債務者の意思に反する場合でも弁済をすることができる)。
求償権の内容(主債務者の償還義務の範囲)は、保証契約が主債務者の意思に反してなされたか否かによって区分され、意思に反してなされていた場合には、
求償請求の時点で主債務者が現に利益を受ける限度に制限され(民法462条2項)、その他の場合には、保証債務履行時の時点で主債務者が利益を受けた限度に制限される(民法702条1項及び改正前462条1項参照)。
(a')主債務者の意思に反するか否かは、原則として、保証人が無委託保証契約あるいは代位弁済の事実を主債務者に通知した時点で主債務者が無委託保証契約に関して表明する意思により判断すべきである。
主債務者に内密にすることを予定してなされた無委託保証契約は、主債務者が別段の意思表示をしなければ、主債務者の意思に反するものであったと扱ってよい(債務者の意思に反しないのであれば、内密にする必要はないはずである)。その求償については、民法462条2項が適用されるべきである。とりわけ、無委託保証契約が締結されたことが主債務者の破産手続開始後に通知された場合には、求償権者と他の破産債権者との間の公平が問題になり、主債務者が通知を受けて表明する意思に拘関わらず、求償請求時に主債務者(破産者)が現に受ける利益の範囲でのみ求償権を認めるべきである。
(b)主債務者の破産手続開始後に保証債務が履行されたことによる求償権が破産債権になるか否かは、破産法2条5項の解釈適用の問題である。
無委託保証契約が主債務者のための事務管理の性質を有しない場合には、求償権の原因となるのは、保証契約自体ではなく、
保証契約の履行としてなされた弁済自体である。したがって、その求償権は、発生原因が破産手続開始後にあり、破産債権にならない。
この場合に、彼は、弁済者代位により取得する原債権(民法499条・501条)を破産法104条4項により行使できる。104条4項は「求償権の範囲内において」と規定しているので、求償権が破産債権でない場合に、代位債権を破産債権として行使できるのかという疑問は生ずるが、
同項はそれを許容する趣旨を含んでいると理解してよい。
なぜなら、破産手続開始後でも破産債権の譲渡や第三者の弁済による代位は一般に許容されていることであり、無委託保証人をこれらの者よりも不利に扱う必要はないからである。
もちろん、無委託保証人も主債権者から見れば全部義務者の一人であるので、主債権者の受けた満足が一部の場合には、主債権者が破産手続に参加すれば、彼の残存債権行使が優先する(104条2項)。
(c)無委託保証人が破産者に対して債務を負っている場合に、破産手続開始後の保証債務の履行による求償権を自働債権として相殺することは許されない(67条1項の反面解釈。 弁済により代位した主債権を自働債権とする相殺も72条1項1号により許されない)。 なお、求償権の破産債権性を肯定する前掲・最判平成24年は、 この結論を72条1項1号の類推適用により根拠付けた[97]。
(d)無委託保証人は、保証債務を履行する前でも、主債権者が破産手続に参加していない場合には、破産法104条3項の拡張解釈により、 代位取得する予定の被保証債権を破産債権として届け出ることができると解すべきである(最後配当の除斥期間までに保証債務を履行して代位取得しなければならないことは、 104条3項の本来の適用対象である将来の求償権の場合と同じである)。
(e)代位により取得した原債権は、求償権を確保するための権利であるが、他方で、無委託保証人の求償権は、主債務者の関与なしに発生するのであるから、 主債務者の関与の下に発生する原債権を超えることは許されないと解すべきである。たとえば、(e1)主債務者の意思に反して保証した者は、 主債務者が現に(求償権行使の時点で)利益を受けている限度においてのみ求償権を有するのであるから(462条3項)、 求償権行使の時点では原債権の時効期間が満了していた場合には、保証人は求償請求できないと解すべきである。 (e1')他方、主債権の時効完成前に無委託保証人が代位取得債権を破産債権として届け出でた場合には、 その届出により主債権の時効の完成は猶予されるので(147条1項4号)、求償可能である。(e2)免責許可決定により主債務者が原債権の責任を免れる場合には、求償権の責任も免れると解すべきである。 破産手続開始後に第三者(債権者に対して全部義務を負わない者)が事務管理として債権者に弁済した場合に、これにより弁済者が取得する求償権と代位取得する原債権とについても同様である。
類似契約との比較及び類似契約への拡張
(a)債権買取予約 信用リスクの移転が≪債務者の破綻時に信用リスク引受者が債権者から請求があれば債権を買い取ることを予め合意する方式≫
(以下「債権買取予約方式」という)でなされた場合と比較してみよう。 債権買取予約は、債務者を関与させることなく、
債権者と信用リスク引受者(買取義務者)との間の合意ですることができ、また、それが通常であると思われる。
この信用リスク移転契約にあっては、信用リスク引受者の債務者に対する求償権は問題にならない。主債務者について破産手続が開始された場合に、破産債権となるのは、原債権のみである。
保証人が債権者から保証料を徴収して主債務者に内密にしてなされる無委託保証契約についての前述の規律(主債務者の破産手続開始後に保証債務が履行された場合に関する前述の規律)は、
債権買取予約方式による信用リスク移転とのバランスがよい。
(b)重畳的債務引受契約 保証契約に類似する契約として重畳的債務引受契約がある(この契約を以下では「債務引受契約」と略し、主債務者からの委託のないものを「無委託債務引受契約」という)。債権者と引受人との間でなされた債務引受契約(民法470条2項)は、 債務者の承諾がなくても効力を生ずる(同条3項と対比)。無委託債務引受契約は、法学的にも無委託保証契約に類似する。 すなわち、引受人が債務を履行した場合には、 引受人は求償権を取得する[96]。 引受人が原債権を代位取得するかは、499条・501条の解釈問題になるが、代位取得を肯定すべきである[102]。無委託債務引受契約が事務管理に該当するか否かの区分についても、無委託保証契約について述べたことが妥当する。 これを前提にして、無委託保証人が主債務者の破産手続開始後に保証債務を履行した場合について述べたことが、無委託債務引受契約の履行についても基本的に妥当する。
| A−−5億円の主債権−→Y(主債務者) ↑ ↑ ‖ | (2億円弁済) 2億円の求償権 ‖ | ‖========== Z(保証人) |
以下では、開始時現存額主義の意義を明瞭にするために、これと当初債権額主義とを比較するが、そのためには、平成29年民法改正前の民法の規定を前提にする方が都合が好い
(その方が、開始時現存額主義を古典的な姿で描くことができるからである)。 すなわち、破産手続開始前に共同義務者が一部弁済をしたことによる求償権は、破産配当において、
債権者の残債権と平等であるとする[108]。
開始時現存額主義の当否
日本では伝統的に開始時現存額主義が採用されている[66][67]。
例えば、Aが主債務者Yに対して5億円を貸し付けるに当たって、Zが連帯保証人になり、Yについて破産手続が開始される前に、ZがAに2億円を弁済したとしよう。
AはYの破産手続に債権額3億円でもって参加することができる。Zは、2億円の求償権をもって破産手続に参加することができる。 2割配当がなされる場合には、Aは6000万円、Zは4000万円の配当を受けることができる。
しかし、破産手続において、Aが、Yに対する債権の範囲において、Zに配当されるべき金額からも配当を受ける(6000万円+4000万円=1億円を受領する)ことができるというわけではない。
これが最善の処理かといえば、もちろん疑問である。なぜなら、
当初債権額主義(成立時債権額主義)
全部義務者の一人について破産手続が開始された場合に、破産手続開始前における破産者からの一部弁済等による債権額の減少は考慮するが、彼の共同義務者からの弁済や相殺は考慮せずに
、当初の債権額をもって破産債権額とする建前を当初債権額主義という。この立法主義を採用している国もあるが[CL6]、日本は採用していない。
当初債権額主義の下では、例えば共同義務者から4億円の弁済を受けていて、残債権額が1億円であったとしても、当初の債権額5億円でもって破産手続に参加することができる。もし2割配当であれば、
1億円の配当を受けることができる。3割配当であれば、配当金は1億5千万円となるが、債権者が受領することができるのは、残債権額に相当する1億円であり、残りは求償権者に交付される。
このように、当初債権額主義は、債権者優先原則の一つの実現方法である。
現存額主義よりも当初債権額主義の方が優れている、あるいは立法論として考慮の余地があると述べる見解は少なくない[41]。 さらに進んで、現行法の解釈論としても、当初債権額主義の趣旨を述べる見解もあるが[49]、日本の現行破産法がこの立法主義を採用していると解釈するのは難しい。 なぜなら、(α)現行破産法の前身である大正破産法が制定される当時(1922年)、スイス債務取立・破産法(1889年制定)が採用する当初債権額主義も既に知られており ([加藤*研究1]245頁以下(1908年初出)参照)、大正破産法は、それを採用することなく開始時現存額主義を採用し、それが現行法に引き継がれているからである。
開始時現存額主義の意義
成立時現存額主義との対比において、開始時現存額主義の意義はなんであろうか。次のことを挙げることができる:保証人が主債務者に代わって一部弁済をしたことにより発生する求償権は、
彼の一般財産に属するのであり、彼はそれを譲渡し、あるいは担保として利用することが認められるべきであり、彼は、これによる利益を享受し、
また、一般債権者が差し押えることができる責任財産の増加による信用力の向上の利益を享受することができるべきである;
ところが、当初債権額主義のもとでは、その後に主債務者について破産手続が開始されたときに、 求償権が主債権に劣後するため、主債務者の破産手続開始前においても求償権の取引価値は著しく低下する;
このため、保証人が受ける前記の利益は、開始時現存額主義の下で受ける利益と比較して、著しく小さくなる; 保証人が上記の利益を十分に得ることができるようにするためには、
主債務者の破産手続において求償権の順位を主債権のそれと同じにする必要があり、そのためには開始時債権額主義を採用せざるを得ない;
主債務者の破産手続開始前に保証人が一部弁済をしたことによる求償権を彼の責任財産として利用することを許すことと、開始時現存額主義とは、分離困難な関係に立つ。
したがって、開始時現存額主義の意義は、 当初債権額主義との対比では、償還義務者の破産手続開始前に発生した求償権の責任財産性(求償権者の責任財産の一部として利用し得ること)を確保することにあるということができる。 償還義務者が破産することなく弁済者に償還することもあり得ることを考慮すると、開始時現存額主義を採用することには、それなりの合理性がある。
開始時現存額主義の下では、主債権者に破産手続開始時における債権額と保証人の求償権額との合計額で破産手続に参加することができるとの地位を与えることは、 当事者間のその旨の特約に委ねざるを得ない(最も簡便な方法は、債権者の主債務者に対する債権を被担保債権にして、保証人が取得する将来の求償権上に質権の設定を受けることであり、 これも、保証人の責任財産に属することになる求償権の利用の一つの方法として許される[28])。 ただし、その特約は、保証人の一般債権者による求償権の差押え後になされた場合には差押債権者に対抗できないので、それ以前にしなければならない。
このように、当事者の合意により開始時現存額主義を当初債権額主義に近づけることができるが、それでも次の点で両者に差異が残ることに注意しておく必要がある。
AがYについて複数の債権(f1,f2)を有していて、Zがその全部について保証人になり、 Yについて破産手続が開始された後でZがその一部の債権(例えばf1)の全額について代位弁済をした場合はどうか (こうしたケースは、ZがA・Y間の一定の取引から生ずる債権について根保証人になっている場合のみならず、Zが根抵当権をもって物上保証人になっている場合にも生じやすい。 後者も前者と同じ処理に服する(104条5項参照))。この場合の取扱いについては、次のように見解が分かれている([杉本*2009a]参照)。
判例の立場 同一の保証人が同一の債権者に対して、別個の契約で複数口の債権を保証したのではなく、一つの保証契約により複数口債権を保証して、 主債務者の破産手続開始後にそのうちの一口の債権の全額について弁済がなされた場合は、一個の債権について一部弁済がなされた場合と利益状況が似ており、債権者の債権回収を優先させるために、 複数口の債権全体について開始時現存額主義(104条2項)を類推適用して、保証人の求償権は主債権者の主債権に後れるとすることにも一理あり、 この立場を採用した下級審判例もある(大阪高等裁判所平成20年4月17日判決(平成19(ネ)第2032号))。
しかし、その上告審である最高裁判所平成22年3月16日第3小法廷判決(平成20年(受)第1202号)は、 次のように説示して、これを否定した:「破産法104条1項及び2項にいう「その債権の全額」は, 特に「破産債権者の有する総債権」などと規定されていない以上, 弁済等に係る当該破産債権の全額を意味すると解するのが相当である」; 「債権者が複数の全部義務者に対して複数の債権を有し,全部義務者の破産手続開始の決定後に, 他の全部義務者が上記の複数債権のうちの一部の債権につきその全額を弁済等した場合には, 弁済等に係る当該破産債権についてはその全額が消滅しているのであるから,複数債権の全部が消滅していなくても, 同項にいう「その債権の全額が消滅した場合」に該当するものとして,債権者は,当該破産債権についてはその権利を行使することはできない」。 これに先行して、連帯保証人が破産し物上保証人が弁済した事例について、 大阪高等裁判所平成20年5月30日第14民事部判決(平成19年(ネ)第2033号)も同趣旨を説示している。
保証人について破産手続が開始された後で主債務者が一部弁済をした場合にも、開始時現存額主義の適用は肯定されるべきである。 しかし、最近は否定説も有力である。 否定説は、次のことを根拠とする([杉本*2009a]1274頁以下、[小原*2009a]430頁以下[26])。
しかし、この見解には賛成できない(詳しくは、[栗田*2010b]参照)。(α)債務保証制度の趣旨からすれば、主債務者が無資力の場合には、 保証人は、債権者に代位弁済をして主債務者に対する求償権を取得し、その求償権の行使により代位弁済金を回収するという形で、主債務者の無資力から生ずる損失の危険を負担すべきである。 (β)問題は、保証人が破産した場合に、その破産財団は、いつの時点の債権額について主債務者の無資力の危険を負担すると考えるべきかである。 破産法に別段の規定がない以上、この場合にも開始時現存額主義が適用され(104条1項・105条)、 保証人の破産財団は破産手続開始時における債権額について危険を負担する(この金額の保証債権が破産債権になる)と解すべきである。(γ)否定説は、保証人の破産財団が引き受ける危険を配当時における債権額に限定しようとするものであり、 立法論としてそれが可能であることは認めなければならないが、しかし、解釈論としては、その見解は特に105条の文言に反しよう。 (δ)否定説を徹底させると、 主債務者と保証人の双方について破産手続が開始されている場合には、債権者は、まず主債務者の破産手続において配当を受け、 不足額についてのみ保証人の破産手続において破産債権者として権利を行使すべきことになる。 さらに、債権者が主債務者の財産上に担保権を有している場合には、 その担保権を行使して、その不足額が保証人の破産手続において破産債権として行使されるべきことになる。 いわば、主債務者の財産に対する担保権及び破産債権が、 保証人の破産手続との関係で、不足額主義の適用を受ける準別除権とされるべきことになる。 しかし、11条3項・108条2項は、これらの権利を準別除権としていない。 もちろん、拡張解釈の余地はあり、また、そもそもそこまで徹底しないと否定説は意味がないというわけではないが、気になるところである。
(a)100万円の主債務について2人の連帯保証人AとBが存在し、そのうちの1人Bについて破産手続が開始され、さらに主債務者についても破産手続が開始されたとしよう。 その後に、他の連帯債務者Aが主債権者に100万円全額の弁済をすると、Aは、
保証人について破産手続が開始された場合には、手続開始時現存額説をとるか、配当時現存額説をとるかにかかわらず、次のような面倒な問題が生じ得る。 すなわち、保証人の破産手続において債権者に配当がなされると、保証人は配当額と同額の事後求償権を主債務者に対して取得し、これも破産財団に属するので、破産管財人はこれを取り立てて配当をしなければならず、 この配当により再び求償権が生じ、これも破産財団に属することになる。適当な時点で打ち切りを行わなければならないが、破産法はこの点について規定を設けていない[62]。
この問題は、(a)主債務者についても破産手続が開始されていて、債権者がその破産手続に参加している場合には、原則として生じない(104条3項ただし書により、保証人の破産管財人は求償権を行使できない。 ただし、主債権者が保証人及び主債権者の双方の破産手続において受領する配当額の合計額が債権額を超過する場合は別である)。 しかし、(b)主債務者についても破産手続は開始されているが、債権者がその破産手続に参加しない場合、及び(c)主債務者について破産手続が開始されていない場合には、この問題が生ずる。 もっとも、主債務全部について履行期が到来している場合には、主債務者は主債務全額を弁済すべきであり、それができないのであれば、彼についても破産手続が開始されてしかるべきであることを考慮すると、 (c)の場合として想定されるのは、(c1)主債務について長期の分割弁済の合意がなされていて、主債務者は遅滞なく債務を履行している場合、 あるいは(c2)主債務の分割弁済の約定はないが履行期未到来の場合に、 主債権者が105条の規定により保証人の破産手続において保証債権を破産債権として行使するときである。
前記(c)の場合に破産管財人がこの事後求償権を(配当金交付の時から)主債務者に対して即時に行使できる(取り立てることができる)とすることは、 主債務者の関知しない事由により彼の義務履行期を早める結果になるので、許されない(大判大正3年6月15日民録20輯476頁。 民法459条の2第3項)[25][44]。このことを前提にして、弁済者代位の規定により取得した原債権の履行期がかなり先である場合について、 事後求償権の処理方法を考えることにしよう。これについては、次の方法が考えられる。
[方法1] 主債務者が事後求償権を一定の掛け目で買い取る(正確には、履行期未到来の事後求償権について、求償権者の求めに応じて繰上弁済をする)ことを約束して、 保証人の破産管財人が主債務者から事後求償権見込額を上回る金額を預かって最後配当を行い、これにより事後求償権額を確定させ、預り金からこの金額を差し引いた余剰を返還するという方法である。 この場合の事後求償権額(p)は、次の方程式から算出される。
主債権者への配当額すなわち事後求償権額をp
求償権買取額をq
主債務者が求償権を買い取るときの掛け目をr(1≧r>0)(r=q/p)
保証債権の手続開始時の現存額をa
その他の破産債権額をb
求償権を含めない配当財団の額をc
とする。
[求償権額]=[配当額]=[保証債権額]×[配当率]
であり、
q=[求償権買取額]=r×[求償権額]=r×[保証債権額]×[配当率] ・・・(1)
[配当率]=(c+q)/(a+b)
である。これを(1)式に代入すると(以下では、乗算記号を省略する)、
q=ra(c+q)/(a+b)
さらに、q=rpであるので、
rp=ra(c+rp)/(a+b)
rp(a+b)=ra(c+rp)
p(a+b)=a(c+rp)
p(a+b−ar)=ac
p=ac/(a+b−ar)=a(c/(a−ar+b))
r=1のとき(掛け目なしで買い取るとき)は、p=a(c/b)
r=0のとき(買い取る者がいないとき)は、p=a(c/(a+b))
例えば、a=1000万円、b=9000万円、c=1000万円のとき、主債務者が求償権を掛け目なしに買い取るとすると(r=1)、
p=a(c/b)=111万1111円
r=1であるので、p=qであることに注意して配当率を確認すると、
配当率=(c+p)/(a+b)=(1000+111.1111)/(1000+9000)=0.11111111
他方、前記(b)の場合(主債務者についても破産手続が開始されているが、債権者がそれに参加しない場合)には、保証人の破産管財人が主債務者の破産手続において求償権を行使しても、 部分的な満足しか得られず、その割合も不確定であるので、上記の計算式は妥当しない。保証人の破産管財人としては、問題の簡明な処理のために、債権者に主債務者の破産手続にも参加することを要請するのが最善である。 しかし、債権者が主債務者の破産財団から多くの配当を得る結果、保証人の破産財団から手続開始時現存額を基準に配当を受けると過払になるような場合(実際上はあまりない場合)以外は、 保証人の破産財団の負担が軽くなるわけではないことにも注意すべきであろう[85]。
[方法2] 法律関係の決済の方法としては、上記のように債権者が保証人の破産手続に債権全額で参加し、 破産管財人が主債務者に対して取得する求償権を行使あるいは譲渡するという方法が本来的な決済方法であるが、 ただ、次のような簡便な決済方法も考えられる(主債務者が代保証人を立てる義務を負わないことを前提にする):
問題は、この解決方法が105条の下で可能か(正当化されるか)である。105条を適用した解決方法と等価であるならば、正当化されると考えてよいであろう。
(2)式と(3)式とが同じであるから、(2)式の前提になる解決方法は、破産法105条の下で可能な解決方法であるということができる。
ところで、[主債務者の不履行の確率]は、債権者が新たな保証人(保証を業務とする会社)を見いだして、その者に支払う保証料に反映されると考えられるから、
であると仮定しよう。
であるから、
これを(2)式に代入すると、
今、αが1であると仮定すれば、[債権者への配当額]=[新規保証料額]×[配当率]になる。それは、次のことを意味する。
上記の計算に際して設定した幾つかの仮定が成立する範囲では、これも、一つの簡便な解決方法になろう。
なお、法人保証において保証料が一定期間ごとに支払われる場合には、保証はその期間ごとになされたものと解してよく、そして、 (α)各保証期間の開始前にその期間に応じた保証料が支払われること及び(β)保証料率が当初の保証契約時と新規の保証契約時と変化がないことを前提にすると、 保証人の破産により債権者に生ずる損害は、破産手続開始時点において未経過期間に対応する保証料額と解してよい。
損害保険
例えば物の損害保険の目的物が第三者(加害者)の行為により滅失し、その後に加害者について破産手続が開始される場合を考えてみよう。保証との差異を明瞭にするために、
加害者の過失割合を8割とする。保険価額を1000万円とし、被保険者(物の所有者)は、加害者に対して800万円の損害賠償請求権を有するとともに、保険者に対して1000万円の保険金請求権を有するものとする。
保険者が被保険者に保険金を支払った場合に、保険者が加害者に対して求償権を取得すると観念するのがよいのかが問題になるが[109]、ここでは、保険者の加害者に対する求償権は観念しないものとし、
保険者の請求権代位(保険法25条)により問題が解決されるものとしよう。(α)もし保険者が1000万円の保険金全額を支払えば、
保険者は、被保険者債権(被保険者が加害者に対して有する800万円の債権)全部を代位取得する。 (β)保険者が400万円しか支払わない場合
(一部填補の場合)には、被保険者には未填補の損害600万円があり、被保険者はこれを加害者の財産から回収しなければならないので、
保険者が代位取得することができるのは、800万円から600万円を控除した200万円となる(保険法25条1項2号カッコ書)。保険者は、支払済み保険金額より多くの利益を代位により得るべきではないので、
代位することができる金額は支払済み保険給付額を限度とするとされているが(同条1項1号)、上記の設例ではこの要件は充足されている。一般的な形で述べると、(1)
代位は被保険者債権額から不足額(未填補の損害額)を控除した残額についてのみ認められ、かつ、(2)
保険給付額を超えて代位を認め必要はないので、保険者は両者のうちの少ない方の額で被保険者に代位する
(保険法25条1項。後者の要件は、 民法501条柱書の「自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内において」に相当するものである)。
また、損害賠償請求権(被保険者債権)は、彼と保険者との間で上記の金額で分有されることになるが、被保険者が確実に損害を回復することができるように、
被保険者の債権は保険者が代位取得した債権に優先するとされている(保険法25条2項)。
以上のことを前提にして、保険者が保険給付を行う前に加害者又は保険者が破産手続開始決定を受けた場合について、破産法104条の適用ないし類推適用を考えてみよう。
104条1項 この規定との関係では、加害者・保険者の双方について破産手続が開始されたことが前提になる。 被保険者の加害者に対する損害賠償請求権と保険者に対する保険金請求権は、保険事故により被保険者に生じた損害の回復という同一の目的に向けられており、 被保険者が加害者から賠償金の全額を得れば、その範囲で保険金請求権は消滅するのであるから、金額が共通する範囲では加害者と保険者とは全部義務者に相当すると言うことができる。 もし、その立場に立てば、104条1項の適用が肯定される。他方、保険者に対する保険給付請求権と加害者に対する損害賠償請求権との実体法上の性質の違いを重視して、 両者は金額が共通する範囲内でも全部義務者とは言えないとの立場に立てば、まさにその理由により、被保険者は、各破産手続開始時の債権額において各破産手続に参加することができる。
104条2項 この規定との関係では、加害者又は保険者のいずれか一方について破産手続が開始されたことが前提になる。
104条3項 この規定は、加害者のみについて破産手続が開始され、 その破産手続中に保険者が被保険者に保険価額の全額を支払う場合に問題となる。 この場合に、保険者が加害者に対して求償権を取得すると考えると、104条3項をストレートに適用してよいことになるが、前述のように彼は求償権は取得しない考えると、 同項中の「将来取得することのある求償権を有する者」を「破産債権者との法律関係に基づき破産債権を将来取得することのある者」と読み替え、 被保険者債権がそこにいう破産債権に該当するとして、同項を類推適用することになる。
104条4項 この規定についても、3項について述べたことが妥当する。 保険者は加害者に求償権を取得することはないとの立場に立てば、4項中の「破産者に対して将来取得することがある求償権を有する者」は「破産債権を将来代位取得することがある者」と読み替え、 「その求償権を有する者は、その求償権の範囲内において」は「破産債権を代位取得した者は、代位取得した破産債権の範囲内において」と読み替え、 被保険者債権がそこにいう破産債権に該当するとして、同項を類推適用することになる。
信用保険
貸付債権等の債務不履行により債権者に生ずる損害の填補を目的とする保険も、損害保険の一種であり、信用保険あるいは保証保険と呼ばれる。
保険法25条1項は、保険対象となる債権(前述の当該貸付債権等)も請求権代位の対象になることを明示している。信用保険については、債務者の委託を受けて保険契約が締結されることもあり得、
その場合には、信用保険委託契約の中で保険者の債務者に対する求償権が合意されることも考えられる。その点を除けば、損害保険について前述したことが基本的に妥当しよう。
別除権行使手続における処理
前記の例において、主債権者Aの主債務者Y(破産者)に対する債権についてAがYの不動産上に第一順位の抵当権を有していて、抵当権を破産手続外で実行した結果
1億円の配当原資が得られた場合に、この1億円は、3億円の残債権を有するAと破産手続開始前の代位弁済により原債権の一部2億円(及び抵当権の一部)を取得したZとの間でどのように配分されるのであろうか
(Zは求償権自体に基づいて抵当不動産の代金の分配を受けることができないことに注意)。
別除権の行使は破産手続外で行われるのであるから、この場合には、破産手続内での破産債権への平等配当の原則は妥当せず、債権者優先原則が妥当する。債権者Aの債権が保証人Zが代位取得した原債権に優先し、 Aが1億円全額を受領することになる(結果的に、原債権者は求償権者に優先すると表現することは可能である)。ここでは、他の債権者との関係では(つまり対外的には)、 主債権者と求償権者(保証人)とは一体となって一般債権者に優先し、配当時の被担保債権の現存額(3億円+2億円)の範囲内で優先配当(1億円)を受けるが、主債権者と保証人との間では(つまり内部的には)、 主債権者が優先し、残存債権額3億円の範囲内である1億円全額を受領するのである。
この場合には、保証人間に連帯関係があるか否かで、場合分けをする必要がある。
(a)保証人間に連帯関係がない場合(分別の利益がある場合) 主債務者Yの債務1000万円をAとBとが保証した場合には、 別段の合意がなければ、民法456条・427条により、A・B間では、AとBは別個の500万円をそれぞれ保証したことになり、AとBは、Gからの保証債務履行請求に対して、500万円を超える履行を拒むことができる (このように、共同保証人の各々の保証債務額が減少することを「分別の利益」という)。AとBとが共同して(同時に)債権者Gと保証契約を締結する場合が典型例であるが、 各別に保証契約を締結した場合にも、原則として民法427条の適用がある)。この局面に関しては、保証人が債権者に対して分別の利益を主張する限り、一部保証の場合と同じ結果になる。しかし、分別の利益が認められることと一部保証とは別個のことと理解されている。
では、次のような場合には、どのように処理すべきであろうか。なお、AとBは受託保証人であるとし、また、分別の利益を有する保証人が分別の利益を主張することを前提にする。
(b)保証人間に連帯関係がある場合(分別の利益がない場合) この場合には、保証人間でも104条が適用される。 これに該当するのは、次のような場合である。
(c)分別の利益を有する保証人と有しない保証人とが混在する場合 この場合には、分別の利益を有する保証人は、主債務額を保証人の総数で除した額を超える保証債務の履行を拒むことができ、分別の利益を有しない保証人は主債務の全額について保証債務をりこうしなければならない。例えば、主債務者Sが負っている1000万円の債務について、Aが連帯保証人になり、Bが単純保証人になった場合には、Bの500万円を超える保証債務の履行を拒むことができる([内田*民法3v4]446頁)。S・A間では破産法104条が全面的に適用される。S・B間及びA・B間については、前述(a)参照。
主債務者が債務不履行に陥った場合に、債権の全額が不履行になるとは限らず、多くの場合には、その一部についてのみ弁済が得られなくなるだけである。 さらに、保証の対象が、主債務者を異にする複数の債権をプールしたもの(債権群)である場合には、債務不履行が生ずる可能性がある部分は小さく、大数の法則により予見可能性が高まる。 そこで、保証の必要な債権あるいは債権群の一部についてのみ保証を付すことも考えられる。保証人からみれば、保証債務額を限定することにより、 自己に生ずるリスクを限定することができ、 債権者にとっては、これにより保証料を節減することが期待できるという利点がある。
この場合に、主債務者から一部弁済がなされたときに、保証人の義務は、(α)弁済額の範囲で消滅するのか、(β)未弁済額がある限り存続するのか、 (γ)一部弁済の割合に応じて消滅するのかは、リスク引受契約の解釈の問題である([内田*民法3v4]417頁)。別段の合意がなければ、 (β)と解釈される([内田*民法3v4]418頁)。 例えば、1000万円の債権について、300万円の一部保証がなされた場合に、主債務者が800万円の一部弁済をして破産したときは、 債権者は、保証人に対して未弁済額の200万円について保証債務の履行を請求することができる。 この場合に関して言えば、債権回収の確実性は、一部保証のあった部分よりは、なかった部分(主債務者から既に弁済がなされている部分)の方が高かったことになる。 もっとも、主債務者が保証のない部分について必ず弁済をするとは限らないので、その場合(上記の例で、主債務者の弁済額が500万円にとどまる場合)を想定して言えば、 安全性の順位は、 (1)主債務者が一部弁済した部分、(2)一部保証のあった部分、(3)いずれにも該当しない部分になる。
一部保証の契約において、保証人が主債務者の破産手続開始後に一部保証額の全部を主債権者に支払えば、保証人は、当該部分について原債権を取得するとともに支払額に応じた求償権も取得し、 主債務者の破産手続において保証人がこれらの権利を被保証債権者と同順位で行使することができると合意すること、あるいは、被保証債権者の権利行使が原債権者の権利行使に後れると合意することは、 契約自由の原則の範囲内である(直接の言及ではないが、[内田*民法3v4]417頁参照)。その合意の実質は、一定金額の破産債権に対する配当金を債権者と保証人との間でどのように分配するかを定めるにすぎず、 他の破産債権者の利益を害しないからである。しかし、その合意がない場合に、どのように規律すべきか。この問題についても、責任の集積による債権の強化の議論はおおむね妥当するが、 具体的規律については、見解が分かれよう[99]。
例えば、XのYに対する債権100万について、Zがその一部である60万円のみを保証し、Yの破産手続開始後にZがXに60万円を弁済したとする。Zは、Xが参加しているYの破産手続において、 60万円の求償権及び代位取得した原債権をXとの関係でXと同順位で行使することができるか。次の2つの見解が考えられる。
一部保証契約の中で、Aの結果がもたらされるような特約(例:「Zは、一部保証債務を全部履行した場合でも、Xが全額の満足を得るまで、求償権及び原債権の行使をXに委ねるものとし、 Xは、原債権全額の行使により得られる金銭からZに優先して満足を得ることができるものとする」)をすることは、契約自由の範囲内のこととして可能である。その点からすれば、 上記の問題は、一部保証契約の解釈の問題であるとも言うことができ、したがってまた、そのような特約のない場合にどのように処理するかは、多分に、当事者の通常の意思を基準として解決してよい問題であろう。
次の理由により、Bが支持されるべきものと考えたい[93]。(α)論理の問題として持ち出すことができるのは、 物上保証人に関する104条5項の規律とのバランスの問題にとどまろう(民法502条3項との整合性の問題もあるが、前述のように、ここでは立ち入らない)。 すなわち、物上保証人は、債権者に対して債務を負うわけではなく、物上保証に供された財産の範囲内でのみ責任を負い、その責任を全部果たした場合でも、 債権者が全部の満足を得るまでは、求償権を行使することができないとされている; そのこととのバランスからすれば、Aの選択肢が採られてもよいように思える。しかし、104条5項は債権全部について物上保証がなされているという通常の場合を前提にしている考えることができる; 彼が被保証債権全部の満足のために自己の財産を担保に供したことを重視するならば、債権全部の物上保証の場合と債権の一部保証とを区別することができ、後者についてBの選択肢をとることは可能である。 さらに言えば、債権の一部についての物上保証も可能であり、これと債権の人的一部保証とは同列においてよい。しかし、物上保証であるか人的保証であるを問わず、債権の一部の保証と全部の保証とは区別されるべきである。 (β)破産法の領域においては、開始時現存額主義の一つの構成要素として、原債権者優先原則が採用されている。その優先原則は責任の集積による債権回収の確実化を根拠とする。 債権回収の確実化は、保証された債権の範囲で行えば足りる。一部保証人が保証債務の全部を履行した場合に、保証対象外の残債権を彼の求償権よりも優先させる理由はなく、 責任財産の集積の法理(原債権者の権利は責任財産を提供した者の求償権に優先するとの法理)の適用の基礎を欠く。 (β')このことは、一部保証がなされた原債権は、 一部保証部分と無保証部分とに分裂するとみれば、説明が一層容易になる。 すなわち、一部保証に係る部分については、一部保証の全部の履行により「その債権の全額が消滅した」(104条4項)と評価することができ、 したがって、その部分について、一部保証人は、104条4項により、「求償権の範囲内において、債権者が有していた権利を破産債権者として行使することができる」。 (δ)上記のように解すると、破産手続中に原債権者が行使することができる債権額が変動することになり、手続上の負担が増すのは確かである。 しかし、破産債権の総額が変わるわけではなく、単に債権の一部について帰属の変動が生ずるだけであり、その負担が大きいとはいえないであろう。 同様な負担増加は、 例えば、破産債権の一部譲渡によっても生ずることであり、破産手続中に破産債権の一部を譲渡することが手続負担の増加を理由に禁じられているわけではない。 (ε)それほど決定的な理由があるわけではないが、債権の一部保証という契約類型を選択した当事者は、Bの解決を期待するのが通常であるように思われ、 また、当事者がAの解決を望むのであれば、その旨の特約をすれば足りることを考慮すると、そのような特約のない通常の場合については、Bの解決が採用されるべきであると思われる。
前述のことは、一部信用保険についても理論上は妥当する。ただ、保険法25条2項が、保険者の代位取得債権よりも被保険者の未補填債権を優先させることを規定し、 同法26条が25条を片面的強行規定としているので、保険者の代位取得債権の順位をこれよりも高める合意をすることができない([萩本*2010a]141頁)。
もっとも、同法36条4号が「法人その他の団体又は事業を行う個人の事業活動に伴って生ずることのある損害をてん補する損害保険契約」を26条の適用対象外としているので、 これに該当するものについては、保険者の代位取得債権の順位をこれよりも高める合意をすることができる。 どのような信用保険契約が36条4号所定の損害保険契約に該当するかは明瞭ではなく([萩本*2010a]145頁参照)、判例を待つ必要がある。
債権全体について保証を受ける場合でも、(α)主債務者の財産自体から回収が可能な部分と(β)そうでない部分とをある程度予想することができるときに、 前者については保証料の低い無担保保証ですませ、後者については保証料は高いが確実に補填を受けることができる保証にする(例えば、保証債権を被担保債権にして保証人がその財産上に担保権を設定する)ことが考えられる。
こうしたことは、通常の保証契約実務の中で行われることは少ないと思われるが、後述のその他の信用リスク移転契約の世界ではすでに行われていることである。 標語的に言えば、「予想されるリスクの度合いに応じて債権を細分し、リスクの度合いに応じてリスク移転方法を選択する」ということになる(リスク細分型リスク移転)。
貸倒れリスクの移転の最たるものは債権を売り切ることであるが、ここでは、債権を債権者に帰属させつつそのリスクを他に移転させる契約を中心に取り上げることにしよう。 保証契約は、主債務者の信用を補完する契約であるが、債権者から見ると、債権の貸倒れリスクを保証人に移転させ、自己に生ずる損失を軽減する結果をもたらす契約である。 特に、債権者が、主債務者への融資実行後に、主債務者からの委託を受けない保証人と保証契約を締結し、保証料を受取利息の中から支払う場合がそうである。 リスク移転のための契約類型は、これ以外にもある。
また、一人の債務者に対する多額の信用リスクを債権者が一人で背負うことは、危険である。信用リスクは、多数の債務者に分散させ、多数の者により分担するのが賢明である。 リスクを分担する者を不特定多数の投資家にまで拡大することができれば、さらによい。こうした目的を達成するために、新種の証券化商品(デリバティブ商品(派生型商品))も開発されてきている。
債務者の債務不履行によって生じた損害を第三者が補填することを内容とする契約を損害担保契約と呼ぶことにしよう。 第三者は、貸倒れの発生の確率を考慮して決定される担保料を受け取ることになるが、 それを支払うのが債権者であるか債務者であるかは、ここでは重要でない。
上記のように定義された損害担保契約は、破産手続との関係で、次のような特色をもつ:この契約の純粋な形態にあっては、
損害担保契約と保証契約との差違は、債務者と担保義務者が同じ時期に破産手続開始決定を受けた場合に現れる。 保証契約にあっては、開始時現存額主義が適用され、 債権者は、主債務者の破産手続で得た配当額に影響されることなく保証人の破産手続の開始時における保証債権額を基準にして配当を受けることができる (ただし、少数ではあるが異論のある点である)。他方、損害担保契約の場合には、その契約の趣旨に従い、 債務者の破産財団からの配当額を控除した残額を基準にして配当を受けることになる。 この点を厳格に貫けば、 債務者の破産手続における配当額が確定するまで、担保義務者の破産財団から配当を受けることができないことになる。 しかし、それは現実的ではないので、担保義務者の破産手続開始時の債権額で破産手続に参加することを認めた上で、 債務者の破産財団からの配当額分だけ破産債権額が減少する解除条件付債権として扱うのがよく (債権者は、債務者の破産財団からの配当額a円を受領した結果、これに担保義務者の破産手続における配当率rを乗じた金額a×r円をその破産財団に返還する義務が負うことになる)、損害担保契約においてそのような取扱いを可能にする合意をなすべきである。
6.5.2 債権買取予約・停止条件付債権買取契約
債務者の財産状況の悪化を示す事由(破産申立て等)が生じた場合には、買取義務者に債権買取りを請求できる契約(債権者が予約完結権をもつ予約)あるいは当然に買い取る契約も、信用リスク移転の機能をもつ。 どの金額で買い取るかは、契約自由の原則の範囲内のことである。典型的には、額面額で買い取るとの合意がなされよう。
債権買取予約等と保証契約との差違は、債務者と買取義務者の双方について破産手続が開始された場合に顕著に現れる。 保証の場合には、主債権者は、主債務者及び保証人の双方の破産手続に参加することができるのに対し、 債権買取予約等にあっては、一方の破産手続にしか参加できない(責任財産の集積なし)。 両破産手続における配当率が同じである場合には、保証契約によりリスクを移転させた債権者が回収できる債権額は、 債権買取契約によりリスク移転を図った債権者の回収額の2倍になる[51]。
これは、米国の金融取引や国際的な金融取引の中で発達してきた新種の信用リスク移転取引であり、いわゆるデリバティブ取引の一種である (基本的な仕組みについて、[大久保=井伊*1996a]15頁以下、 [寺山*2001a]、[田中*2002b]、[杉原=細谷=馬場=中田*2003a]2頁、[中山=河合*2005a]2頁、[ピムコ*2007b]、[栗田*2017a]などを参照)。 こうした取引も、日本の民法や倒産法の中で、適当な居場所を与えることが必要である。本来ならば、取引社会において用いられている標準的な契約書から基本的特質を抽出して、 その法的性質を議論すべきであるが、今はその余裕もないので、いくつかの文献から知り得る範囲で、その破産法における位置付けを考えてみることにしよう。
最高裁判所 平成28年3月15日 第3小法廷 判決(平成26年(受)第2454号)は、次のように説明(定義)している:「CDSとは,参照対象となる企業その他の組織(以下「参照組織」という。)につき, その倒産,不払等のリスクを回避したい者(保証の買手)がそのリスクを引き受ける者(保証の売手)に対し保証料を支払い, その参照組織につき倒産,不払等の事由が発生した場合に保証の売手が保証の買手に対し上記事由に応じた所定の金額を支払うことなどを内容とする金融商品のことである。 そして,複数のCDSの市場価格を平均値により指数化したものを用いたものがインデックスCDSである。」。この説明における「保証」は、「プロテクション」ともよばれる。 民法446条以下が規定する「保証」と機能的に近く、同一と言い得る場合もあるが、常に同一であるとまではいえないので、以下では、「プロテクション」の語を主として用いることにする。
CDS取引の最も基本的な形態は、保証契約ないし損害担保契約に類似する([大久保=井伊*1996a]参照)。それは、債権者が債務者に対して債権を有していて、 債務者が債務を弁済できなくなることにより債権者に生ずる損失を保護(補填)することを他の者が約束する取引である。債権者はプロテクションの買手(あるいはリスクの売手)と呼ばれ、 保護を約束する者はプロテクションの売手(あるいはリスクの買手)と呼ばれ、プロテクションの買手が売手に支払う対価は、プレミアムと呼ばれる。リスクの要因となっている債務者は、 通常は法人であり、参照法人と呼ばれる。プロテクションの売手が買手に保護を与えるべき事由をクレジット イベント(信用事故)といい、参照法人の倒産や支払不履行が代表例である。クレジット イベントが参照法人についてではなく、特定の債務について定められる場合もあり (ノンリコース特約がある場合には、そうする必要がある)、その場合には、その債務を参照債務と言う(債権債務関係は証券に化体されていることが多く、 上記の説明における「債権」は「債券(に表章された債権)」に置き換えていくことができる)。
CDS取引を抽象化ないし一般化していけば、プロテクションの買手が参照法人に対して債権を有することは必要ない。抽象化を推し進めれば、参照法人にクレジット イベントが生ずることによりプロテクションの買手に損失が生ずるという関係も必要なくなる。クレジット イベントも、倒産に限られず、参照法人の信用低下を示す事由であれば何でもよいことになる (例えば、債務減免交渉の開始でも、株価が一定の水準を下回ることでもよい。ただ、その発生を明確に判定できることが必要である)。 CDS取引は、きわめて一般的な形でいえば、参照法人の信用に関わる事由の発生を停止条件とする参照法人以外の者の間の給付契約と言うことができる(給付は、金銭給付でも債権買取りでも、その他の給付でもよい)。
法的性質と有効性 CDS取引はその基本的形態において有効であることに問題はなかろう。その法的性質は、リスク保護の買手が参照法人に対する債権(被保護債権)を有するか否か、及びクレジット イベントが生じた場合の決済方法に依存しよう。
(a)決済方法 リスク保護の買手が参照法人に対する債権を有している場合の基本的な決済方法として、次の2つがある。
現金決済の場合には、プロテクションの買手に生ずる実損害は、参照法人の倒産処理手続を経て確定することが最も正統的である。 しかし、それ以前に売手が買手に金銭を支払うことが約定される場合があり、その場合には、クレジット イベントの生じた債権(多くは債券)の評価額(時価)でもって買手に生ずる損害が算定される。 評価を公正に行うために、対象債権を競売(競争売却)にかけることもある (多数の買受希望者を集めるために、売却対象となる債権を集合させておくことが望ましい)。プロテクションの売手も買手もこの競売に参加できるようにしておけば、評価の公正性を期待できよう。 また、この競売において購入された債権の使い道も様々であり、単純に債務者に対して弁済請求することもあるし、 債権を有していない者が現物決済の合意のあるプロテクションを購入していた場合に競売で購入した債権を決済に用いることもあろう。
参照法人に対して債権を有しない者が現金決済型のプロテクションを購入する場合に、仮想的に元本額を定めておき(この元本額は「想定元本額」と呼ばれる)、クレジット イベント発生後に行われる債権の競売等により確定した回収不能率を約定された想定元本額に乗じて算出される金額をプロテクションの売手が買手に支払うことを合意することも可能である。
(b)法的性質 (α)プロテクションの買手が参照法人に対する債権を有している場合に、現金決済が約定されているときは、その法的性質は、損害担保契約の一種である。 現物決済が約定されているときは、停止条件付債権買取契約の一種である。 これらの場合に、プロテクションの買手が参照法人に対して有する債権がプロテクションの売手に移転することは、 保証債務の履行による被保証債権の代位取得と類似する。 代位取得と同性質のものと観念されれば、 日本民法の下では、代位取得された原債権の行使については「求償をすることができる範囲内において」という制約が付く(501条2項)。 他方、代位取得ではなく債権の買取りと同性質のものと観念されれば、原債権の行使についてはそのような制約がないことになる。 CDSは、プロテクションの売手による原債権の取得が代位弁済による取得と同性質のものと観念される場合に限り、保証契約に類似する (プロテクションの売手が銀行でその倒産が予想し得ない状況にある場合には、その類似性が高まる)。 しかし、決済方法が現金決済であっても現物決済であっても、参照法人とプロテクションの売手の双方が共同債務者の関係に立つわけではなく、 双方について破産手続が開始された場合に破産法104条1項・105条が適用されることはないから、保証契約ではない。CDSがこのような内容のものである場合( 真性の保証契約ではない場合)には、CDSの経済的機能は保証契約に近いが、それは、損害担保契約や停止条件付債権買取契約の経済的機能が保証契約に近いという以上の意味を有しない。
(β)プロテクションの買手が参照法人に対する債権を有しない場合には、CDS契約は保証契約ではあり得ない。 しかしこの場合でも、参照法人の倒産等によりプロテクションの買手に損害が生ずるという関係がある場合には、 そのCDS契約の射倖性は低く、その有効性を肯定してよい。 例えば、前述の損害担保契約の例において、債務者に対して債権を有せず将来も求償権等を取得することのない損害担保義務者が、 債務者の倒産リスクを他に移転するためにCDSを利用する場合がそうである[16]。
(γ)上記の(α)にも(β)にも該当しない場合には、CDSは、おおむね、射倖契約の中に分類することができる停止条件付金銭給付契約や停止条件付債権売買契約である。
(c)有効性 (α)クレジット イベントが参照法人の倒産で、プロテクションの買手が参照法人に対して債権を有する場合を典型例として、クレジット イベントの発生によりプロテクションの買手に損害が生ずる関係がある場合には、CDS契約は有効としてよい。 ただ、こうしたCDS契約が有効となることを前提にして、多額の信用リスクが引き受けられ、 信用リスクの移転が幾重にも積み重なていくと、リスクの所在がつかみにくくなる。 例えば、銀行が債務者Aに対する多額の債権のリスクをBに移転させたが、 Bがさらにそれを他に移転させ、最終的な移転先がZであり、銀行がそれを知らずにZに多額の融資をしていると、 Aの倒産がZの倒産となって現れ、Zに多額の融資をしている銀行が結局リスクの最終的な引受手となる。この場合には、リスク移転の事務作業は、浪費である。 そして、リスク移転手段があることをよいことに最初の債務者に多額の融資を続けると、その債務者が倒産したときに社会に生ずる損害も大きくなる(一人の債務者の倒産により社会に生ずる損失は、 その債務者の負債額に比例するのであり、債権者が倒産リスクを他に移転したところで、このことは基本的に変わらない)。
(β)参照法人についてクレジット イベントが生じてもプロテクションの買手(リスクの売手)に損害の生ずることがない場合 (プロテクションによって保護されるべき利益(被保全利益)がない場合)には、 そのCDS取引は投機性・賭博性を帯びる。 株式市場においては、投機行為も株式の流動性を高める効果があり、その有効性に疑問がもたれることはない。CDS取引も同様に考えるべきかは、迷うところである。 こうしたデリバティブ取引は、現在は、契約自由の原則の下に取引当事者の創意工夫により様々な商品ないし取引が開発されている段階である。 その取引が定型化される過程で、 あるいは定形化が完了した段階で法的規制が加えられることになると思われるが、現在のところは、当事者の創意工夫による自由な発展に委ねておく方がよいと思われる。 したがって、CDS契約は、それが他者の倒産を材料とする賭博性の高い行為であり公序良俗(民法90条)に反すると評価されたり、 あるいはCDS取引において高いプレミアムが支払われている参照債権であるから不履行のリスクが高いと投資家に思わせることにより債券の価格を意図的に引き下げる手段として悪用されるのでないかぎり、 有効としてよいであろう[CL9]。
プレミアムの算定にあたっては、参照法人あるいは参照債務の評価が重要となる。その評価がプロテクションの買手に不当に不利あるいは有利になるように不公平な手続でもってなされると、 モラルハザードの問題が生ずる。ただ、その評価は、参照債務となっている証券の格付けあるいは証券の発行体の格付けを基に行われるようであり、格付機関が客観的な資料に基づいて公正に格付けをする限り 、モラルハザードの問題はこれを通じて抑制されることが期待できる。何をクレジット イベントとするかの問題についても、同様なことが妥当する(特に、倒産や支払不履行以外の事由をクレジット イベントにする場合が問題となる)。以上につき、[ムーディーズ*2003a]15頁−17頁参照。 もっとも、金融危機のたびに、 証券の発行体の依頼を受けて発行体から手数料を徴収してなされる格付けの信頼性が疑問視されことにも注意しなければならず、 それ故に、その民事責任も議論されるようになった[83]。そして、プロテクションの買手が参照債務の不履行の確率が高いことを知りながら、 それに関する資料を格付会社及びプロテクションの売手の双方に開示せずあるいは必要な指摘をせずに、格付会社が高い格付けを行なうことを放置して、低いプレミアムでプロテクションを購入した場合には、 その非開示が取引上の誠実義務に反すると評価されるときには、暴利行為として民法90条により無効になり得ると解すべきである。
参照法人 最も基本的なCDSにおいては、参照法人は一人であるが、複数の参照法人を一つのグループにして取引の対象とすることもある(バスケット型CDS)。
参照法人とプロテクションの売手との関係 CDS取引は、プロテクションの売手と買手の間の取引であり、参照法人(債務者)が売手にプロテクションの売り(リスクの引受け)を委託することはないようである。 これを前提にすると、CDSが保証契約類似の契約と把握される場合でも、事前求償権は問題にならない(真性の保証契約がCDS契約と呼ばれている場合は、もちろん別である)。
プロテクションの買手の権利の保全 クレジット イベントが発生したときに、プロテクションの売手が所定の義務を履行するか否かは、彼の財産状況に依存する。 売手自体が破産した場合には、個々のCDS取引の内容に応じて、保証契約、債権買取予約あるいは損害担保契約の場合と同様に(前述参照)、 プロテクションの買手が破産債権者として破産手続に参加することを認めてよいが、 ともあれプロテクションの価値は著しく失われる。この点の危険を回避するために、(α)プロテクションの売手を参照債務者とする別のプロテクションを他の者から購入すること、 あるいは、(β)プロテクションの売手(例えばAIGのような保険会社)の株価が一定の水準を下回れば、参照債務に相当する額の担保を提供させることがある。 また、(γ)次に述べるファンド付のCDSにより担保を予め提供させておくこともある。
ファンド付CDSないし合成CDO (Synthetic Collateralised Debt Obligation)
プロテクションの売手自体が破産することによりプロテクションの価値が失われる危険を回避するための方法として、プロテクションの売手に予め資金を提供させ、
その資金をプロテクションの売手とは別個の者に管理させる方法がとられる(ファンド付きのCDS)。具体的な方法は、例えば次のようになる。
例1
この場合には、リスク資産を原債権者(G)に帰属させたまま、そのリスクを他に移転させる形で二次的な債券が組成される点に特徴がある。 また、この債券の元利金の支払原資は、(α)証券の代金で購入された資産(国債)と(β)CDSのプレミアムの複合である。 このような特徴をもつ債券は、Synthetic CDOと呼ばれる(「合成債務担保証券」と訳されることがある。[杉原=細谷=馬場=中田*2003a]1頁)。 このタイプの債券は、代金で購入される資産の運用益(利息)にCDSのプレミアムが加わるため、利回りが比較的高くなる。 この債券の販売にあたって好利回りの点が強調され、CDSによるリスク引受が強調されないままとなると、買手は、好利回りの金融商品という外装につられて、 実のところ、担保まで提供して保証人の責任を引き受けているのである。その債権のクレジット イベントが発生したときに、投資家は損失を被る。 その意味で危険な商品である。この場合には、投資家は、国債に投資しているのではなく、 原債権者の保有するリスク資産に投資したのであり、その点が強調されるべきである。
例2
| 誤解のあることを恐れつつも、CDOの語義について説明しておこう。
CDO (Collateralised Debt Obligation) のObilgationは、権利義務関係を意味する。債権者から見れば権利(債権)である。 CDOにあっては、通常は、証券化された債権である。Collateralisedの語の基礎となるcollateralの意味は、「派生的な」あるいは「二次的な」であるが、 そのほかに「追加的な担保によって保証された」あるいは「見返りの」の意味もあり、 名詞形では単に「担保」の意味で使われる場合もある。 Collateralisedがこれらの内のいずれの意味を直接の基礎としているのか判然としないが、いずれにせよObligationの裏付資産がDebtであること、 ないしはDebtを基礎にしてObligationが作られているという関係にあることを意味している。Debtは、Obligationの裏付けとなる資産が債権債務であることを意味する。 全体では、「債権を裏付けにして作られた二次的な権利(債権)(を化体する証券)」を意味する。 資産担保証券(Asset Backed Security)の一種でもある。 裏付けとなる債権が貸付債権(Loan)である場合には、CLOと呼ばれるように、CとOとの間の文字はいろいろ変わる。 Synthetic CDOには様々な類型のものがあり、本質的要素(必要最小限度の要素)が何であるのか判然としないが、ここで問題にしているのは、 プロテクションの最終的な売手と買手との間に媒介法人(SPV)が介在し、 SPVがプロテクションの売手から拠出された資金でもって買手に生ずることのある損失を補填するためのファンドを保有している形態のものである。 |
リスクの一部移転
債務者が債務不履行に陥った場合に、債権の全額が不履行になるとは限らず、多くの場合には、その一部についてのみ弁済が得られなくなるだけである。
さらに、リスク移転の対象が、債務者を異にする複数の債権をプールしたもの(債権群)である場合には、債務不履行が生ずる可能性がある部分は小さく、大数の法則により予見可能となる。
そこで、リスク保護の必要な債権あるいは債権群の一部についてのみリスク引受が行われることがある(例えば、20%であるとしよう)。
この場合に、債務者から一部弁済がなされたときに、リスク引受人の義務は、保証の場合と同様に、未弁済額がある限り存続すると解釈するのが当事者の意思に合致しよう (ただし、この点は、リスク引受人の義務内容に関わる重要な点であるので、契約で明確にしておくべきである)。 これを前提にすると、保証やCDSによってリスク引受のなされていない部分は、 債務者の財産からの回収が確実な限り、リスク引受のなされている部分よりも優先順位が高いことになる。 そのためであろうか、この部分はスーパー シニアと呼ばれる。それが債権全体の70%から80%に及ぶ場合もあるようである。 その場合に、債務者の弁済率が70%を下回ると、スーパー シニア部分にも回収不能リスクの高い部分が生ずる (例えば、スーパー シニア部分が債権全体の80%で、債務者からの弁済率が50%であるとすると、 スーバーシニア部分のうち債務者から弁済されない部分(債権全体の30%)のうち、 リスク移転契約よってカバーされない部分(30%−20%=10%)が回収不能になる)。 スーパー シニアの語に惑わされないようにしなければならない。
リスク移転の階層化(序列化)
一つの債権ないし債権群全体についてリスク移転を行う場合でも、債務不履行が生ずる確率を考慮して、回収不能になる見込みが高い部分と低い部分とに切り分けて、
回収不能となる確率の高い部分については、高いプレミアムを支払って、補填が確実に行われることを期待できるリスク移転(例えば、ファンド付のCDS、つまりシンセティックCDOによるリスク移転)を行い、
その余の部分については補填の確実性がやや劣るリスク移転(例えば、ファンドなしのCDSによるリスク移転)ですませることもある。
リスク引受人が破産した場合の破産法上の取扱い
債権の帰属を変更することなく債務不履行のリスクを他に移転させる方法としては、前述のように、保証、保険及びCDSがある。CDSの内でここで取り上げる必要のあるのは、
保証や保険とは異なる法的性質のものであるので、ここでは、次の2つを取り上げることにしよう:一つは、停止条件付金銭給付契約であり、 他の一つは停止条件付債権買取契約ないし債権買取予約である。
これらの方法によりリスクを引き受けた者について破産手続が開始された場合に、債権者のリスク引受人に対する権利がどのように処遇されるかを概観しておこう。
いずれの類型のリスク引受契約においても、(α)リスク引受料(プレミアム)が期間に応じて設定されているとみるべき場合には、契約が効力を失った後に未経過期間が残存するのであれば、 その期間に対応する料金は不当利得として返還されるべきである。その返還請求権は、契約が53条1項の解除により失効した場合には財団債権になるが(54条2項)、 それ以外の場合(保険法96条2項により失効した場合)には破産債権になる。また、(β)リスク引受人について破産手続が開始されたため、 債権者が新たなリスク引受契約を締結することが必要になる場合に、その費用を契約の不履行による損害として賠償請求できるか、債権者はその賠償請求権を破産債権として行使することができるかは、 個々のリスク引受契約ごとに検討されるべきである。特段の合意がなければ、賠償請求権を破産債権として行使することが肯定されるためには、54条1項の適用又は類推適用が肯定される場合であることが必要である。 同項の適用も類推適用もない場合でも、破産債権である非金銭債権の特質を考慮して、非金銭債権の評価(103条2項1号イ)の一つの方法として、 代替的契約をなすことの費用額をもって評価することも許されてよい。 なお、(α)の不当利得は(β)の損害(代替的契約を締結する際に支払う必要のあるプレミアム)に含まれ得るので、 その限りで、両請求権は部分的に請求権競合の関係に立つ。なお、双務契約の相手方が履行済みのために、彼の破産者に対する履行請求権が破産債権になる場合とのバランスを考慮すると、 (β)の損害(代替的契約費用相当額)の中には、契約締結のための交渉費用を含めるのは適当ではないであろう。
リスク引受人について破産手続の開始に至ることなく私的整理が行われるときには、多くの場合に、CDS契約の合意解除が必要になるものと予想され、そのための交渉が困難な仕事になるようである。
支払保証委託契約
これは、債務者が、債権者に対して負っている債務について、受任者(金融機関等)に支払保証を委託する契約である (「保証引受契約」ともいう。
文脈によってはこの語を使うこともある[100])。
代表例は、訴訟費用の担保の提供方法として民事訴訟規則で規定されている「支払保証委託契約」である
(民訴76条、 民訴規29条。
その外に、民執15条、民執規10条)。
この名称は、「保証委託契約」と混同しやすい点で難あるが、「支払」の語が付加されていることにより十分区別できよう。
契約の特質・内容・効果 債権者は、受益の意思表示により、支払保証人に対して保証債権を取得する。 この委託契約は、狭義の「第三者(債権者)のためにする契約」 (民法537条)と異なり、 次の点に特徴があり(特に1の特徴により)、広義の「第三者のためにする契約」に属する。
さらに、民事訴訟法等で予定されている支払保証委託契約では、次のことが契約内容に含まれなければならない(民訴規則29条)。
支払保証委託契約は、委任契約の一種であり、委託者(主債務者)又は受託者(保証人)が破産手続開始決定を受けることにより終了する(民法653条2号)。
しかし、この終了の効果は既往には遡らず、債権者の保証債権はこれにより影響を受けないと解すべきである。
この保証債権及び保証人の求償権の破産法上の取扱いは、保証委託契約及び保証契約が締結されている場合と同じである。
金額貸与の委任
内容 例えば、資金を必要とするAがBに融資を申し込んだところ、B自身は手許資金がないために、BがCにAへの融資を委任する場合に、
その委任契約を「金額貸与の委任」という([寺田*1973a]2号196頁以下参照。ここで「金額」は、「一定金額の金銭」の意味であるから、「金銭貸与の委任」ということもできる)。
CがAに融資した場合に、受任者が委任者に償還請求することができる費用となるのは、別段の合意がなければ、この委任契約の特質から、融資金そのものではなく、
Aが弁済期に弁済しないことによりCに生ずる損失(その時点での未回収金額)となろう。A・B間では、通常、BがCに金額貸与の委任をすることの委任契約が締結されるが、
その委任契約(A・B間の契約)がないときは事務管理となろう。AがCに弁済をしないため、BがCに弁済をした場合には、BはAに対して求償することができ、
この求償権は、この委任契約又は事務管理による費用償還請求権と位置づけられる。
歴史的にはこのような委任契約も行われていたようであり、債権者の担保保存義務(民法504条)の起源はこの金額貸与の委任契約にあると説明されている([寺田*1973a]2号22頁・48頁以下)。 この種の委任契約は、現在ではあまり目にしないが、現在でも可能である。
破産手続における取扱い Bについて破産手続が開始された場合に、104条1項の適用の有無が問題になる。 金額貸与の委任も、保証契約そのものではないので、別段の合意がなければ、 AがCに対して負う給付についてBがAの共同義務者になることはなく、 104条1項の適用はないとしてよいであろう。 Aについてのみ破産手続が開始された場合には、開始前の弁済及び破産配当により回収することができなかった不足額についてのみ、CはBに償還請求することができる。 Bについてのみ破産手続が開始されれば、将来Aが弁済しないことにより生ずる費用の償還請求権のみが破産債権となるが、これは、将来の債権であり、 Bの破産手続中にCのAに対する融資債権について弁済期が到来しなければ、この将来の債権(金額貸与の委任契約に基づく費用償還請求権)がBの破産手続における最後配当の除斥期間満了までに現在の債権になることはなく、 したがって、これについて配当を受けることはできない(198条2項)。 これを回避するためには、Cは、Aに対して融資する際に、「Bについて破産手続等の倒産手続が開始された場合には、Aは期限の利益を失う」との特約を入れておく必要がある。
信用補完契約(クレジット サポート アグリーメント(credit suppor tagreement))
内容 大企業(例えば自動車メーカ)が金融市場から多額の資金を調達する場合に、全額出資の金融子会社を設立して、その子会社に債券を発行させ、得られた資金をグループ内の会社
(親会社や関連会社)に、あるいは販売金融として消費者に貸し付けるという方法を用いることがある。 この場合に、子会社の信用補完のために、親会社が子会社と次の条項を含む合意をし、それをクレジット
サポート アグリーメントと呼ぶことがある。ここでは、それを信用補完契約と訳しておこう。
この契約の機能は、保証契約や保証引受契約に類似する。ただし、保証契約等の場合には、保証人等について破産手続が開始されたときを除外して言えば、 主債務者が履行期に債務を弁済にしないときに初めて債権者は保証人に保証債務の履行を求めることができるのに対し、 この信用補完契約では、履行期到来前に親会社に対して資金提供を請求でき、子会社が不履行に陥る事態を防止することができる点等に違いを見出すことができる。
破産手続における取扱い 子会社について破産手続が開始される場合には、それ以前において、親会社の資金提供義務は尽くされているはずであるので、 子会社の破産管財人が親会社に対して資金提供を求めるという状況はあまりないと思われるが、例外的に、親会社が資金提供義務を果たしていなければ、そのような状況もあり得るであろう。その場合に、親会社自身についても破産手続が開始されるような事態になれば、 破産管財人が信用補完契約に基づいて資金提供を請求することができるかが問題になり得る。
(a)金融子会社が債券の発行により得た資金を親会社に貸し付けておらず、金融子会社が親会社に対して有する債権は、この信用補完契約に基づく資金提供請求権のみであるとしよう。 子会社は、親会社から提供された資金を再び親会社に返還する義務を負うことになるから、信用補完契約は、破産手続開始時において双方未履行の双務契約である。 親会社の破産管財人は、53条1項により契約を解除することができ、解除の効果は発行済み債券にも及ぶ。 (α)これを保証契約との違いであるとして是認するか、 それとも、(β)本質的な機能は保証引受契約と同一であるから、親会社の破産管財人は契約を解除することができないとするかが問題となる。
二つの選択肢のうちのどれを採るべきかを決定する前提として、後者の選択肢を採ると、どのようなことになるかを検討することにしよう。 例えば、金融子会社が100億円の債券を発行していたとする。 子会社の破産管財人は、親会社の破産手続おいて、100億円の資金提供を請求し、1割配当であるとすれば、10億円の償還用資金を得ることができる。 この資金は、約定に従い特定の債券の償還のためにのみ用いられるべきであり、その他の破産債権への配当のために用いられるべきではない。 親会社は、子会社の破産手続においてこの10億円の返還請求権を破産債権として行使することができるべきである (この返還請求を破産手続開始前に原因のある信用補完契約に基づく債権であると考えることができるかの問題が生ずるが、ここではそれを前提にする。信用補完契約を双方未履行の契約とみて、 その履行が選択されたと考えれば、返還請求権は財団債権になるが、それでは、子会社の他の破産債権の負担において債券保有者が親会社から提供された資金により優先弁済を受けることになり、不当な結果が生ずる)。 しかし、債券保有者は全額の満足を得ていないので、彼の破産債権は信用補完者の資金返還請求権に優先すべきであると考えられる(保証の場合であれば、104条2項の問題である)。 そして、債券者が子会社の破産手続に参加すれば、親会社は資金返還請求権を行使することができないとしないと、子会社の債権者間の公平がとれない (保証の場合であれば、主債務者の一つの給付義務について、保証人が求償権を行使するとともに債権者が被保証債権を行使することはできないとの原則(104条3項ただし書)の問題になる)。 債券保有者が子会社の破産手続に参加しない場合に、親会社が10億円の返還請求権を破産債権として行使し、その1割配当の場合であれば、1億円の配当を受けて、それが親会社の破産財団に属することになる。
上記の結果は、それ自体としてはそれほど問題はないが、信用補完契約の内容と整合するかは疑問である。 信用補完契約においては、親会社について破産手続が開始された場合の処理に関する規定がないが、保証契約でないと明示されており、 債券保有者が親会社に対して有する権利として明示されているのは、子会社への資金提供を求める権利であって、自己への支払を請求する権利ではない。 親会社が破産手続開始後に提供した資金の返還請求権を破産債権とすることは、かなり特例的な取り扱いであろう。 その点は別にしても、債券保有者が子会社の破産手続に参加している場合には、親会社の破産管財人は提供資金の返還請求権を破産債権として行使することができないという結果は、 信用補完契約からは読み取れず、当事者の予期しない結果と言うべきである。また、債券保有者が子会社の破産手続に参加しない場合に、親会社の破産管財人は提供資金返還請求権を破産債権として行使することができるが、 そうなると、親会社の破産手続は、子会社の破産手続において最後配当が行われるまで終了することはできないことになり、それが手続の渋滞の要因になる。 信用補完契約の実質は保証引受契約であるとして、債券保有者に親会社の破産手続に直接参加することを認めれば、こうした問題は生じないが、 しかし、これらの契約の違いに鑑みれば、信用補完契約の実質的機能は保証契約のそれに近いとはいえても、実質的に同一とまではいえない。 したがって、上記の(β)の選択肢は、信用補完契約の内容と整合しないと考えるべきであり、(α)の選択肢をとるべきである。
(b)金融子会社が債券の発行により得た資金を親会社にのみ貸し付けている場合には、通常は、親会社から返還された資金で債券の償還が可能になるから、親会社に対する貸付金返還請求権を問題にすれば足りる。これに重ねて信用補完契約に基づく資金提供請求権を破産債権として行使できるとする必要はない。
位置付け 信用補完契約は、補完者に資力がある限り、債務者が支払不能になる前に信用補完を請求できる点で、保証契約よりも債権者にとって有利であるが、補完者について破産手続が開始される状況になれば、 双方未履行の双務契約として破産管財人によって解除される結果、保証契約よりも債権者にとって不利であり、そのようなものとして保証契約とは異なる契約として独自の存在意義のある契約と考えるべきである。
その他の論点 (1)ここで取り上げている信用補完契約にあっては、その条項(c)により、親会社について倒産手続が開始されている場合は別として、
そうでない限り、子会社が債券の償還をしないとき、債券保有者は親会社に対して償還用資金を子会社に提供することを請求する権利を有する。その点で、その条項は第三者のための契約である。
債券保有者が有する請求権は、資金を自己に給付することを求める権利ではなく、債務者である子会社に給付することを求める請求権である。この点に迂遠さがあるが、契約の文言に素直に従う限り致し方ない。
ただ、提供された資金が債券の償還以外の目的に使われることを阻止するためには、子会社が有する資金提供請求権を差し押さえて、その取り立てをする方がよいであろう。
債券保有者以外の者は、この請求権を差し押さえて自己の債権の満足に宛てることはできない。それはこの請求権の目的に反するからである。
(2)子会社の支払不能後・破産手続開始前に償還用資金が子会社に支払われた場合に、子会社がその資金を用いて債券保有者に弁済することは否認の対象にならないとしてよいであろう。
この弁済と債務負担は、債務の内容(特に利息)が債務者に不利に変わるのでない限り、結局のところ、債務の借り換えだからである(不利に変更された場合には、当該部分のみを否認すれば足りる)。
(3)親会社が子会社に対して債務を負っている場合に、子会社の支払不能後・破産手続開始前に資金提供をしたことにより生ずる資金返還請求権を自働債権にして、
子会社の親会社に対する債権と相殺することも、72条2項3号又は4号により許容される(72条1項2号・3号の適用を受けない)。
この場合には、親会社から提供された資金を用いて債権者に弁済することは、
単純な資金の借り換えとは言えず、親会社からの弁済金を用いて特定の債権者に弁済することに近いが、 信用補完契約の特質を考慮すれば、受託保証人が保証債務を履行してその求償権を自働債権にして主債務者の保証人に対する債権と相殺する場合と同様に許容されると考えるべきであり、
債券者への弁済も否認対象にならないと解すべきである(子会社が支払不能等になった後に債券者に弁済がなされた場合には162条1項1号柱書本文の要件を満たすことになる。
それにもかかわらず否認できないとするためには、その根拠として、信用補完契約の特質を持ち出さなければならない)。
(4)親会社から子会社に償還用資金が提供される前に子会社について破産手続が開始され、
親会社については破産手続が開始されないという事態は、ほとんど生じないとは思われるが、それでも検討しておくべきである。
この場合でも、親会社が子会社に対して債務を負っていなければ(つまり相殺の問題が生じなければ)、親会社から提供された資金はその目的に従い債券の弁済にのみ用いられるべきである。
この結論を正当化するためには、親会社が取得する資金返還請求権は、破産債権としなければならない。信用補完契約を双方未履行の双務契約とみた場合には、
破産管財人がその履行を選択したときに相手方に生ずる債権は財団債権になるのが本来であるが(148条1項7号)、これは、未履行契約の履行が破産債権者全体の利益になる場合の規定であり、
特定の債権者のために履行が選択される場合には、別段の配慮が必要であり、今問題にしている場合については、破産債権にしかならないとすべきである。 そのように解すれば、
債権者が債券保有者から親会社に入れ替わることにより他の破産債権者が悪影響を受けることはない。
もっとも、破産管財人が特定の債権者のために職務をする必要があるのかという問題が生じよう(特に親会社が任意に弁済しない場合に、訴訟を追行すべきかの問題が生じよう)。
償還用資金の提供請求権を債券保有者に譲渡すること(債券保有者のために破産財団から放棄すること)も許すべきであろう。 ただ、ここまで来ると、子会社についてのみ破産手続が開始された場合には、
信用補完契約に基づく親会社の償還用資金提供義務は、債券買取義務に転化するとする方が単純である。 しかし、契約の文言はそこまで踏み切ることをためらわせる。
(4a)親会社が子会社に対して債務を負っている場合には、親会社が子会社に提供した資金の返還請求とこの債務とを相殺することができるかが問題となる。
親会社の債権は、破産手続開始前に締結された信用補完契約に基づく債権であり、破産債権であるとみれば、これを自働債権として、子会社の親会社に対する債権を受働債権とする相殺が許される。
しかし、これは、破産財団に属する親会社に対する債権の換価金から債券保有者のみが満足を得るのと同じ結果になるので、債券保有者以外の破産債権者には非常に不利なことである。
しかし、同様なことは、受託保証人が破産者に対して債務を負っている場合に、受託保証人が主債権者に債務を弁済した後で、保証委託契約に基づく事後求償権を自働債権として相殺する場合にも生ずることであり、
許容してよいであろう。この点では、信用補完契約は、保証契約に近い。
その他
企業の金融取引においては、親会社が子会社・関連会社の信用補完のために様々な書面を作成し、関係人に交付することがあり、 その法的な意味が問題となる。
代表的類型として、次のものがある([若松*2002a]12頁参照)。
これらの合意ないし契約は、正規の保証契約の代替手段の面がある。すなわち、保証契約が締結された場合には、保証債務は偶発債務(主債務者が債務を履行しない場合に現実化する債務)であるので、 直ちには貸借対照表に負債として記載する必要はないが、注記しなければならない(企業会計原則「第3 貸借対照表原則」1C)。 発生の可能性の高いものについては(かつ、それのみについて)引当金を計上する(企業会計原則注解第18。 これらの資料は、オンライン企業会計原則-So-netに掲載されている)。 そのため、債務者の親会社に保証契約の締結を回避しようとする圧力が生じ、このことが上記の代替手段を採る一つの要因となる。いわば、姑息な代替手段であり、 親会社について破産手続が開始されたときに、貸借対照表に注記されていないもの(開示されていないもの)が保証と同等の効力を有する契約として突如浮上して、 破産債権を増加させたり、あるいは財団所属債権との相殺により破産財団を窮乏化することを認めることは許されないとの議論も出てきやすい。 しかし、まずは当事者間における契約の効力を定め、その効力に従って貸借対照表に注記すべきか否かを論定すべきである。
保証予約にもさまざまな類型が考えられるが、主として会計上の理由(保証人となるべき者の財務諸表に開示することを避ける目的)で利用されてきたものであるが、 破産法上は保証契約と同様に扱ってよい(したがって貸借対照表に注記すべきであろう)。なぜなら、
経営指導念書や与信念書が保証と同等の効力を持つか否かは、個々の事件における意思表示の解釈の問題となる。特定の融資案件について作成されたこれらの書面は、
保証と同様な効力(経営指導念書にあっては、監督義務)が認められる場合もあろうし(親会社と子会社間で締結された経営指導念書は、一種の第三者のための契約となる)、否定される場合もあろう。
法人の債務について無限責任を負う構成員を「無限責任員」と呼ぶことにしよう。典型的には、合名会社や合資会社の無限責任社員がこれにあたる。 無限責任員は、 法人の全債務について弁済責任を負い(無限責任社員について会社法580条1項[78])、保証人と同じ地位にある。 法人の債権者は、無限責任員の破産手続に、手続開始時の債権額でもって、参加することができる(106条)[CL10]。 内部的な損失分担を超えて法人の債権者に配当がなされた場合には、無限責任員(破産者)はその額につき、他の責任員に対して求償権を有する。 また、法人自体に対して求償権を有するとともに、債権者が有していた権利を代位取得する(民法499条・501条)。 これらは、破産財団に属する財産として、破産管財人が行使する。
持分を譲渡した無限責任社員は、その旨の登記前に生じた会社債務について無限責任を負い(会社法586条1項)、その限度で破産法106条の適用を受ける。
合名会社や合資会社の無限責任社員について破産手続が開始されると、彼は退社する(会社法607条1項5号。 ただし2項に注意)。 彼は法人に対して持分払戻請求権を有し(会社法611条1項本文)、これは、破産財団に属する財産として、破産管財人が行使する。 会社以外の法人の無限責任員についても、別段の定めがなければ、同様である。
法人の債務について有限責任を負う構成員を「有限責任員」と呼ぶことにしよう。典型的には、合資会社や合同会社の有限責任社員がこれにあたる。 一般に、有限責任員も、未履行の出資義務の範囲で、法人債権者に対して直接に責任を負っていると理解されている(会社法580条2項)。 しかし、法人債権者が有限責任員の破産手続に直接参加すると、破産手続が複雑となる。そこで、法人債権者の権利行使を認めないこととし、その代わり、法人が未履行の出資義務の履行を求め、 これにより法人財産を充実させて法人債務の弁済を確実にすることとされた(有限責任員の法人債権者に対する責任の間接化)。
会社について破産手続開始原因が存在しない場合について考えてみよう。破産手続が開始された有限責任社員が会社を退社するときは(会社法607条1項5号。2項に注意)、 当該有限責任社員は、持分の払戻しを受けることができる(会社法611条1項本文)。払戻請求権が現実に発生するか否かは、会社の財産状態に依存するが、債務超過でないことを前提にすれば、 通常は払戻請求権が発生し、払戻しが金銭によりなされることを前提すると(会社法611条3項)、これと会社が有する出資請求権とは相殺可能である。会社が極めて健全であり、 会社に未払債務がない場合、極端に言えば会社債権者が存在しない場合には、会社財産の充実の問題は生じないが、それでも、出資請求権があれば行使され、それと持分払戻請求権とが相殺されることになる。
会社が債務超過の状態にある場合には、早晩、会社についても破産手続が開始されることになるが、開始されているか否かにかかわらず持分払戻請求権は無価値であり、 出資請求権と持分払戻請求権との相殺の問題は生じない。会社(又はその破産管財人)により出資請求権があれば行使され、会社財産の充実が図られる。
リスクの大きい事業については、事業主体の負担を軽減するために、責任財産を当該事業のための特別財産(当該事業に用いられる財産、当該事業から得られる財産等)に限定した資金調達が行われることがある。 プロジェクト・ファイナンスと呼ばれるものである([若松*2002a]参照[23])。
(a)責任限定を確実にするために、次のような措置がとられることがある。
(b)上記のような措置をとらない場合には、事業主体たる会社は、≪当該事業への融資者が会社の他の財産から弁済を得ることができないこと≫を特約により明確にしておく必要がある (融資契約において、責任財産を限定する旨の特約で足りと思われるが、念のために、責任財産から弁済を受けることができなかった残債権を放棄する旨の特約を付しておく方が確実である)。 当該事業が失敗した場合には、当該特別財産の任意清算となる。ただ、事業主体たる会社自体が破産した場合には、他の一般債権者は、当該事業のための特別財産からも弁済を得ることができるので、 プロジェクト・ファイナンスの融資者は、その財産に担保権の設定を受けて、優先権を確保しておく必要がある。
信用リスク移転契約も、経済社会の中の一つの道具であり、それ自体が社会全体の信用を膨張させる自動装置になるというわけではない。 例えば、銀行の子会社が銀行の貸出債権(例えば住宅ローン)の保証を行う場合には、当該子会社(信用保証会社)の実質的な機能は、任意の履行がなされなくなったローンを法的手段を用いて回収することとみてよい。 そこには、銀行の社会的好感度を保つために、債権回収という泥臭い業務を銀行の外に出すと共に、銀行退職者の受皿を用意するという意味合いさえある。 そのような機能を有する信用保証会社への信用リスクの移転が信用膨張の道具となるという事態は、あまり考えられない。
しかし、道具は、使い方により利器にも凶器にもなる。このことは、信用リスク移転契約にも妥当する。金銭債権の債務不履行のリスクを最も把握しやすい立場にある者は、通常、原債権者である。 したがって、金銭債権のリスクの移転は、リスク発生の具体的事情を知る者から知らない者への移転となり、そこに過大なリスク引受けの要因がある。 原債権者以外の者による過大なリスク引受けは、 原債権者による過剰融資の原因となり、社会全体における信用膨張となる。それは、
新種のリスク移転契約に潜むこの危険性に人々が慣れていない場合には、リスク移転契約がバブルを促進する機能を果たすことに注意する必要がある。
2006年に崩壊が始まったアメリカの住宅バブルは、住宅取得者への過剰な信用供与が原因となっており、クレジット
バブルと呼ばれることもある。バブルの生成(クレジットの膨張)には、新種の信用リスク移転契約が大きな役割を果たしていた。バブルの舞台装置として、次の2つを指摘することができる。
(a)信用保証は、保証料が一定期間ごとに分割して支払われる限り、現実に発生する債務不履行による損失 (立替払金と抵当権の実行等による回収金との差額)と保証料とのバランスを比較的安定的に保つことができ、 ある時期に多くの信用保証を行うことが会社に多くの収益をもたらすというわけではなかろう。 しかし、保証期間全体にわたる保証料の半額を契約締結時に前払させる保証契約と、前払された保証料を契約締結期の収益に計上する会計制度と、 その収益が直接に担当者の報酬に反映されるような報酬体系を採用している会社にあっては、担当者は、信用リスクを十分に吟味することなくできるだけ多くの保証契約を締結する誘惑に駆られる。
(b)そして、原債権者が自己の融資した債権を信用保証付で売却することにより融資の原資を回収することができるようになると、信用膨張の社会的危険はさらに高まる。 すなわち、住宅ローンのような長期の融資を実行した原債権者が債権を転売することなく保有して、分割弁済により順次回収される資金を次の融資にあてるという場合には、 信用膨張のリスクは小さい(例えば、ある時に10億円の資金を用いて、1億円づつ10年間貸し付ける融資を10件行う場合には、 次の融資は、1年後に回収した1億円(1件につき1000万円×10件)で1件できるだけである(利息収入は無視した))。 しかし、貸付業者が融資債権を信用保証付で売却して資金を回収することができるようになれば、1件1億円の融資を10件行い、 それを1月後に全部売却して次の10件の融資を行い、1年間で総計120億円の融資を行うことも可能になる。 売却を容易にするためには、高利の融資を行う必要があり、高利の融資を利用する者は資力が乏しいのが通常であるが、 担保となる不動産の価格が上昇期にある間は、 名の通った会社の格付と信用保証があれば、債務者の信用力が乏しいことは陰に隠れ、融資債権は容易に売却できる。 この債権売却による融資の回転が高速度で行われ、 しだいに適当な融資先を見いだすことが難しくなり、最終段階では、返済能力が極めて乏しい者を対象に、 高金利と引換えに当初の数年間の弁済を猶予するという条件で融資するところまで行った。 いわゆるサブプライム ローンである。融資を実行する者には、その融資のリスクはわかっている。 しかし、債権買取りの形でリスクを引き受ける者には、それがわからない。リスクの階層化によりスーパー シニアなどという名が付されれば、危険性はますますわからなくなる。 こうして、異常なまでに信用が膨張し、そして崩壊した。信用バブルの崩壊が最高潮に達したのが2008年のリーマン ショックであった。
プロテクションの売手の財産的危機 CDSにあっては、クレジット イベントが発生した場合に、プロテクションの売手が所定の義務を履行するかは、彼の財産状況に依存する。 売手自体が破産すれば、プロテクションは、無価値になる。プロテクションの買手は、この点の危険を回避する必要がある。 そのために、プロテクションの売手(例えば2008年の金融危機の中心の一つとなったAIGのような保険会社)の株価が一定の水準を下回れば、 売手は参照債務に相当する額の担保を買手に提供しなければならない旨の特約が結ばれていることがある。ここにも、大きな危険が潜んでいる。
(a)景気循環 プロテクションの買手が支払うべきプレミアムのかなりの部分は、CDS契約時に売手にまとめて支払われる。 一括して支払われたプレミアムが、その時点で売手の収益に計上されるような会計処理がなされ、それが従業員の業績給に反映されるような給与制度が採用されている場合には、 プロテクションの売手の従業員には、できるだけ多くのプロテクションを販売しようとする誘因が働く。好景気のときには、通常、CDS取引の参照債務の格付けが高いので、 従業員は、大量のプロテクションを売却して多くの利益を計上し、多くの給与を得ようとする。優良な保険会社がプロテクションの売手となっているCDSによって保護されている債券は安心して買われるので、 これにより、さらに信用が膨張する。例えば、多くの人が金融機関から融資を受けて不動産等を購入し、 その貸付金債権を証券化した金融商品が再びプロテクション付きで売却され、 その売却代金が再び融資に回されるという形で、CDSが景気の高進に寄与する。しかし、好景気が永遠に続くことはない。 例えば、優良債務者がこれ以上融資を受けて不動産等を買うつもりはないというほどに融資が行き渡った後で収入の乏しい債務者に不動産等の購入資金が融資されるようになると、 融資の焦げ付きが目立つとともに、不動産等の価格の上昇も止まる。その頃には、好景気の間に拡大した供給力よりも需要の方が小さくなり、景気後退になる。
(b)プロテクションの売手の危機 景気が後退してクレジット イベントが多発すると、プロテクションの売手(A)の経営危機が噂されるようになる。 その内情(株価が下落すれば担保提供義務が生じ、それを履行できなくなればデフォルトになること)をよく知っているプロテクションの買手は、Aを参照債務者とするプロテクションをBから購入した上で、 Aの株式を大量に空売りしてその株価を下げ、A社の資力を超える担保提供義務を発生させて、A社を倒産に追い込むことができる。これにより、A社の株の空売りから利益を得ることができるとともに、 B社から約定の金銭を得ることができ、場合によればB社も倒産に追い込むことがでる。それを見込んでB社の株式を空売りしておけば、これからも利益を得ることができる。 実際には、このシナリオ通りには行かないであろうが、ただ、最初のプロテクションの売手であるA社が破産寸前に追い込まれることは、実際にある。
(c)評価 このように、CDSは、リスク管理を一歩誤ると、信用を過度に膨張させ、そして、プロテクションの売手を破綻に追い込み、 その売手を参照債務者とするCDS契約のプロテクションの売手をさらに破綻に追い込むという危険性がある。 各自が自己の利益を追求するために契約を自由に締結できることは、 自由主義社会の重要な基本原則であるが、しかし、自由に締結された契約の全てが社会の進歩に役立つわけではない。 社会の進歩、人々の幸福につながらない契約は、制限されるべきである。典型例は、賭博契約である。CDSの社会的有用性は、どの範囲で認められるか。それが問題である。
プロテクションへの投資
ある参照法人について倒産処理手続が開始されることをクレジット イベントとする期間5年、想定元本100億円のCDS契約を考えてみよう。
議論を単純にするために、プレミアム(保証料)を年1%とし、5年間のプレミアム5億円全額の前払が合意され、その支払がなされたものとする。
また、プロテクションの買手が参照法人に対して債権等を有していることは必要でなく、かつ、プロテクションの買手の地位を自由に譲渡できるものとしよう。
このCDS契約は、停止条件付金銭給付契約であり、プロテクションの買手の地位は、譲渡可能な停止条件付金銭債権を有する者の地位となる。 この債権を用いて利益を挙げる方法は、いくつか考えられる。
他にも利用の方法はあるのであろうが、ともあれ、このように参照法人の信用リスクが変動することによりプロテクションの価格が変動することを利用して、 収益をあげることができるので、 「プロテクションへの投資」が話題になることがある。これは、買手側の投資である。
リスクへの投資
CDSは、売手側にとっても投資の側面を有し、時に「リスクへの投資」と言われることもある。その趣旨は、次の点にある([ピムコ*2007b]がわかりやすい):
債券投資は、本来的に、発行主体の倒産のリスクを伴う;そのリスクにあわせて利息を徴収することができるように、倒産リスクにあわせてプロテクションのプレミアムが決定されるのであるから、
ある参照法人についてプレミアムを受け取ってプロテクションを売ることは、当該法人の債券に投資することに類似する。
換言すれば、純粋に投資の視点から見れば、通常の債券投資では、投資家は、最初に債券発行主体に債券購入代金を支払うことによりリスクを負い、リスクに見合った利息を受け取る。
CDSによるリスクの投資は、最初の債券購入代金の支払を省いたものである。
このような形態でのリスクへの投資と通常の債券投資との違いは、損失の負いかたに現れるが、リスクに見合った利息ないしプレミアムを受領するという点で類似性がある。