
訴訟要件 1
栗田 隆

 |
[←| 目次|文献略語 |→]
民事訴訟法講義
訴訟要件 1関西大学法学部教授
栗田 隆 |
 |
訴訟要件は、次のことの要件ではない。
次のものを訴訟要件と見るべきかについては議論があるが、この講義では訴訟要件ではないと考える。
これに対して、次の訴訟要件は、もっぱら当事者の処分に委ねてよい利益に関わり、当事者からの指摘ないし申立てをまって調査すれば足りる(抗弁事項)。
判断資料の収集
職権調査事項であるか否かは、誰の発意で調査を開始するか否かの問題である。これと、誰の責任において判断資料を収集するかの問題とは別個の問題である。どのような事項について誰がどのような資料収集責任を負うかについて、見解が分かれている。
(A)通説は、次のように分類する。
(B)しかし、中間的な審理方式として弱い職権探知(職権審査)を認めて、訴訟要件の性質に応じて、より細かな配分を行うべきである([高島*1984a]117頁以下[39])。
(C)職権審査事項と弁論主義に服する事項とに2分し、訴えの利益を含め職権調査事項は基本的に弱い職権探知(職権審査)によるべきであるとする見解([中野=松浦=鈴木*新民訴v2.1]406頁以下(松本博之))。
| 対象事項 | A説(通説) | B説 | C説 | |
|---|---|---|---|---|
| 職権調査事項 | 下記以外のもの |
職権探知 |
強い職権探知 |
弱い職権探知 |
| 訴えの客観的利益・ 当事者適格(対世効のある判決の場合を除く) |
弁論主義 |
弱い職権探知 |
||
| 任意管轄 |
弁論主義 |
|||
| 抗弁事項 | 仲裁合意・不起訴の合意・ 訴訟費用の担保提供 |
弁論主義 |
||
規則14条は、「裁判所は、法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものとして訴え、又は訴えられた当事者に対し、定款その他の当該当事者の当事者能力を判断するために必要な資料を提出させることができる」と規定しており、これは、(強い)職権探知を認めたものと理解することができる。当事者能力も弱い職権探知に服させようとするC説は、これと整合的ではない。
訴訟要件の判断時期
訴訟要件は本案判決の要件であるので、各審級の裁判所は、その判決内容を決定する時点で訴訟要件が備わっているか否か判断する。上告審は、法律審であるとの特質により、事実審の口頭弁論終結時に訴訟要件が具備されていたか否かを判断すべきことを原則とするとの見解もあるが、むしろ、上告審についても、その判決時を基準に判断することを原則とする方がわかりやすい([梅本*民訴v2]299頁以下)。例:
しかし、訴訟要件の特質に応じた例外がある。訴訟要件に関する主張の制限により、判断時期が前倒しになり、これにともない判断基準時も前倒しになる(前記の原則より早まる)ことがある。
さらに、信義則により、事実審の口頭弁論終結後の事由を主張することが許されない場合がある。
補正不能であることが明らかな訴えを被告への訴状送達前に判決により却下することができるかについては、見解は分かれるが、肯定して良い(最高裁判所 平成8年5月28日 第3小法廷判決(平成7年(行ツ)第67号)・判例時報1569号48頁)。訴状送達前に訴えを却下する場合には、却下判決を被告に送達する必要はない(前掲最判)。
訴訟要件を欠く訴えに対する裁判は、前記 a, b の場合を別とすれば、「訴えを却下する」である。これは、「請求について判決しない」ということを意味する。訴訟要件が充足される場合には、原告が訴えをもって主張した法律関係の存否を審理し、それが認められる場合には、それが認められる範囲で、原告が要求した通りの判決(請求認容判決)をする。それが認められなければ、「原告の請求を棄却する」という主文の判決をする。「訴え却下」と「請求棄却」の用語は、このように使い分けるのが現在の約束事になっている[63]。
訴えの利益の語は多義的であり、この概念の中に何を含めるかは教科書によって微妙に異なる[19]。
訴えの利益の問題は、本案の問題と重なり合うことが多い。本案の問題と重なる範囲では、原告の主張を基に訴えの利益の有無を判断するのが原則となる[57]。
法律上の争訟は、字義に従えば、(α)「法を適用して解決できる争い」を意味するが、これに該当する紛争でも、裁判所が判決手続により解決するのに適しない紛争もある。そこで、法律上の争訟の語は、 (β)「裁判所が判決手続により法を適用して解決するのに適する争い」の意味で使われる場合がある[60]。
個々の事件を離れて一般的に、裁判所が裁判をなすに適する請求であることを請求適格(または、権利保護の資格)という。そのような請求であるためには、法律上の争訟を解決する請求でなければならない。この講義では、「請求適格のある請求」と「法律上の争訟」とを同義に用いる。請求適格を有するためには、次のことが必要である。
(a)請求が具体的な権利または法律関係に関するものであること 現在の日本では、訴訟は、具体的な法的紛争を解決する制度であるとされている。従って、次のものは、請求適格を有しない。
(b)法令の適用により解決することができる紛争であること これも最高裁の確定判例により、裁判所法3条にいう「法律上の紛争」の要件とされている(前記(a)と併せて、「裁判所がその固有の権限に基づいて審判することのできる対象は、当事者間の具体的な権利義務ないし法律関係の存否に関する紛争であつて、かつ、それが法令の適用により終局的に解決することができるものに限られる」と説かれている(最高裁判所 昭和56年4月7日 第3小法廷 判決(昭和51年(オ)第749号)))。
ただ、請求が具体的な権利または権利関係に関するものである場合には、通常は、その請求は法令の適用によって判断できるはずのものである。それにもかかわらず、裁判所が判決の求められている紛争を「法令の適用により解決するのに適しないもの」として、本案判決を拒むことは、相応の理由のある例外的な場合にのみ許されることである。その例外的な場合は、憲法により保障された重要な利益の尊重あるいは制度枠組みの維持のために、裁判権の行使を自制すべき場合と一括することができよう。この講義では、(b)の要件を「裁判権の行使を自制すべき場合に該当しないこと」に置き換えて、これも請求適格の要件に含めておこう[27]。裁判権行使の自制の仕方には、(α)請求適格を欠くものとして訴えを却下するという態様と、(β)個々の争点について裁判所の判断を控えるべきであるとしつつ、請求適格は肯定し、証明責任の分配原則等に従って本案判決をするという態様の2つがある[50]。紛争解決の視点からは(β)が好ましいが、ここで問題にするのは(α)の態様での自制である。この視点から、次のことが訴訟要件となる。
(b1)信教の自由(憲法20条)の保障のために裁判権の行使が自制されるべき場合でないこと 請求自体は法律関係の主張である場合でも、請求について判断するためには宗教上の教義自体の当否や信仰の対象物の真否の問題に立ち入ることが不可欠であり、裁判所の理由中の判断が信教の自由に影響を及ぼす虞がある請求については、裁判所は当該法律関係自体についても判断すべきではなく、その法律関係をめぐる争いは実質的に見て法律上の争訟に当たらず、訴えを却下すべきであるとするのが最高裁の立場である[45]。
もっとも、宗教団体といえども、純粋な宗教活動のみならず,その宗教活動のための財産を所有管理し,さらにはこれらのための事業を行うなど,一般市民法秩序にかかわる諸活動をする。こうした世俗的問題については、裁判所の保護が必要であり、裁判所は、宗教上の教義に立ち入ることなく本案の問題を判断できる場合には、できるだけそのようにすべきである。
平成12年の第1小法廷判決は、平成11年の第3小法廷判決やその後の最判平成14年2月22日 第2小法廷 判決(平成11年(受)第1455号)と対照的である。事案の差異というより、各小法廷を構成する裁判官の考えの違いであろう。第2小法廷判決および第3小法廷判決でも、第1小法廷判決と立場を基本的に同じくする少数意見が付されている(元原利文裁判官、河合伸一裁判官、亀山継夫裁判官)。大法廷判決により決着を付けるのが適当な時期にあるように思われる。
なお、訴訟物たる法律関係の判断の前提問題が教義に関係する場合の裁判権行使の自制の方法については、前述のように、(α)訴えを却下する方法と、(β)教義に関わる争点についての判断を自制した上で本案判決をする方法との2つがあるが、学説上は、後者の選択肢を採る見解も有力である。両選択肢の差異は、次のような事例において現れよう。
(b2)三権分立の建前から、裁判権の行使が制約される場合でないこと。
(c)訴訟による救済を必要とする利益が問題となっていること この要件の下には、次のものを含めることができる。
(c1)定型的に訴訟以外の手続で権利を行使すべきものとされている類型の権利は、その手続によるべきであり、訴訟の利用は許されない
(c2)一般市民法秩序と直接の関係を有しない団体の内部問題については、団体の自律性が尊重されるべき場合があり、そのような問題は司法審査の対象から除外される(自律性の尊重の程度は、団体の種類により異なる[53])。この要件は、司法権行使の抑制の面もあるが(部分社会論)、この講義では、むしろ、団体の内部紛争のうちの一定範囲のものは、訴訟による救済を必要とする利益が争われているのではないという視点からこの要件を取り上げることにする。
民事請求適格
人事訴訟を含めて民事訴訟により裁判所が裁判をなすのに適する請求であることを民事請求適格と呼ぶことにする。前述の要件を満たす法律上の争訟のうち行政訴訟の対象となるべきものが除外される。
140条との関係
請求適格を欠く訴えは、140条の口頭弁論を経ない却下の対象となり得る。そのため、無意味な訴えについて口頭弁論を開く負担から裁判所と被告を解放するために、請求適格の要件を厳格にしようとする誘因が働く。しかし、140条の効能を重視することは、他方で、国民の裁判を受ける権利を狭める虞がある。請求適格を欠き、補正不能[29]であることが明かな場合以外は、請求適格の有無自体についても弁論の機会を与えるべきである。
権利保護の利益が否定される場合を、必要性を欠く場合と許容性を欠く場合(法令等により禁止される場合)とに分けてあげておこう(必要性と許容性の双方が問題になる場合もあるが適宜一方に分類した)。
(a)必要性を欠く場合
(b)許容性を欠く場合
重複起訴の禁止(142条)は、再訴禁止・別訴禁止と同列に置かれ、権利保護の利益の欠如の事由としてあげられることもある。しかし、重複起訴の禁止は、厳密には起訴の態様についての制限である。例えば、債務者からの債務不存在確認の訴えに対抗して債権者が支払請求の訴えを提起することは、別訴としては許されないが、反訴としては許される。この点で、再訴禁止・別訴禁止に抵触する訴えが常に不適法として却下されるのとは異なる。そこで、この講義では、重複起訴の禁止を権利保護の利益の問題から除外する[4]。
訴求力を欠く債権
訴求力を欠く債権について訴えが提起された場合に、請求棄却判決をすべきか、訴え却下判決をすべきかが問題となる。これは、請求棄却判決をした場合の既判力の生ずる判断内容をどのように定めるかとも関係し、また、当該債権に残されている効力が何であるかにも依存する[CL1]。
最高裁判所 平成19年4月27日 第2小法廷 判決(平成16年(受)第1658号)は、第2次大戦中に日本国内に強制連行され、建設会社により強制労働に従事させられた中国人労働者の建設会社に対する損害賠償請求について、この訴訟の対象たる損害賠償請求権にも昭和47年の日中共同声明5条の請求権放棄の効力が及び、この放棄により原告は請求権自体を失ったのではないが、裁判上訴求する権能を失ったというべきであり,そのような請求権に基づく裁判上の請求に対し,被告が請求権放棄の抗弁が主張したときは,当該請求は棄却を免れないとした[66]。
次のように考えたい。一般に、債権の対内的効力として次の効力が認められている:(α)給付保持力、(β)請求力(裁判外で弁済を要求する権能であり、弁済要求行為を適法にする効果がある)、(γ)訴求力、(δ)掴取力。給付保持力のみが認められる債権[73]ついては、請求棄却判決をすべきである。消滅時効にかかった債権も同様である(ただし、その債権の支払請求を棄却する判決が確定した後でも、消滅時効完成前に相殺適状にあった相手方の債権を受働債権とする相殺に供することはなお許されるべきであるから、訴求債権が時効により消滅したことを理由とする請求棄却判決と債権が弁済により消滅したことを理由とする判決とでは、既判力の生ずる判断の内容に差異をもたせることが可能であることに注意する必要がある[70])。破産免責の効力の及ぶ債務は、債務自体が消滅するのか、それとも責任のみが消滅して自然債務として存続するのかについては争いがあるが、存続するとしても給付保持力のみが認められ、請求力は否定すべきであるから、この債権が訴求された場合にも、請求棄却判決をすべきである。日中共同声明により訴求力を失った債権にどの効力が残されているかは明瞭ではないが、掴取力を欠くことは明らかであり、おそらく請求力も欠いているというべきであろう。
他方、訴求力のみを欠き他の効力は具有している債権が主張されている場合に、請求棄却判決をすることは許されず、訴え却下判決をすべきである。その債権のために担保権が設定されている場合に、その担保権の行使を許容する点(配当異議訴訟は、誰が原告になるかにかかわらず、許容してよいであろう)、あるいは、訴え却下判決確定後に債権者が債務者との話し合いにより執行証書を得て強制執行する余地を認める点に意味がある。
訴訟物が同一の場合には、既判力により解決できるので、紛争の蒸返しの禁止の法理を適用する必要性は少ない。しかし、それでも、訴訟物が異なる場合にこの法理が認められるのであれば、訴訟物が同一の場合にはなおのこと認められるべきである。例えば、貸金返還請求訴訟で債権の不存在を理由に敗訴した債権者が、同一債権について再度訴えを提起した場合には、この法理を適用して訴えを却下することは、認められてよい。認める実益は、140条により口頭弁論を経ることなく迅速に判決を下し、被告を訴訟の重圧からすみやかに解放する点にある。同一訴訟が再三提起されるような場合には、被告に訴状を送達することなく訴えを却下することも可能となる[42][43]。
この法理が適用されない場合
最高裁判所 令和3年4月16日 第2小法廷
判決(令和2年(受)第645号)は、次の事例において、この法理の適用を否定した: Aの共同相続人XとYとの間で,Xが提起した遺産の一部に関する前件訴訟において,Xが自己に遺産全部を相続させる旨のAの遺言の存在を主張したにもかかわらず時機に後れた攻撃防御方法であるとして却下され,Yが相続分を有することを前提とする判決が確定した後で,XがYを被告にして,前記遺言の有効確認を求める本件訴えを提起することが信義則に反するとはいえないとされた事例。その理由として、次のことを指摘した(前件訴訟については本訴のみを取り上げる)。
攻撃防御方法のレベルへの拡張
この法理は、攻撃防御方法の提出の段階でも認められるべきである。例えば、同一の生活事実関係から不法行為による損害賠償請求権と不当利得返還請求権が発生する場合に、Xが不法行為による損害賠償請求の訴えをYに対して提起し、請求棄却判決を受けた後に、Yからの貸金返還請求訴訟において、不当利得返還請求権を反対債権にして相殺を主張することは、それが実質的に見て紛争の蒸返しと評価されるときには、そのようなものとして許されない(その防御方法は却下される)。
| この講義では「即時確定の利益」を「確認の利益」の構成要素の一つと位置付ける。しかし、前者は後者とほとんど同じ意味で用いられることもある。 |
確認訴訟の対象となり得る事項は広範囲であるため、訴えの利益は特にここで問題となる[6]。
確認の訴えの利益(確認の利益)は、(1)原告の権利又は法的地位について不安・危険が現存し、 (2)その除去のために一定の法律関係の存否を被告との間で判決により確定することが必要かつ適切であり、かつ、
(3) 確認訴訟が最も適切な訴訟形式である場合に認められる([兼子*体系v3]156頁参照。なお、上記(3)は省略されることもあるが、この講義では、次の分説との対応関係をとるために付加した)。
確認の利益は、通常、3つに分けて説明される(福永有利[中野=松浦=鈴木*新民訴v2.1] 138頁以下)
(a)即時確定の利益(即時確定の必要性) 確認判決により解消するに値する原告の権利・法的地位の不安・危険が現存すること。次の場合がその代表例である。
判決により守られるべき原告の法的地位が浮動的あるいは小さなものである場合には、即時確定の利益は認められない。例えば、遺言者は既にした遺言をいつでも取り消すことができ(民1022条)、受遺者とされた者は将来遺言が効力を生じたときに遺贈の目的物である権利を取得することができる事実上の期待を有する地位にあるにすぎないから、遺贈を受ける地位は、遺言者の生存中は、確認の訴えの対象となる権利又は法律関係には該当しない(最判 昭和31.10.4 ・民集10-10-1229)[37][33]。
(b)確認対象と被告の適切性 原告の権利や法的地位について生じた危険や不安を除去する方法として原告・被告間で原告が提示する請求(確認請求)について判決することが有効・適切であること[72]。そのためには、確認対象は、現在の紛争の解決あるいは当事者の法的地位の安定に役立つ具体的な法律関係でなければならない。この要件は、
(c)訴訟形式の適切性 確認訴訟以上に有効・適切な紛争解決手段がないことが必要である。確認判決には既判力しかないので、それだけでは原告の権利の最終的な保護にならないことがある。給付の訴えあるいは形成の訴えの方が適切な場合には、確認の訴えは許されない(確認の訴えの補充性)。たとえば、債務者が債権の存在を争っている場合には、原告は可能な限り給付の訴えを提起すべきである(履行期が未到来の場合には、将来給付の訴え)。確認の訴えでは強制執行ができず、原告が次に給付の訴えを提起することは、裁判所の負担となるからである[56]。給付されるべき金額が将来の事実に依存する場合には、給付の訴えは適当ではなく、確認の訴えが許される。最判平成11.1.21第1小法廷判決(平成7年(オ)第1445号)は、賃貸人の地位を承継した者が敷金交付の事実を否認して返還請求権を争っているが、敷金返還債務が確認されるのであれば、停止条件成就時に任意に履行する態度を示している場合につき、敷金返還請求権(賃貸借契約が終了して賃借人が建物を明け渡した後で金額が確定する停止条件付債権)を原告が被告に対して現在有していることの確認請求の訴えを現在の法律関係について確認の訴えとして適法とした。もっとも、敷金返還債務が確認されれば任意に履行する態度を被告が示していなくても、権利関係が早期に明確になることについて原告が相応の利益を有する場合、例えば、時の経過の中で生ずる証拠散逸の不利益を回避すること、あるいは権利関係が明確になることにより行動予定が立てやすくなることについて相応の利益を有する場合には、確認の利益を肯定してよいであろう。
過去の法律関係・現在の法律関係・将来の法律関係
この3つは、一定の法律関係の存在確認について言えば、次のように区別される。
将来の法律関係を現在の資料に基づいて判断しても、それは不完全な判断であり、その後に重要な事情変更が生ずれば、その事情変更を考慮して判断を修正することを認めざるをえない(口頭弁論終結後の新たな事実は、既判力によって遮断されない)。したがって、将来の法律関係についての判決の紛争解決機能は限られたものとなるが、それにもかかわらず現時点において判決をすることが必要な場合もある。将来の法律関係について判決することは、その場合にのみ許すべきである。そのような判決は、確認の訴えよりも、将来給付の訴えの形で求められることが多い。
法律行為の有効性の確認を求める訴えは、その法律行為がなされた時点以降の事情を考慮せずに判断する場合には、過去の法律関係についての判断となる。他方、その時点以降の事情を考慮して、現在有効であるか否かを問題にすることもできる。例えば、法律行為がなされた時点では有効であっても、その後にその法律行為が取り消されれば無効になるので、その法律行為が現在有効であるか否かを問題にすることができる。また、無効な法律行為がその後の事情の変化により有効になることは少ないので、過去の無効は現在の無効を意味するのが通常であるが、それでも追認により有効となることもある。したがって、過去の時点での無効と現在の時点での無効とを区別する実益がある。その点に注意するならば、過去になされた法律行為の現在における効力の確認は、現在の法律関係の確認ととらえるべきである。
訴えの利益 この訴えは、法律上の紛争の解決が証書の真否という事実の確定のみに依存する場合には、その証書が作成名義人とされている者の意思に基づいて作成されたか否かという事実を確定すれば、原告の法的地位が安定するとの理由により許されるものであるから、この理由が妥当する範囲でのみ確認の利益が認められる。証書の真否が確定されても、原告の権利または法律上の地位の危険・不安が除去されず、さらにその権利または法律上の地位自体の確認を求めなければならない場合には、証書真否確認の利益は認められない(福岡高判昭和48.3.29判時706-32)。例えば、借用証書に記載された債務について弁済が主張されているような場合がそうである。
法律関係確認訴訟との関係 証書により証明されるべき法律関係の存否を確認する判決の既判力は、証書の真否が理由中で判断されている場合でも、この点には及ばない。しかし、その確定判決がすでに存在する場合には、証書真否確認の訴えを提起する利益はない。訴えにより原告が得ようとしている利益が同じだからである。判決確定前でも、通常の確認訴訟が適法に提起されていれば、同様に、証書真否確認の訴えの利益は否定される。他方、貸金債権の担保として土地を売り渡す旨の証書が存在する場合に、債権者が貸金の返還を訴求したのに対し、債務者が売渡証書の成立の不真正の確認を求める利益は、肯定される(最判昭和41.9.22判時464-28[百選*1982a]45事件)。訴えにより各々が得ようとしている利益が異なるからである。
訴訟費用の負担の問題 弁済期が到来しているにもかかわらず債務者が弁済しないため給付の訴えを提起した場合には、被告が直ちに認諾しても、訴訟費用は被告に負担させるべきである(62条)[22]。事前に催告したにもかかわらず弁済がないため訴えを提起したところ、訴訟係属中に弁済がなされた場合にも、請求はもちろん棄却されるが、訴訟費用は被告に負担させてよい。他方、被告が争ってもいないのに、催告なしにいきなり訴えたところ被告が直ちに弁済をした場合には、請求は棄却され、訴訟費用は原告に負担させるべきである。
| Xは、Yに土地を3年間に限り資材置場として賃貸した。Xは、契約期間満了時にその土地に建物を建設する予定であった。賃貸してから1年後にYが契約の長期継続を求め、契約期間満了時に返還できないと言ってきた。Xは、契約期間満了前でもYに対して明渡しの訴えを提起することができるか(135条参照)。 |
履行すべき状態にまだなっていない給付義務を主張し、予めこれについて給付判決を得ておくことを目的とする訴えを将来給付の訴えという。現在給付の訴えの必要性は、被告が履行期にある義務を履行していないため、原告に権利保護を与える必要性があるということ自体によって根拠づけられる。これに対し、将来給付の訴えについては、そのような根拠付けはできず、予め判決を請求する(判決を得ておく)必要のあることが要件として追加される。
将来給付の訴えが許されるための要件は、次の2つのレベルに分けられる。
なお、将来給付の訴えにあたるか否かの判断の基準時は、口頭弁論終結時である。訴え提起の後、口頭弁論終結時までに履行すべき状態になったことを原告が主張すれば、その時点で現在給付の訴えとなり、裁判所はこれらの要件が充足されているかを判断する必要はなく、代わりに、履行すべき状態になったとの原告の主張の当否を判断する。
権利保護の利益のレベル−事前請求の必要性
最初に、すでに発生しているが履行期未到来の請求権を念頭において、事前の請求(判決取得)の必要性の要件を見ておくことにしよう。この要件を充足する場合は、2つの類型に分けられる。
(a)履行期における任意の履行を合理的に期待できない事情が存在する場合。
(b)一定の日時または期間内に履行がないと契約の目的を達することができない場合、あるいは原告に著しい損害が生ずる虞のある場合。この場合には、前記(a)の事情が存在する必要はない。債務者は、訴訟を回避したければ、執行証書等の債務名義となる文書を作成して、債権者に与えておくべきである。
請求適格のレベル−予測可能性
将来給付の訴えは、すでに発生している請求権のみならず、将来発生する請求権のためにも許される。口頭弁論終結後も土地の不法占拠が継続することにより生ずる損害賠償請求権が、その典型例である。しかし、判決において将来発生するであろうと認められた請求権が発生しないことになった場合には、その判決に基づく強制執行を阻止するために、債務者は請求異議の訴えを提起しなければならないという負担を負う。債務者が負うこの負担と債権者の予め判決を得ておく利益との適切な調節として、将来給付の訴えが許されるためには、訴求債権が次のいずれかに該当することが必要である。
肯定例 次のものは、将来給付の訴えの請求適格を有する[24]。
否定例 次のものは、将来給付の訴えの請求適格を有しないとされた。
継続的不法行為の成立要件の証明責任の転換
不法行為による損害賠償請求権の発生要件については、債権者である被害者が証明責任を負うのが原則である。このことは、ある時点Aから時点Bまでの継続的不法行為についても妥当し、債権者は、時点Aにおいて不法行為の成立要件が充足されることのみならず、時点Bまでその不法行為が継続していたことについて証明責任を負う。被害者が時点Aにおける不法行為の成立要件事実について証明すれば、その後の不法行為の継続が法律上推定され、その終了については加害者が証明責任を負うという原則が一般的に承認されているわけではない。もちろん、土地の不法占拠を理由とする損害賠償請求などにおいても、民法186条2項の適用は肯定してよく、したがって、土地所有者である原告が時点Aと時点Bにおける被告(不法占拠者と主張されている者)の占有を証明すれば、その間の被告による占有の継続は推定される。しかし、時点Aにおける被告の占有が証明されれば、時点Bにおける占有を証明しなくても、時点A以降の占有の継続が民法186条2項から推定されるというわけではない。
では、原告(被害者)は、口頭弁論終結時において不法行為が継続していることを基礎づける事実を証明している(あるいは被告が自白している)ことを前提にして、不法行為が口頭弁論終結後も継続することによる損害の賠償を命ずる判決(将来給付判決)が確定している場合は、どうであろうか[71]。
この点について、最高裁判所 昭和56年12月16日 大法廷 判決(昭和51年(オ)第395号)は、傍論ではあるが、次のように説示している。
この文言からすると、将来給付を命ずる判決により確定された請求権の継続的発生の終了について加害者が証明責任を負わせることが不当でないことを将来給付の訴えの請求適格の要件の一つとしており、したがって、その請求権の継続的発生を終了させる事実については加害者が証明責任を負うことになろう。
しかし、将来給付判決があることのみでそのような証明責任の転換を根拠づけることができるかは、疑問である。将来給付判決が確定している場合でも、請求異議等の訴えにより請求権の発生が争われた場合には、債権者がなお発生原因事実の継続について証明責任を負うものと解したい。
当事者の一方的な意思に基づく法律関係の変動が許される場合には、その変動は、通常、裁判外での形成権の行使に委ねられる。それに争いがある場合には、変動前の法律関係あるいは変動後の法律関係を前提とする確認の訴えあるいは給付の訴えにおいて、前提問題として判決理由中で判断され解決される。しかし、重要な法律関係(特に、多数の者が関係する法律関係)については、法律関係を明確にしておく必要があるので、法定の形成原因を裁判所が認定し、判決でもって新たな法律関係を宣言し、その判決が確定した時に法律関係が変動するとされる。それが形成訴訟である。そのため、形成の訴えは、法により認められた場合にのみ提起可能となる。
実体法上の法律関係の変動を目的とする形成の訴えの例として、次のものがある。
次の手続法上の訴えは、広い意味で形成の訴えに入れることができる(もっとも、請求異議の訴えなどについては、その法的性質について争いがある)。
形成の訴えは、それを許す規定がある場合に許され、所定の要件を満たす場合には訴えの利益が原則的に肯定される。したがって、形成訴訟にあっては訴えの利益が問題にされることは多くない。しかし、問題になる場合もある。例:
形式的形成訴訟の特色 筆界確定訴訟を例にすると、この訴訟には、次の特色がある。
共有物分割の訴えにも上記の特質のうちの 1,2,3 が当てはまる。
形式的形成訴訟も、それを許す法規範(実定法あるいは慣習法)がある場合にのみ許されるのが原則であり、所定の要件を満たす場合には訴えの利益が原則的に肯定される。したがって、形式的形成訴訟にあっても訴えの利益が問題にされることは少ない。しかし、筆界確定訴訟については、平成17年改正により不動産登記法147条・148条に筆界確定訴訟と筆界特定手続との関係を定める規定がおかれたものの十分とはいえず、問題が生じやすい。
意 義
筆界確定訴訟は、連続する土地を筆に分割し、筆を権利の対象とする制度の下で、その筆の範囲を確定するための訴訟である[75]。審理の結果既存の筆界線が明らかになればそれを明確にし、明らかにならなければ、合理的な筆界線を設定することにより筆界を確定することを目的とする訴訟である。筆界確定訴訟は、この意味で筆界形成の機能を含むので、形成訴訟の一種であり、かつ、形成要件が法定されていないために、形式的形成訴訟と呼ばれる。
このような意味での筆界確定訴訟の外に、土地所有権の範囲の確定の訴えも認められてよい。なぜなら、土地の取引は筆を単位にしてなされるのが基本であり、筆の一部を対象とする取引をする場合には、分筆の上で取引をすべきであるとはいえ、分筆前に筆の一部について取引がなされた場合に、その取引を無効とするわけにはいかず、筆の一部の所有権移転も認めざるを得ない;また、筆の一部の所有権の時効取得も認めざるを得ないからである。しかし、筆界の確定と土地の所有権の及ぶ範囲の確定とは明確に区別すべきである(筆界確定訴訟を土地所有権の範囲の確定の訴えとして理解する見解もあるが、賛成できない)。
民事訴訟としての筆界確定訴訟
筆界線は、私法上の権利の対象たる筆の範囲を定める線である。したがって、その確定を求める訴訟は、民事訴訟の一種であり、私人が当事者となる。ところが、しばしば、土地の範囲は課税および行政区画の基礎となることを理由に、筆界線は公法上のものであり、筆界確定訴訟は公法上の筆界線を定める訴えであるといわれる。しかし、この説明は適切でない。(α)この説明に対しては、私人が当事者となる民事訴訟においてなぜ公法上の筆界線を定めることができるのかという疑問が生ずる。(β)また、筆界確定訴訟で問題になるのは、所有者による分割あるいは合併が許される筆(公簿上特定の地番により表示される土地)であり、私権の対象たる筆を区切る筆界線である。課税対象となることを理由に、その対象物あるいは対象物の範囲たる筆界線の公法的性格を強調するのは適当ではない。類似の例を挙げて言えば、建物は、課税対象となり、また、建築基準法等の公法的規制に服するが、だからといって建物が公法的性質を有することを強調しても、あまり意味がないのと同様である[47]。(γ)「公法上の筆界線」という説明は、要するに、筆界線を隣接所有者の合意のみによっては変更できないという結論を導くための説明であろう。そして、この結論は、「筆界線は公法上のものである」という説明を用いなくても、「筆界線は、私権の対象たる土地の基本的単位としての筆の範囲を区切るものである」と把握しても可能である。
私権の対象たる土地の基本的単位としての筆
筆は、土地に関する権利関係の基本的単位である。権利関係を明確にし、取引の安全を図り、紛争を未然に防ぐために、筆に関する情報は登記所に備え置かれる地図により公示され(旧不動産登記法17条、現不動産登記法14条1項)、土地の分筆の登記に当たっては土地所在図・地積測量図の提出が義務づけられ(旧不動産登記法81条の2第2項、現不動産登記法18条柱書、不動産登記令3条13号・別表中8)、かつ、地図の現地復元能力を高めるために種々の方策が採られているのである[49]。このよう方法で厳格に管理され、また管理される必要のある一筆の土地の筆界線は、客観的存在と理解され、それを変更するためには、合筆・分筆の手続を経るべきものとされる。このことは、次の場合に、顕著に現れる。
客観的存在としての筆界
分筆の場合に典型的に現れるように、土地の筆界線は人間が定めるものである。しかし、一旦定められた筆界線は、一定の手続を経なければ変更することのできないものとすることが、法律関係の明確化・安定化のために必要である。この意味で、筆界線は、相隣者間の合意によっては変更できない客観的存在であると言われる。しかし、土地の筆界線が客観的な存在であるとはいえ、それが不明確になった場合に、その確定のために常に筆界確定訴訟が提起されなければならないというのは、行き過ぎである。筆界線をめぐる紛争の多くは、当事者間の協議で解決される[51][52]。協議が一旦成立した後で、紛争が再燃し、筆界確定訴訟が提起された場合に、その協議にどの程度の効力を持たせるかが問題となる。最高裁判所昭和42年12月26日第3小法廷判決(昭和41年(オ)第118号)は、相隣者間において筆界を定めた事実があっても、これによって、その一筆の土地の筆界自体は変動しないことを前提にして、相隣者間の合意の事実を筆界確定のための一資料にすることは差し支えないが、これのみにより筆界を確定することは許されないとした。一般論としてはこれを支持すべきであるとしても、当事者の合意は重要な資料というべきであり、筆界線が当事者間の合意により明確に確定され、その筆界線が登記所に備え置かれる地図に反映されているような場合であれば、当事者の合意は最大限尊重されるべきであろう。また、当事者の合意によっては筆界線は変動しないといっても、証拠調べの結果によっても客観的な筆界線が明らかにならない場合には、裁判所が合理的な筆界線を定めるにあたって、当事者の合意がなされた経緯を考慮しつつ、合理的になされた合意であると判断される限り、それを最大限尊重すべきである。
当事者適格
筆界確定訴訟は、私権の対象たる筆の範囲を確定する訴訟であるから、これについて当事者適格を有するのは、次の者である(最高裁判例は下記のaのみですべてを説明しているが、bを独立類型としてあげる方がわかりやすいであろう)。
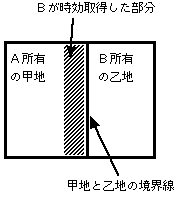 隣接する土地の所有者 所有者に限られ、地上権者等は当事者適格を有しない([下村*1995b]264頁以下に興味深い議論がある)。筆界確定訴訟が登記された一筆の土地の範囲を確定する訴訟であることを考慮すると、ここにいう所有者には所有権を他に移転したが登記簿上は所有者となっている者を含むと解すべきである([下村*1995b]264頁)。逆に、所有権を取得したが移転登記を得ていない者は含まれない。これは、新不動産登記法123条5号の「所有権登記名義人等」と基本的に一致する。しかし、訴訟では、登記名義人が偽造文書等により所有権移転登記を得た者であることが判明する場合もあり、その場合にはその者に当事者適格を認めるべきでない。
隣接する土地の所有者 所有者に限られ、地上権者等は当事者適格を有しない([下村*1995b]264頁以下に興味深い議論がある)。筆界確定訴訟が登記された一筆の土地の範囲を確定する訴訟であることを考慮すると、ここにいう所有者には所有権を他に移転したが登記簿上は所有者となっている者を含むと解すべきである([下村*1995b]264頁)。逆に、所有権を取得したが移転登記を得ていない者は含まれない。これは、新不動産登記法123条5号の「所有権登記名義人等」と基本的に一致する。しかし、訴訟では、登記名義人が偽造文書等により所有権移転登記を得た者であることが判明する場合もあり、その場合にはその者に当事者適格を認めるべきでない。 処分権主義との関係
筆界確定の訴えは、処分権主義との関係で特殊な扱いを受ける。
弁論主義との関係
筆界線については、筆界確定訴訟においても、また、筆界線を前提問題とする訴訟においても、弁論主義に服さないのが原則である。相手の主張する筆界線あるいは筆界線の確定の基礎となる事実を認める陳述をしても、時機に後れたものでない限り、自由に撤回できる。当事者の一致した陳述は、裁判所により重要な資料として尊重されるべきであるが、しかし、裁判所を拘束する効力はない。裁判所は、当事者が弁論において主張しない事実を筆界線確定の基礎とすることができる。ただし、その事実が重要な事実である場合には、当事者に意見陳述の機会を与えるべきである。筆界線を証明責任にしたがって定めることはできないので、客観的な筆界線あるいは合理的な筆界線が見いだされるまで証拠調べが必要となり、職権での証拠調べも許される。
判 決
筆界確定訴訟においては、裁判所は、かならず筆界線を明確に確定しなければならず、請求を棄却することは許されない。筆界確定判決が確定した場合には、その筆界線は旧不動産登記法17条、現14条の地図に迅速に反映されるべきである。したがって、判決確定後に裁判所が登記所に判決を送付する等の措置をとるべきである(判決内容の職権による事実的実現)。
土地の一部を指示して、その部分の所有権確認を請求する訴訟が提起され、それを認容または棄却する判決が確定している場合でも、その後に土地の筆界確定訴訟を提起することができ、前訴判決の既判力は後訴に及ばない。一筆の土地の範囲の問題と、土地の一部の所有権の帰属の問題とは、別個の問題と観念されるからである[48]。
筆界線は、訴訟当事者のみならず第三者との関係で統一的に確定される必要がある。したがって、筆界確定判決に対世的効力が認められる(人訴法24条1項の判決効拡張と同じである)。