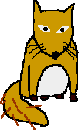
民事執行法概説
民事執行の概略
栗田 隆
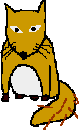
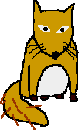 |
[←| 目次|文献略語 |→]
民事執行法概説民事執行の概略関西大学法学部教授 栗田 隆 |
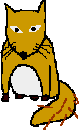 |
人間は、一人では非力なものである。いかに卓越した人間でも、離れ小島での独り暮らしにより得られる物質的豊かさは、限られている。人間は、他人と協力することにより生活の安定と経済的豊かさを得ることができる。人と人との協力において最も重要なものは、相互の信頼である。
経済取引における信頼は、信用と呼ばれる。特に金銭を貸与するときの信用が重要であり、債権者が債務者に融資することを「信用を与える」とも言う。取引の際に相手が信頼できるかを調査すべきであるとは言え、それにはおのずと限度がある。何らかの事情で相手が契約を履行しなくなったときに契約履行を強制する手段のない場合より、強制手段のある場合の方が相手を信用しやすい。法的な義務の強制手段は、民事執行法に規定されている。民事執行法は、信用秩序の基盤の一つである。
もちろん、権利の実現の基本は、相手に任意の履行を求めることである。その履行請求も、背後に執行制度が控えているから成果があがるのである。債権回収業務は、必要に応じて民事執行制度を利用することにより、一層効率的になる(生産性が高まる)[R8]。
なお、私人の権利の実現を国家が支援する方法は、執行という方法に限られない。人事訴訟法では、扶養料や財産分与の給付を命ずる裁判について「履行の確保」という支援制度を設けており(人訴38条以下)、履行命令に従わない場合には、過料を課すという強制制度も用意されている(人訴39条4項)。
4つの形態
民事執行法では、義務者あるいは財産所有者の意思を抑圧して権利の強制的実現を図るための手続として、次の2つが規定されている。
そのほかに、私法の領域では、共有物の分割の場合のように、物を公正な価格で売却することが要請されることがある。この競売は、金銭債権の強制的実現のためのものではないが、民事執行法所定の売却手続はこの要請にも応えることができる。そこで、この要請に応えるために、次の手続が規定され、これも民事執行の一つの形態と位置づけられている(法1条)。
また、金銭債権の実現のための強制執行を実効性の高いものにするためには、その満足に充てられるべき財産(責任財産)の発見が必要である。それは、従来執行債権者が自己の負担でなすべきものとされていたが、実際上さまざまな困難があったので、平成15年改正及び令和1年改正で、責任財産の発見を支援するために、次の手続が用意された。
執行機関(2条・167条の2)
上記の各種類の民事執行について、それを担当する国家機関あるいは執行処分を行う国家機関を執行機関という(前者は2条に、後者は3条に即した表現である)。これには、次の3つがあり、それぞれ法令で定められた種類の執行について、債権者からの申立てを受けて実施する(2条・167条の2第1項)。
執行裁判所
民事執行は、国民の一人である債務者の生活領域への侵害を伴うので、法律の定めるところに従って適正に行われなければならない。そのため、裁判所が執行機関となる執行以外についても、裁判所の関与が必要となる。そこで、民事執行法は、執行裁判所の概念を設け、これにさまざな役割を与えている。その主要な役割は、次のことである:(α)裁判所が執行機関として定められている執行について、みずから執行機関として執行処分を行うこと;(β)執行官・裁判所書記官が執行機関である執行について、執行官・裁判所書記官を監督し、それらの者がする執行処分あるいはその遅怠に対する執行異議について裁判すること(3条・11条1項、167条の3・167条の4第2項等)。「執行裁判所」は、この2つの役割を含んだ概念であるが、裁判所が一方の役割を果たすだけの場合でも、執行裁判所と呼ばれる(例えば44条)。
執行裁判所の語は、官署としての裁判所の意味でも(44条・90条2項・167条の3など)、事件を担当する特定の裁判官から構成される執行機関あるいは裁判機関の意味でも使われる(4条・5条・11条など)。もっとも、民事執行事件については口頭弁論を経ることは必要的ではなく(民執法4条)、執行機関あるいは裁判機関を構成する裁判官が交替しても、おおむね新裁判官が事件記録を閲読することで足り、弁論の更新(民訴249条2項・3項)は必要ない(もちろん、記録の閲読だけでは不十分であるならば、新裁判官は利害関係人や参考人を審尋する(5条))。そのため、両者の区別にあまり神経質になる必要はない[4]。
執行共助機関
不動産の強制競売の手続などは、権利関係が不動産登記簿に公示されている関係で、デスクワーク中心に進めることができ、裁判所が執行機関(執行を主宰する機関)となるが、デスクワークだけで全てを処理することができるわけではない。財産の所在する現場に赴く必要がある事項もいくつかある。例えば、不動産の現在の状況を調査する現況調査(57条)がそうであり、これについては執行官に協力(共助)を求めることになる。この場合の執行官の位置付けは、執行機関としての裁判所を共助する機関(共助機関)である。不動産の売却の実施も同様に執行官が行う[6]。また、不動産の評価は、不動産の評価について専門的知識を有する者(通常は不動産鑑定士)に評価を依頼することになる。
一つの手続の分担(執行官から裁判所への連係)
一つの執行については、一つの執行機関が手続の最初から最後までを担当(主宰)するのが通常であるが、最初は執行官が担当し、次に裁判所が担当する場合もある。例えば、動産執行については、債権者の申立てを受けて差押え・換価までは執行官が担当するが、換価金を債権者に与える段階については、執行官が担当するとは限らない。(α)複数の債権者に売得金を配当する必要がある場合に、債権者間で配当について協議が成立しないときは、配当をめぐる争いを適正に解決するために、裁判所が配当を実施し、(β)それ以外の場合には執行官が配当等を行うものとされている(139条・142条)。(α)の場合には、執行官が手続の前半を担当し、執行裁判所が後半を担当するという連係プレーになる。
手続の分離
不動産の競売では、執行機関である裁判所が売却不動産の引渡しまで行うのが本来であるが、前述の裁判所の特質をも考慮すると、不動産の引渡しは、競売手続の外に置く方が手続の整理がしやすい。そこで、不動産の引渡しのための強制執行に必要な引渡命令を発するところまでを競売手続に取り込み、その引渡命令に基づく明渡執行の手続は、競売手続から分離されており、後者の執行機関は執行官である(所有権移転登記は、競売手続内で裁判所書記官による嘱託の方法で行われる(82条1項))。
執行官制度
執行官の組織上の地位は、長い歴史の中でさまざまな制度改革を経て、現在では、手数料を主たる収入源とする公務員という地位に落ち着いている。しかし、国際的に見れば、執行官またはこれに相当する執行担当者の組織上の地位は、様々である。ドイツでは、執行官の権限を民間人に与え、民間人が公的な監督の下でこれを行使するという改革モデル(「権限委任」型の改革モデル)の実現が試みられているとのことである([柳沢*2008a]等参照[CL1])。
民事執行の刑法的保護
執行の現場は、債権者と債務者の利害が激しく対立する修羅場である。少なからぬ債務者が、手段を選ばずに執行による苦痛から逃れようとする。極端な例をあげれば、競売により売却された建物の明渡強制執行の際には、債務者が白刃を振りかざして、執行官に同行してきた債権者に襲いかかったり、絶望した債務者が建物に灯油をまいて焼身自殺を図ることもある。巧妙な債務者は、暴力団と結託して競売を妨害したり、場合によれば、暴力団員が債務者に少額の金銭を渡して建物を賃借した外観を整えて、債権者に高額の立退料を要求したり、買い手が付かないようにして仲間が安価で買い受けることができるようにすることもある。
こうしたことを防ぐために、民事執行法は、債権者に様々な法的手段を用意しているが、しかし、それだけでは十分とは言えない。信用秩序の法的基盤である民事執行制度の機能を維持するためには、刑罰法規による保護も欠くことができない。民事執行法204条以下の規定の外に、刑法にも民事執行の保護に資する規定が多数ある。主だった規定として、次のものがある。なお、刑法96条の2以下にいう「強制執行」には,民事執行法1条所定の「担保権の実行としての競売」が含まれる(平成23年改正前の刑法96条の2についての先例であるが、最高裁判所 平成2年7月14日 第1小法廷 判決(平成19年(あ)第2355号)参照)。
執行により実現されるべき権利を執行債権あるいは請求債権という。強制執行の概略は、執行債権と、その実現のために用いられる執行方法の2つの要素で説明することができる(民執法第2章第2節以下では、「・・・権についての強制執行」との見出しの下で、執行債権の種類ごとにその実現に用いられるべき執行方法を規定している)。執行方法は、権利の実現行為をする者が誰であるかにより、次のように分類される。
金銭執行
金銭債権の実現のための執行(広義の金銭執行) には、直接強制のほかに間接強制の方法も認められている。一般的・基本的な執行方法は、前者であり、財産の差押え・換価・配当の3段階を追って行われる。これを狭義の金銭執行と呼ぶことにしよう(財産換価の方法により行われる点にちなんで「財産換価執行」と呼ぶこともできる)。これは、売却される財産の種類(不動産、船舶、動産、債権など)に応じて手続が細分されている。間接強制は、限られた範囲の金銭債権の実現のためにのみ認められている。
金銭執行の場合には、対象財産の種類による細分化はあるものの、その細分化を度外視すれば、執行債権と執行方法との間におおむね1対1の対応関係がある(扶養義務等に係る金銭債権については、執行方法は2つある(間接強制も認められている))。
非金銭執行
金銭債権以外の債権(請求権)の実現のための強制執行は、非金銭執行と一括されるが、これは更に次のように細分される:
非金銭執行にあっては、執行債権が多様であるのに応じて、複数の執行方法が用意されている。しかも、適用範囲が複数の種類の権利にまたがる執行方法もある。一つの権利の執行方法が一つであるとは限らず、複数の方法が利用可能な場合がある。民事執行法が非金銭債権のために用意している執行方法は、次のとおりである。
離婚判決は、その確定により離婚(夫婦関係の消滅)という法律効果が生ずる形成判決である。離婚判決を提出してする離婚の届出は、報告的届出に過ぎない。しかし、この届出をすることにより初めて戸籍が改められるのであり、離婚判決によって生ずべき法律状態はこの戸籍の改編まで進まないと実現されない。しかし、そこには、民事執行法所定の執行機関が関与する執行手続はない。このように、判決によって実現されるべき法律状態が執行手続によらずに実現される場合に、それを広義の執行という(この言葉の定義上「広義の執行」は「狭義の執行」を含まず、両者は排斥関係にある。ただし、前者が後者を包摂するように定義する立場もある)。
「広義の執行」の一種としての意思表示の擬制
土地の売主に対して、買主への所有権移転登記手続に協力することを命ずる判決は、共同申請主義(不登法60条)の下で、登記義務者としてなすべき申請の意思表示をせよという内容の給付判決である(これが、民事執行法の立場からの理解である。金銭の給付と登記申請との引換給付を命ずる判決については、、民執法177条1項ただし書・2項を適用する必要があるので、そのように理解するのが正しい。しかし、民法の研究者の中には、不登法63条1項が判決による単独申請を認めているから、登記義務者の登記申請の意思表示は必要なく、したがって、登記手続を命ずる判決は意思表示(登記申請)を命ずるものではないとの理解を示す者もある)。
登記申請を命ずる判決を代表とする意思表示を命ずる判決等については、命じられた意思表示を債務者に実際にさせるのは迂遠であり、当該判決の確定あるいは裁判上の和解等の債務名義が成立したときに、その意思表示があったものと擬制し、権利者がその判決等を意思表示の名宛人に提出することにより意思表示が到達したとする方が簡明である。意思表示を命ずる判決の執行は、このように意思表示の擬制によりなされる(民執法177条1項本文)。ただし、債務者の意思表示が債権者の証明すべき事実の到来にかかるとき(例えば、代金の支払と引換に登記申請をすべきとき)、あるいは、債務者の証明すべき事実が存在しないことにかかるとき(例えば、≪債務の弁済を一回でも怠れば債務者所有の不動産の所有権が債権者に移転する≫旨の合意に基づき所有権移転登記の申請をすべきとき)には、執行文の付与の時に意思表示が擬制される。
いずれにせよ、意思表示の擬制は、執行機関の関与を必要としない(執行文の付与は、民事執行法に規定されているが、債務名義作成機関がなすべき行為であり、執行手続の一部ではない)。したがって執行機関が関与する執行手続を経ることなく債務名義で命じられた法律状態が実現されるので、この執行は、「広義の執行」に分類される。
執行債権と執行方法との対応
執行債権と執行方法との一応の対応関係を示せば、次の表のようになる(この表において、ある種類の執行債権について複数の執行方法があるとされている場合でも、執行方法に課せられた要件により、一つの執行方法しか選択できない場合もある)。
|
執 行 債 権 |
|||||||||
| 金銭債権 | 物の引渡・明渡請求権 | その他の代替的作為請求権 | 不代替的作為請求権 | 不作為請求権 | 子の引渡請求権 | 意思表示請求権 | |||
|
執 |
直接強制 | 金銭執行(財産換価執行) |
○ |
||||||
| 物の引渡・明渡執行 |
○ |
||||||||
| 引渡請求権の差押え |
○ |
||||||||
| 代替執行 | ○ |
○ |
|
||||||
| 監護解除による引渡執行(注1) |
○
|
||||||||
| 間接強制 | ○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
(肯定説もある) | ||
| 意思表示の擬制 | ○ |
||||||||
(注1)監護解除による引渡しは、裁判所の決定により行う執行官が実施する(174条1項1号・4項。執行機関は裁判所である)。この執行は、裁判所の決定に基づて実施される点で代替執行に近似する(ハーグ条約実施法では、子を返還先国まで連れて行く必要があるので、代替執行と位置づけられている(134条1項)。授権決定においては、監護を解除する者として執行官を指定するとともに、子を外国に連れて行く者(返還実施者)も指定する(137条))。他方、執行官が監護解除を直接実施する点で直接強制の一種である物の引渡執行にも類似する(執行官法1条のいずれの号の職務かと問われれば、1号の職務と答えるべきであろう。閉鎖された扉の解錠について専門技術者を用いることあるいは児童福祉や児童心理の専門家の補助をえることはあるにせよ、監護解除それ自体について第三者にさせる(建物収去執行の場合のように解体業者に請け負わせる)余地はない。また、執行官による監護解除については、債権者(例外的にその代理人)が解除場所に出頭することが必要なので、監護解除(又は監護解除に接続して債権者が子を引き取ること)により執行は終了すると考えられる)。このように、監護解除による子の引渡執行をいずれかの類型(代替執行又は直接執行)に含めることもできないわけではない(裁判所の決定により子の引渡執行の手続が開始されるという意味では裁判所が執行機関であることに争いはないが、文献では「直接的な強制執行」という表現がよく用いられている)。ここでは独立の類型とした。
以下では、不動産に対する金銭執行(そのうちでも、強制競売)を例にして、強制執行の概略を述べることにしよう(法45条 以下)。
強制執行は、権利者の義務者に対する一定の行為を求める請求権(執行債権)の強制的実現行為であり、国家の執行機関が行なう場合でも、私人の生活領域への侵害行為であることに変わりはない。その侵害行為を正当化するのは、執行債権の存在である。
権利確認手続と執行手続との分離
しかし、執行債権の存在そのものを執行の基礎とすると、(α)執行機関はその確認にエネルギーをとられ、また、
(β) 執行機関に配置できる人材が限定されることになる。さらに、(γ)裁判所が執行機関となる場合でも、金銭執行にあっては執行対象財産の所在地を管轄する裁判所が執行機関になることを前提にすると、一つの金銭債権の満足のために複数の執行機関が執行手続を行うことになるので、執行手続と権利確認手続とを分離しないと、権利確認の重複の無駄が生ずる。
手続間の架橋としての債務名義
そこで、両手続を分離して、権利確認手続において作成される債務名義(権利の存在を公証した格式のある一定範囲の文書)により強制執行を行うものとされた。債務名義となりうる文書は、法22条 に列挙されている。代表例は確定判決である。
債務名義とは、執行債権(強制執行により実現されるべき請求権)の存在・内容を公証した一定の(民執法22条に列挙された)格式のある文書である。 この定義において「格式」の語は省略可能であるが、「債務名義となる文書は強制執行の根拠となるにふさわしい格式のある文書であるべきだ」との考えを込めて、用いた。
執行力
「≪債務名義を提出して執行を申し立てれば、債務名義に表示された権利の実現のための強制執行を開始してもらうことができる≫という債務名義に認められた効力」を執行力という[7][5]。債務名義に執行力があるか否かの判断は、債務名義となる文書をみればすぐにわかるというわけではない。例えば、給付を命ずる第一審判決は、確定すれば債務名義となり執行力を有するが、確定しているか否かは判決の正本自体からは明かにならない。そこで、執行力の存在は、債務名義作成機関が債務名義の正本の末尾に執行文を付記する方法により公証するものとされ、強制執行は、原則として執行文の付された債務名義の正本に基づき行われるものとされた(法25条 。例外がある)。執行文は、執行力の本質を的確に言い表した次のような文言である(法26条 2項)。
「債権者〇〇〇は、債務者〇〇〇に対してこの債務名義に基づき強制執行をすることができる」法25条により執行の基礎となる文書を「執行力のある債務名義の正本」(法51条 )、略して「執行正本」という。
給付判決確定後に債務者が債務を任意に弁済したにもかかわらず、債権者が強制執行を申し立てることもある。その執行は、既に存在しなくなった債権についての執行であり、不当な執行であるが、執行機関としては、執行正本が提出されれば、執行を開始せざるをえない。執行文付与手続は、判決の確定等の形式的事項を文書に基づいて調査するに過ぎず、弁済の有無のような問題を審査するようには作られていない。こうした問題は、執行手続とは別個の通常の訴訟手続(判決手続)により審査すべきものとされている。
その訴訟では執行債権が現存するか否かが審理判断の中心となるが、ただ、すでに債務名義が存在しているので、その訴えは、債務名義の執行力の排除を求める訴えとなり、請求異議の訴え(法35条 )と呼ばれる。
執行債権が存在しないにもかかわらず、債務名義を悪用して強制執行がなされた場合には、債務者は、執行により奪われた利益を不当利得として返還請求することができる。
金銭債権や物の引渡請求権については、債権の満足に供せられるべき財産は何かを問題にすることができ、そのような財産を責任財産という(なお、「責任財産」の語は、狭義では、金銭債権の満足に充てられるべき財産の意味で使われる[2])。金銭債権については、債務者の執行開始時における全財産が責任財産となるが、ただ、債務者といえども社会の一員であり、それにふさわしい生活を営む権利は保障されなければならず、一定範囲の動産や債権が執行対象から除外される。すなわち、差押禁止財産となる(法131条 ・152条 )。住宅を含めて不動産は、差押禁止財産にはならない(例外として、宗教法人法第83条がある)。
差押えは、債務者の責任財産に対してのみなされるべきであるが、執行機関がその点の判断を正確になすことには限界がある。そこで、債務者名義の不動産、債務者の支配する場所にある動産は、債務者の責任財産である蓋然性が高いので、そのようなものとして差押えが許される。第三者の不動産であっても、債務者名義で登記されていれば、その差押えは適法である(国に損害賠償義務は生じない)。しかし、第三者は、その不動産は執行債権の満足に供せられるべき財産ではなく、その執行により自分の利益が害されることを主張して、執行の排除を求めることができる(第三者異議の訴え。法38条 )。逆に、第三者の登記名義となっている不動産は、たとえ債務者の財産であっても、債権者代位権(民423条)や債権者取消権(民424条)を行使して、債務者名義の不動産にしなければ、差し押さえることができない。
現行法では、債務者の責任財産を探索するのは、債権者の役割とされている。金銭債権者は債務者の財産またはその所在場所を見つけだして、金銭執行の申立てをしなければならない強制執行の対象となる責任財産の発見を支援するために、平成15年改正により、債務者自身に財産を開示させる制度(財産開示手続。第4章・196条以下)が用意され[1]、さらに令和 1年改正により、第三者から債務者の財産に関する情報を取得する制度(第三者からの情報取得手続。204条以下)が追加された。
金銭執行は、執行対象財産の権利関係を固定し(差押え)、その財産を金銭に換え(換価)、その金銭を債権者に分配する(配当)という3つの段階に区切ることができる。
差押え
執行対象の固定のために、差押えという特別の措置がなされる(法45条以下)。不動産の差押えは、債務者の処分を禁止する効力を有するが、債務者は所有者として目的物を使用することができる(法59条 2項・46条 2項)。しかし、差押えを受けた債務者は、不動産の価値維持に熱意を失い、例えば、建物を空き家のまま放置したり、雪国において雪下ろしをしないでいることがある。場合によると建物を取り壊そうとする。のみならず、暴力団員等が、不正な利益を求めて差押不動産に入り込み、売却されても簡単には出て行かない態度を示すことにより、他の買受希望者を排除し、あるいは、立退料を得ようとする(占有屋)。こうした不当な行為により不動産の価額が減少することを放置していたのでは、執行債権の実現は図れず、ひいては信用秩序が維持されない。とりわけ暴力団員等による不正な利益の獲得は、勤勉に働く者が報われるべきであるとの社会原則を掘り崩すものであり、容認することはできない[3]。こうした事態に対して差押債権者は、執行手続内の保全処分として、債務者または占有者による価格減少行為の禁止や、差押不動産の執行官保管などを申し立てることができる(売却前の保全処分。法55条 )。占有屋に対して建物からの退去を命ずることも実際に行なわれている。
換価
不動産の売却の準備として、執行官による現況調査と評価人(通常は不動産鑑定士)による評価がおこなわれる(法57条 以下)。裁判所は評価人による評価を基に売却基準価額を決定し(法60条 以下)、また、物件明細書を作成して(法62条 )、買受希望者にどのような不動産が売却されるかを明らかにする。売却は、通常、一定期間内に入札書を提出すればよいという期間入札の方法で行なわれ、執行官が実施する(法64条 )。有効な買受申出のうちで最も高い価額で申し出た者を執行官が最高価買受申出人に指定し、執行裁判所がその者に売却するか否かを決定する(法69条 )。売却許可決定が確定して、代金が支払われると、所有権は買受人に移転し(法79条 )、所有権移転登記がなされ、売却により消滅する物上負担(抵当権など)の登記そして差押えの登記の抹消登記がなされる(法82条 )。売却不動産上の負担のうち、担保権は消滅するのが原則である(法59条 1項。消除主義。例外は、通常の質権、留置権)。用益権については消除主義の原則をとることはできないが、売却により消滅する担保権よりも後順位の用益権は、もし存続するとなると担保権者の利益を害することになりやすいので、物権の順位の原則により一律に消滅するものとされている(法59条 2項)。差押え後に設定された負担は、執行手続との関係では無効なものとして扱われ、買受人に引き受けられることもない。債務者が売却不動産を任意に明け渡さない場合には、信用秩序の基盤としての執行制度の機能を維持するために、通常訴訟によることなく引渡命令という簡易な手続で明渡しを得ることが買受人に認められている。引渡命令の相手方は、事件の記録上買受人に対抗することのできる権原を有していると認められる者を除くその他の占有者にも拡張されている(法83条)。
配当
買受人の支払った代金からまず手続費用が支払われ、残りが登記されている担保権者および手続に参加した債権者に分配される。分配を受ける債権者が一人だけの場合およびすべての債権者が全額の満足を受けることができる場合には、債権者間で売却代金を取り合う関係は生じないので、簡易な手続で分配がなされる(法84条 2項。弁済金交付)。その他の場合には、慎重な手続で分配がなされる。すなわち、実体法の定める順位に従って分配をなすために配当表が作成され、配当表に異議のある債権者には配当異議の訴えを提起して自己への分配を増加させる機会が与えられる(法84条1項・85条以下。配当)。両者をあわせて、「配当等」と言うこともある。
抵当権等の担保権には、伝統的に、次の2つの権能が認められている(留置権には優先弁済を受ける権能はなく、留置権に基づく競売は法195条 による換価のための競売である)。
日本の不動産価格は、第二次大戦の敗戦のどん底から立ち直る経過の中で、一貫して上昇傾向を保っていた。しかし、1990年をピークとするいわゆるバブル経済の崩壊を契機にして、日本の不動産価格は、一転して、下落傾向に陥った。その原因は、(α)単なる不動産バブルの崩壊だけではない。 (β)平和の回復の中で多数生まれたいわゆる団塊世代の住宅取得の終了と後続世代の人口減少による住宅需要の減退、及び、 (γ)日本の実質賃金よりも遙かに安い賃金で良質な労働力を提供することができるようになったアジア諸国へ工場が移転することにより、日本の土地に対する需要が減退しているという、構造的要因もあった(もちろん、一般物価が上昇すれば、それに伴い不動産価格も上昇しようが、しかし、2010年の時点において、不動産価格が一般物価以上に下落した現状をみると、不動産価格が一般物価以上に上昇する時代が到来するのは、先のことと思われる)。
不動産バブルがピークを過ぎ、担保不動産の価格が継続的に低下していく状況の中で、少なからぬ抵当権者は、過去の経験に照らせば不動産市況は間もなく回復するであろうと期待した。彼らは、法定果実を生み出す不動産については、競売をためらい、賃料債権に対する物上代位を試みた。抵当権に基づく賃料債権への物上代位が許されるかについては見解の対立があったが、最高裁判所 平成1年10月27日 第2小法廷 判決(昭和60年(オ)第1270号)は、これを肯定した。これにより担保権に基づく収益執行の道が実質的に開かれたのであるが、賃料債権に対する物上代位という方法には、さまざまな問題があった。例えば、抵当権者が抵当不動産所有者から賃料を根こそぎ取り上げることができるため、目的不動産の維持管理が困難となる;賃借人が多数いる場合には、各賃借人ごとに物上代位権を行使しなければならず、賃借人が交代する場合も、改めて物上代位のための差押えを申し立てなければならない。
こうした問題を克服しつつ抵当権者に法定果実からの満足を可能にするために、平成15年の改正により、民事執行法に抵当権に基づく収益執行が規定されるようになった。その前提として、民法で次のことが規定された。
民法371条の規定は、不動産の先取特権に準用され(民341条)、また、使用収益しない旨の定めのある質権にも準用される(民361条)。以下では、これらの担保権について説明する。担保権に基づく強制換価も、所有者の生活領域への侵害を伴うので、民事執行法の規定に従い国家の執行機関が行なうものとされ、「担保権の実行」あるいは「担保執行」と呼ばれる。
上記のように、不動産の担保権には、目的不動産自体を換価する権能と果実を換価する権能とが含まれる。前者を競売権、後者を収益執行権と呼ぶことにしよう。不動産担保権の実行方法は、これらの実体権にあわせて、次の2つに分かれる。
強制執行の正当性の根拠(実体的根拠)が執行債権の存在であるのと同様に、担保執行のそれは担保権の存在である。その問題と手続的根拠・手続的適法性の問題とは区別される。強制執行において手続的根拠が債務名義とされたのと同様に、担保執行についても担保権の存在を公証する格式文書を手続的根拠とすることも考えられたが、その考えは取引費用の増加を招くとの理由で採用されず、担保権そのものが手続的根拠とされた。ただ、買受人が代金を支払ってから担保権の不存在が判明した場合に、競売の根拠が担保権であるとの論理を貫徹すれば、買受人の所有権取得が否定されることになる。しかし、それでは競売手続の信用は害され、競売手続に参加する者は、一定割合で生ずるその危険を吸収することができる程度に多数回競売不動産を買い受ける専門業者のみとなる。それでは売却価額が著しく低下する。それを避けるために、民事執行法は次のように規定した。
55条等を見ながら、こうした事項の配列の順序にある程度の規則性があることを確認しておくと、条文を読むのが楽になる。なお、上記1・2・3の順序は条文により異なり、固定しているわけではない。4以降は、概ねこの順序で項が立てられている。
執筆の準備のメモ