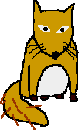
民事執行法概説
非金銭執行
栗田 隆
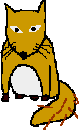
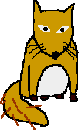 |
民事執行法概説非金銭執行関西大学法学部名誉教授
栗田 隆 |
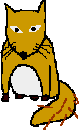 |
非金銭執行に関する 文献 判例
上記2の場合で即日売却・近接日売却が許されない動産又は許されない場合については、動産執行の例により売却する。売却の公告が必要である(規則115条・120条3項)。規則114条では、競り売り期日は「やむを得ない事由がある場合を除き、差押えの日から1週間以上1月以内の日」とされているが、そこにいう「差押えの日」は「明渡し執行の断行日」と読み替えられる。
売却できない場合はどうするのか
目的外動産(以下では混乱を避けるために「残置動産」という)は、多くの場合に、執行債権者が最後の買受人となるが、彼は買い受ける義務を負うわけではない。実際、処理に特別の技術が必要な有害物質など、うかつに買い受けることはできない。そのため、執行官が売却を試みても売却できなかった残置動産はどうするのかという問題が生じ得る。この点について明文の規定があるとは言い難い。なるほど法168条6項は「執行官は、・・・これを保管しなければならない」と規定している。しかし、執行官が無期限に保管することが可能なわけではない;同項は、執行官が保管した動産を売却することができることを前提にした規定と解すべきである(同項2文はそれを前提にしているとみるべきである);換言すれば、同項にいう「保管」は「売却されるまでの一時的な保管」である。したがって、執行官が残置動産を保管した場合でも、動産を売却できないことが確定した時点で、残置動産の処理を含めて引渡執行の手続は完了し、残置動産の処理は執行債権者に委ねられると解さざるを得ない。その後、執行債権者は、売却できなかった残置動産を保管して、執行手続外で、引取義務を負う者(通常は所有者)に対して引取りを請求することができる。引取りを命ずる判決が確定した場合に、判決内容の直接的な実現は、残置動産を引取義務者の管理場所に搬入することになるが、それは動産の引渡し(債務者の占有する動産を取り上げて債権者に引き渡すこと)ではない。したがって、その執行方法は、代替執行又は間接強制の方法になる。
このことから、逆に、次のように言うことができる。(α)残置動産について即日売却を行わないため執行官がそれを一時保管する場合に、執行官自らが管理する場所で保管するのは、残置動産の売却が確実な場合に限るべきである。売却の見込みがない動産については、引渡執行の対象不動産上で保管すべきである(規則104条1項により執行債権者に保管させる)。この場合に、執行債権者の同意を得ることが望ましいことは言うまではないが、同意が得られなくても、そうすることができると解すべきである。(β)実際上は、執行官の管理場所で保管する場合に、保管料を執行費用の一部として執行債権者に予納させることになり、無期限の予納となれば相当な金額を予納させることになるので、執行債権者は、引き渡された不動産上で保管することに同意するであろう(この場合でも保管費用が生ずることはあり得るが、それは、執行債権者が執行債務者(正確には動産所有者)に執行手続外で請求することができる。この保管費用を執行債権者が執行費用の一部として予納するという問題は生じない)。
執行の終了時期
引渡し等の強制執行は、不動産に対する債務者の占有を解いて臨在する債権者の実力的支配に移した時に終了する。 ただし、目的外動産が存在する場合には、すべての目的外動産についてその処理(債務者等への引渡し、売却成功後の買受人への引渡又は売却不成功後の執行債権者への引渡し)が完了した時に終了する。
判 例
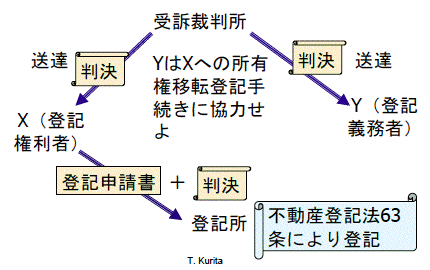 意思表示義務は、不代替的作為義務の一種であるが、債権者には意思表示の結果として生ずべき法律効果を与えれば足り、債務者に現実の表示行為の実施を強いるのは迂遠である。そこで、法は、意思表示を命ずる債務名義の発効時点又はその後の所定の時点で債務者がその意思表示をしたものと擬制する、という執行形態を定めた。
意思表示義務は、不代替的作為義務の一種であるが、債権者には意思表示の結果として生ずべき法律効果を与えれば足り、債務者に現実の表示行為の実施を強いるのは迂遠である。そこで、法は、意思表示を命ずる債務名義の発効時点又はその後の所定の時点で債務者がその意思表示をしたものと擬制する、という執行形態を定めた。