民事訴訟法を初めて学ぶ人との
ダイアローグ
関西大学法学部教授
栗田 隆
以下は、あるロースクールにおいて、2004年度秋学期の講義に参加してくれた学生諸君との授業時間内外における対話を再構成したものである。
民訴114条2項 − 訴求債権額よりも大きい反対債権による相殺が否定された場合
定期試験の答案用紙を回収した後で
- S: 原告の1000万円の支払請求に対して、被告が3000万円の反対債権の存在を主張して、訴訟上の相殺の抗弁を提出したところ、裁判所が「訴求債権は存在するが、反対債権は存在しない」と判断して、請求を全部認容した場合に、反対債権については、どのような判断に既判力が生ずるのでしょうか。
- T: 訴求債権と対当した1000万円部分についてのみ、その不存在の判断に既判力が生じます。
- S: 残部の2000万円部分も存在しないとの判断に拘束力を生じさせるべきであるとの見解もあるそうなんですが。。。
- T: そういう考えもあるでしょうね。明示の一部請求が棄却された場合には、残部も存在しないと判断されているので、別訴で残部を請求することは、信義則により許されないのでしたね。それと同様に、訴求債権よりも大きい金額の反対債権で相殺した場合に、既判力が生ずるのは訴求債権と対当する部分の不存在の判断に限られるが、残部については、信義則によりその存在を主張することが許されないことがあると考える方がよいでしょう。
- S: 残部については、既判力ではなく信義則により主張が禁じられると考えるのですね。
- T: そのとおり。
以下は、続きの想定問答
- T: たとえば、債権者が利息制限法違反の利率で貸付けをし、債務者が超過利息を任意に支払い、かつ元本も支払った結果、3000万円の過払いがあったとします。債権者が別口の債権1000万円の支払いを訴求したのに対し、債務者が3000万円の過払利息の不当利得返還請求権を主張して、対当額で相殺するとの抗弁を提出したとします。超過利息の元本充当を否定した昭和37年判決が妥当する時代にその抗弁を出すと、この判例理論にしたがって、相殺の抗弁に理由がないとされるでしょう。それから、6年後の昭和43年判決で過払利息の不当利得返還請求権が肯定されるようになりましたね。この判決を見た債務者が過払利息の不当利得返還返還請求の訴えを提起したとしましょう。債務者が主張した反対債権のうち、前訴の訴求債権と対当する1000万円部分については、どうなりますか。
- S: 前訴判決により、不存在の判断に既判力が生じています。
- T: 残部の2000万円については、どうですか。
- S: 残部は、114条2項の適用対象外となりますので、既判力は生じません。
- T: 残部の主張を信義則により封ずるのがよいのかどうか、どう思いますか。
- S: この場合については、残部を主張することが信義則に反するとは言い切れないですね。
- T: 残部については、既判力により一律に遮断するよりも、信義則により事案に応じて適切な解決を図る方がよいでしょうね。ところで、既判力の根拠は、何でした。いろいろな説明の仕方はありますが、根拠を2つあげるとすると、一つは、自己に有利な判決を得るように訴訟を追行する地位が当事者に与えられていること、つまり、手続保障があることでしたね。もう一つは、
- S: 当事者が紛争解決を求めており、紛争解決の必要があることです。
- T: その、手続保障と紛争解決の必要性の二つの視点から先ほどの結論を説明するとどうなりますか。
- S: 被告は、相殺の抗弁により主張した反対債権全体について、自己に有利な判断を得るための手続地位を保障されていますが、紛争解決のために既判力を発生させることがどうしても必要なのは、訴求債権と対当する部分に限られるので、この部分についてのみ既判力が肯定される、ということですか。
- T: そのように説明してよいでしょうね。
(2005年2月16日−2005年2月27日)
債権者代位と独立参加
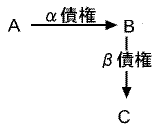 S: 「Aが、Bに対する債権(α債権)に基づいて、BのCに対する債権(β債権)を行使する債権者代位訴訟を提起した。α債権の存在を争うBは、どうしたらよいか」という問題についてですが、これは最判昭和48年4月24日民集27巻3号596頁を基にした事例問題で、その判旨で解決されるとは思いますが、いくつか質問したいことがあります。
S: 「Aが、Bに対する債権(α債権)に基づいて、BのCに対する債権(β債権)を行使する債権者代位訴訟を提起した。α債権の存在を争うBは、どうしたらよいか」という問題についてですが、これは最判昭和48年4月24日民集27巻3号596頁を基にした事例問題で、その判旨で解決されるとは思いますが、いくつか質問したいことがあります。
- T: どうぞ。
- S: 被代位者であるBは、Aに対して、別訴で、α債権不存在確認請求の訴えを提起することができるのでしょうか。
- T: えぇぇ!!(図を描く。描いた図に記号の間違いがあることを学生から指摘されて、訂正する)。この場合に、Bは、α債権について管理処分権を失っているわけではなく、また、AC間の訴訟の訴訟物たる権利とは別個の権利について訴えを提起するのですから、訴えは適法でしょう。
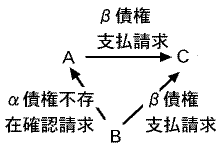 S: AB間で、α債権の不存在を確認する判決が確定すると、AC間の訴訟はどうなるのでしょうか。
S: AB間で、α債権の不存在を確認する判決が確定すると、AC間の訴訟はどうなるのでしょうか。 - T: 当事者が異なり、また、115条1項2号の適用もありませんので、AB間の判決の既判力がAC間に及ぶと言うことはありませんが、ただ、Cによってその判決が援用されれば、普通は、Aは当事者適格を欠くと判断され、訴えは却下されるでしょう。そうなるように、Bは、Cの側に補助参加するのがよいでしょう。
- T: ちなみに、AC間でα債権の存在が認定されてAの当事者適格が肯定されても、その判断にBが拘束されるわけではありません。AのCに対する請求が棄却された場合でも、Bは、「α債権は存在しなかったのだから、Aはβ債権について訴訟担当資格を有せず、従って115条1項2号の適用はないから、AC間の請求棄却判決の既判力はBに及ばない」と主張して、Cに対してβ債権支払請求の訴えを提起することを妨げられません。
- S: α債権の不存在を主張するBが、別訴で、Cに対してβ債権の支払請求の訴えを提起することは、許されるでしょうか。
- T: 債権者代位訴訟は法定訴訟担当であり、115条1項2号が適用されるという判例の立場を前提にしますね。α債権が存在し、Aが適法に代位訴訟を提起していることを前提にすると、その後にBがCに対して別訴でβ債権支払請求をすることは、重複起訴の禁止に触れるのでしたね。この場合には、Bは、β債権支払請求について、当事者適格も否定されますので、その理由によっても、訴えは不適法になります。
- T: 問題は、Bがα債権の不存在を主張して別訴を提起する場合ですね。BC間の訴訟で、α債権の不存在が認定されれば、Bは、β債権について管理処分権を有していることになり、Bのβ債権の支払請求の訴えは適法になります。しかし、α債権の存在が認定されれば、逆になります。そうした状況の中で、Aのβ債権支払請求訴訟とBのβ債権支払請求訴訟とが同時に係属することは好ましいことではないでしょう。特に、AC間ではα債権の存在が肯定されて、β債権の存在が否定されて、請求棄却判決が確定し、他方で、BC間でα債権の存在が否定されて、β債権の存在が肯定されて、請求認容判決が確定すると、法律関係が混乱しますね。既判力の抵触が生ずると言えるかは別として、それに近い法律関係の混乱と評価してよいでしょう。そして、当事者適格の基礎となるα債権の存否と訴訟物たるβ債権とが両方の訴訟で重複審理されますね。また、被告であるCは、二重に応訴することになりますね。これで、142条の規定の趣旨の多くがこの場合に妥当することになるでしょう。
- T: 一般論として言えば、民事訴訟では紛争の相対的解決が認められていますので、適法に独立参加することができる場合に、常に別訴が禁止されて独立参加が強制されるというわけではありません。しかし、この場合には、二つの訴訟で訴求される権利は、Bに属するβ債権であり、全く同一であること、そして、α債権の存否がAとBの当事者適格を同時に左右しますので、その特殊要因により、Bの別訴は許されず、独立当事者参加しなければならないと考えるべきでしょう。
- S: 最後の質問です。Bの参加は権利主張参加ですが、AC間の訴訟の目的はβ債権です。Bは、Aに対して、訴訟の目的となっていないα債権の不存在確認請求をすることができるのでしょうか。現行法では片面的参加が明文の規定で認められていますので、あまり問題にする必要はないとは思いますが。。。
- T: 最判昭和48年4月24日民集27巻3号596頁は、片面的参加が許されないとされていた旧法時代の判例ですが、その事件でもその点は特に問題にされていませんね。47条の「訴訟の目的が自己の権利であることを主張する」というのは、広く考えた方がよいでしょう。
- T: 独立当事者参加は三者間の法律関係を論理的に矛盾なく確定することを目的とする制度でしたね。ですから、条文の文言は、「訴訟の目的の全部若しくは一部が自己の権利であることを主張する」となっていますが、参加人が訴訟の目的つまり原告の請求と論理的に相容れない権利主張をする場合には、参加の理由があり、その権利主張は請求レベルであっても理由付けのレベルであってもよいとすべきでしょう。教科書の説明は、そうなっていますね。問題は、α請求の存否は原告の当事者適格にのみ関係し、原告の被告に対する請求の本案の問題と関係しないことでしたね。確かに、α債権不存在の主張は、参加要件としての権利主張にはなり得ないとの見解もあります。片面的参加が認められていなかった旧法時代には、この参加は独立当事者参加ではなく、共同訴訟参加と扱うべきであるとする見解もありました。現行法の下では片面的参加が認められていますので、独立当事者参加と扱った上で、α債権不存在確認請求とβ債権支払請求とについて合一確定が要求されるか否かの問題と扱ってよいでしょう。
- T: その点から見ると、どうでしょうか。たとえば、第一審でAが全面勝訴した場合に、Bが控訴して、BのCに対するβ債権支払請求の棄却部分についてのみ不服を申し立てるということが許されるかというと、そうはならないでしょう。BのCに対するα債権不存在確認請求の棄却判決と、BのCに対するβ債権支払請求認容判決とは論理的に両立しえない関係にあるというべきでしょう。また、第一審でBが全面勝訴して、Aが控訴する場合でも、Aがα債権不存在確認請求の認容部分の取消しを求めないと、論理的に矛盾のない解決が得られませんね。次のように説明してよいでしょう。α債権の存在は、Aの当事者適格を根拠づけるのみならず、実体法のレベルでもAによるβ債権行使の要件です。したがって、AのCに対する請求は、Aがβ債権を代位行使できるとの主張も含んでおり、この主張とBのα債権債権不存在の主張とは相容れない関係にあるから、Bのα債権不存在確認請求は、独立参加の要件の一つである権利主張になるということができる。
問答9・11及び14・15は、整理段階での補充である。授業時にした蛇足の説明は削除した。問答14の説明を授業時にすることができなかったのは、法学教師として力不足である。
問答8の質問に対する答えは、案外難しい。
- AとBとがそれぞれ動産の所有権を主張して、現在の占有者Cに対してその返還を求める場合を考えると、この場合でも、問答10に述べたことは妥当する。しかし、この場合には、一方の提訴後でも、他方は別訴を提起でき、独立参加を強制されるわけではない。したがって、この場合と学生の質問の場合とを区別する理由を述べなければならない。
- 債権が二重に譲渡され、各譲受人が債務者に対して支払請求の訴えを提起する場合の取扱いも検討しておかなければならない。
以下は続きの想定問答である。
- S: Aが全面勝訴して、Cのみが控訴をし、第一次的にはAのCに対する請求の棄却、第2次的にα債権不存在を理由に訴え却下を求め、審理の結果、裁判所がβ債権の存在とα債権の不存在の心証を抱いた場合は、どうなるのでしょうか。
- T: Aの訴えは却下すべきでしょうね。BのCに対する訴えを却下したままにすべきか、それとも原判決を取り消して、請求認容に変更し、あわせてBのAに対するα債権不存在確認請求を認容すべきか、迷いますね。Bが原判決に対して不服申立てをしていないことを重視すれば、Bの請求については原判決のままにすべきでしようが、そうなると、Aの訴えを却下する理由と、BのAに対するα債権不存在確認請求の棄却判決とが矛盾しますね。そして、BのCに対する訴えを却下する原判決をそのままにして、それが確定した場合に、却下判決については、却下の理由に既判力が生ずるので、再度BがCに対してβ債権支払請求訴訟を提起することが許されるかが問題となります。ただ、債権者の債務者に対する債権の存在が確定しても、その後に債権者が代位権行使を放棄すれば、債務者は再び自己の権利を行使できるはずです。それが、既判力の標準時後の事由と評価されるのであれば、今の設例で、BはCに対して再度β債権支払請求訴訟を提起することができることになりますね。そうなると、二度手間になるだけでしょう。この問題は、Bが原判決に対して不服申立てをしない理由に依存しそうですね。控訴審における不服申立ての手数料をどう考えるか。そして、Bは原判決に対して不服申立てをしたいのだが、そうしない理由が手数料を払うのが困難であるということだけである場合をどう処理するかでしょう。今はこの程度にして、未解決の問題にしておきましょう。
(2005年2月7日−2005年2月9日)
- T: 参加的効力は、訴訟告知を受けた者が補助参加しなくても生ずるのでしたね。
- T: 判例資料集の29頁の10番の事件を見てくれますか。最高裁判所平成14年1月22日第3小法廷判決(平成10年(オ)第512号)
です。要旨を読んでくれますか。番号なしの部分です。
- S1: 「商品の売主が建築工事の請負人に対して代金支払請求の訴えを提起したところ,買主は施主であるとの主張がなされたため,売主が施主に訴訟告知をしたが,施主が補助参加することなく,買主は請負人ではなく施主であるとの理由で請負人に対する代金支払請求が棄却された後で,売主が施主に代金支払請求をした場合に,前訴判決中の買主は施主であるとの判断に参加的効力は生じないとされた事例」。
- T:
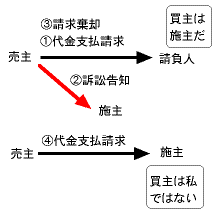 黒板の図を見てくれますか。売主は、請負人に対する第一訴訟では、買主は施主であるとの理由で敗訴しました。施主に対する第2訴訟では、買主は請負人であるという理由で敗訴する可能性があるのですね。矛盾した理由による両負けです。そのリスクを回避するために、売主の訴訟代理人は、施主に対して訴訟告知をして、施主が「買主は自分ではない」と主張することを封じようとしたのです。しかし、予期に反して、最高裁は、この場合には判決理由中の「買主は施主である」との判断には参加的効力が生じないとしたのです。
黒板の図を見てくれますか。売主は、請負人に対する第一訴訟では、買主は施主であるとの理由で敗訴しました。施主に対する第2訴訟では、買主は請負人であるという理由で敗訴する可能性があるのですね。矛盾した理由による両負けです。そのリスクを回避するために、売主の訴訟代理人は、施主に対して訴訟告知をして、施主が「買主は自分ではない」と主張することを封じようとしたのです。しかし、予期に反して、最高裁は、この場合には判決理由中の「買主は施主である」との判断には参加的効力が生じないとしたのです。
- T: 最高裁は、訴訟に参加しなかった被告知者に対して参加的効力が生ずるための要件を2つ設定しました。1番目の要件は、要旨1です。読んでいただけますか。
- S2: 「旧民訴法78条,70条(現53条,46条)の規定により裁判が訴訟告知を受けたが参加しなかった者に対しても効力を有するのは,訴訟告知を受けた者が同法64条(現42条)にいう訴訟の結果につき法律上の利害関係を有する場合に限られるところ,ここにいう法律上の利害関係を有する場合とは,当該訴訟の判決が参加人の私法上又は公法上の法的地位又は法的利益に影響を及ぼすおそれがある場合をいう」。
- T: 2番目の要件は、参加的効力の生ずる判断についての要件です。要旨2aを読んでくれますか。
- S2: 「参加的効力の及ぶ理由中の判断とは,判決の主文を導き出すために必要な主要事実に係る認定及び法律判断などをいうものであって,これに当たらない事実又は論点について示された認定や法律判断を含むものではない。」
- T: この2つの要件をどのように理解すべきか、そして判旨が妥当なものかについては、演習などで検討していただくことにして、ここでは、最高裁がこうした要件を課していることに注意してください。
- T: この訴訟の原告の訴訟代理人は注意深く訴訟を追行したのですが、結果的にまずいことになりましたね。差戻審が自由心証により施主を買主と認定する可能性がまだ残っていますので、矛盾した理由による両負けが確定したわけではありませんが、そのリスクが生じました。この判決の存在を知った皆さんが同じような失敗をして、両負けに至ったら、弁護過誤を問われるでしょう。どうしたらよいですか。
- S3: 売主と被告とを共同被告にして訴えます。
- T: それは、必要的共同訴訟ですか、通常共同訴訟ですか。
- S4: 後者です。
- T: 併合して審理・裁判される限り、矛盾した理由で売主が負けることはないでしょうが、しかし、弁論が分離されるとその可能性が生じますね。弁論の分離を阻止するためには、原告はどうしたらよいですか。
- S5: 41条の同時審判申出ですか。
- T: そうです。条文を見てくれますか。問題は、この場合の請負人に対する権利と施主に対する権利とが、41条1項の「法律上併存し得ない関係」にあるか否かです。「法律上併存し得ない関係」の代表例は、代理権の存在を前提とする本人に対する請求権と、無権代理であることを前提とする代理人に対する責任追及権です。無権代理人の責任は、何条でしたかね。
- S6: 民法117条です。「他人の代理人として契約を為したる者がその代理権を証明すること能はず、且本人の追認を得ざりしときは、相手方の選択に従いこれに対して履行又は損害賠償の責めに任ず」。
- T: ありがとう。複数の被告のうちのどちらかが買主であるという場合は、「事実上併存し得ない」場合であって、「法律上併存し得ない」場合ではないから、この場合には41条の適用はないというのが、立法当時の見解でした。ただ、最近は、このような場合にも類推適用すべきであるという見解もありますので、それに従えば、同時審判訴訟として扱ってもらえるでしょう。
- T: しかし、もし、裁判所がこの場合に41条の類推適用を認めてくれないと、同時審判訴訟にはなりません。参加的効力も役立たないということで、原告はかなり苦しい立場に立たされることになりますね。そこで、41条の適用を確実にするために、主張の立て方を工夫することにしましょう。工事現場から注文があったこと、売主が搬入した商品が工事に使用されたことを前提にして、次のように主張します。
- 第1に、請負人が施主の代理人として注文しており、施主は請負人に代理権を与えているから、施主は代金支払義務を負う。
- 第2に、もし、請負人が代理権を与えられていないのであれば、請負人に対して民法117条により損害賠償を請求する。
- 第3に、もし、請負人が施主の代理人として注文したとの事実が認められないのであれば、施主が請負人を代理人とすることなく自ら注文したものと考えられ、その事実により施主は代金支払い義務を負う。
- 第4に、もし第3の主張が認められないのであれば、請負人が買主として注文したのであろうから、請負人に対して代金の支払いを求める。
- T: 最初の2つで、41条の要件を満たすことができるでしょう。本来主張したいことは3番と4番ですが、41条の要件を満たすように、いわばダミーとして1番と2番の主張を入れるのです。これも許されてよいでしょう。1番と3番の主張の違いは、訴訟物の差異をもたらさないので、訴訟物は、(α)施主に対する代金支払請求と、(β1)無権代理人としての請負人に対する損害賠償請求(主位請求)と、(β2)買い主としての請負人に対する代金支払請求(予備請求)になります。判例の事案で主張されていないのは(β1)で、これがいわばダミーの請求になります。
- T: ちなみに、この訴訟では、原告は、施主に対して民法248条・703条による不当利得返還請求も予備的に併合しておくべきなのでしょうね。
整理の段階で、授業における平成14年判決の紹介の仕方が幾分雑であったことに気づいた。問答1、5から7、9は整理段階での追加である。問答21も整理段階での追加である。最高裁判所平成14年1月22日第3小法廷判決(平成10年(オ)第512号)の要旨は、授業後に追加した。実際に使用した要旨番号とはやや異なる。
最高裁が示した第1の要件の位置付けには迷うが、次のように考えてよいであろうか。訴訟告知による参加的効力が生ずるためには、被告知者は告知者のために補助参加すべきであるという当為条件が満たされる必要がある(参加責任ないし参加義務)。補助参加も、一般人にとっては、訴訟代理人の選任を伴うそれなりに大きな負担である。被告知者は、将来自己に降りかかるであろう不利益が明確に大きなものでなければ、なかなか参加できない。このことを考慮すると、被告知者が参加責任を負うか否かは、(α)告知者が被告知者による補助を受けることの必要性だけで決定するのは妥当ではなく、これと、(β1)被告知者に生ずる参加の負担及び(β2)彼にとってその訴訟がもつ意味(重要性)との緊張関係の中で決まるべきものであろう。
平成14年判決は、被告知者の参加責任を「当該訴訟の判決が参加人の私法上又は公法上の法的地位又は法的利益に影響を及ぼすおそれがある場合」に限ってのみ肯定することとした。ただ、「法的地位又は法的利益に影響を及ぼすおそれ」は、多種多様であり、その度合いは様々であることを考慮すると、参加責任を発生させるのに足りる「法的地位又は法的利益に影響を及ぼすおそれ」が何であるかについてさらに検討が加えられるべきである。
ともあれ、評価に戸惑った判決ではあるが、重要な判例であることには変わりはない。そのような判決は、判決の文言に即して素直に紹介しておくべきであった。
(2005年1月16日−2月7日)
同時審判訴訟
以下は、想定問答
- T: もう少し事例を単純にしよう。請負人が施主の代理人として称して、建築資材の注文をし、売主が商品を工事現場に納入したとします。施主が請負人にそのような代理権を付与したかどうかが問題となったので、売主が両者を共同被告にして、次の請求の訴えを提起し、同時審判の申出をしたとします。
- 施主に対しては、代理権の付与を前提にして、代金支払い請求
- 請負人に対して、代理権の欠如を前提にして、損害賠償請求
- T: 裁判所が代理権の存在を認めて施主に対する請求を認容するとします。請負人に対する請求はどうなりますか。
- S1: 請負人に対する請求は、施主に対する請求が認容されることを解除条件とするものではありませんので、これについては請求棄却判決をします。
- T: この訴訟は、必要的共同訴訟ですか。
- S2: 通常共同訴訟です。同時審判申出があってもこの点は変りません。
- T: この判決に対して施主が控訴したときに、売主は、請負人に対する請求を棄却した部分について控訴を提起する必要がありますか。
- S2: 売主が控訴を提起しないと、請負人に対する請求を棄却した部分は確定してしまいます。控訴審が、施主から請負人への代理権の授与はなかったと判断すると、施主に対する請求も棄却され、原告は矛盾した理由により両負けになってしまいます。それを避けるために、原告は、請負人を被控訴人にして、控訴を提起しておかなければなりません。
(2005年1月16日)
請求棄却と訴え却下(1)
授業の後で
- S1: 請求棄却と訴え却下の違いがよく解りません。
- T: 請求について判断する判決が本案判決で、請求について判断しないという判決が訴え却下判決です。本案判決のうちで、請求に理由がないとする判決が、請求棄却判決です。
- S1: 具体的にどのような場合に請求を棄却して、どのような場合に訴えを却下するのか、なかなかつかめなくて。。。
- T: まったく、慣れるまでになかなか時間がかかりますね。しかたないです。でも、そのうちにわかるようになりますよ。
- S2: 請求棄却か、訴え却下か、よく解らないときには、「訴えを排斥する」といった表現で答案を作成してもよろしいでしょうか。
- T: そうですね。私の試験に関する限りは、それで結構です。苦慮してそのような表現をしたということは、読みとります。ただ、できるだけ、訴え却下か請求棄却か明示してくださいね。
このような問題に慣れるためには、択一式あるいは正誤判定形式の問題が有効なのかもしれない。
次の事例について、下記の問に答えなさい。
- マンションの改修工事にともない、原告の部屋の外の壁面に出窓風の飾り物が設置され、原告がその飾り物の撤去をマンション管理組合に求めた場合に、裁判所が「飾り物は外壁に強固に固定され、建物に附合しており(民法242条)、マンション所有者全員の共有に帰していて、管理組合にはその撤去の権限はない」と判断したとき。(最高裁判所
昭和61年7月10日 第1小法廷 判決(昭和58年(オ)第582号))
- 宝塚市市長が、「宝塚市パチンコ店等,ゲームセンター及びラブホテルの建築等の規制に関する条例」に基づき、同市内においてパチンコ店を建築しようとする者に対し,その建築工事の中止命令を発したが,同人がこれに従わないため,同人に対し同工事を続行してはならない旨の裁判を求めて行政訴訟を提起したとき。(最高裁判所
平成14年7月9日 第3小法廷 判決(平成10年(行ツ)第239号))
- 宗教法人の代表者(住職)として寺院建物の所持を開始した原告が、教義上の異説を唱えたとして僧籍剥奪処分である擯斥処分を受け、その後に法人の代表者に任命された者が原告の占有を奪ってその法人がその建物の占有を開始した場合に、原告が法人を被告として占有回収の訴えを提起したとき(判旨にはなっていないが、最高裁判所
平成10年3月10日 第3小法廷 判決(平成6年(オ)第1998号)を参照)
- 被告の著作物は原告の著作物の著作権を剽窃したものであり、原告の著作権を侵害していることを理由に原告が損害賠償請求の訴えを提起したとき。
- 原告が、被告の著作物は原告の著作物の剽窃であることの確認を求める訴えを提起したとき。
- シャイロックが、期限までに債務の弁済をしなかったアントニオに対して、消費貸借契約中の特別の条項に基づき、アントニオの体からシャイロックが希望する部分の肉1ポンドの切り取って引き渡すことを求める訴えを提起したとき。
[問題形式1] 上記の事例のうちで、訴えが却下されるべきものを全てあげなさい。
[問題形式2] 上記の事例のうちで、訴えが却下されるべきものはいくつあるか。
[問題形式3] 上記の事例のうちで、訴えが却下されるべきものの組み合わせはどれか。 b−e−f
fについては、現行法上是認されえない内容の判決を求める請求は請求適格を欠くとの立場に立って、その訴えは却下されるべきものとした。
(2005年1月16日−2005年2月7日)
請求棄却と訴え却下(2)
授業の後で
- S1: 貸金請求訴訟で、債権が存在しないとの理由で請求棄却判決が確定した後で、債権者が再度同じ債権の支払請求の訴えを提起した場合には、どうなるのですか。
- T: 通説では、訴えの利益が肯定されることを前提にして、後訴裁判所は前訴判決の既判力ある判断、つまり債権が存在しないとの判断に拘束され、再度、請求棄却判決をすることになります。松本先生は、既判力の作用について一時不再理説をとっていますので、これとは違った結論になります。
- S1: 松本説では、前訴の訴訟物と後訴の訴訟物とが同一関係あるいは矛盾関係にある場合に、前訴の既判力の標準時後の事由を主張することなく前訴判決の既判力ある判断と抵触する請求の訴えを提起しても、その訴えは不適法になるのでしたね。先ほどの設例は、前訴請求と後訴請求とが同一関係にあり、かつ、前訴の口頭弁論終結時に存在しないと判断された債権がその後の新事由により存在するようになることは普通はないので、訴え却下になるのですね。
- T: そうです。ただ、通説にしたがっても、確定判決により存在を否定された債権について100回も同じ訴えを提起すれば、裁判所は訴えを却下するでしょう。訴状を被告に送達することさえしないでしょう。
- S2: なぜ?
- T: 訴権つまり訴える権利の濫用と評価されるからです。訴権の濫用でないことが訴訟要件の一つになっていると考えます。
以下は、続きの想定問答
- S2: 同じ訴えを10回提起したときは、どうなるのですか。2回目の時はどうなるのですか。
- T: 訴える権利の濫用かどうか、信義則に反するかどうかは、個々の事案ごとに判断されるべきものですので、一律にはいえません。しかし、前訴の既判力の標準時後の新たな事由が主張されていないため、本案判決をするとなれば同じ判決をすることになる場合に、同じ本案判決をすることに意味がないのであれば、つまり、既判力の標準時の更新に意味がないのであれば、2回目でも不適法な訴えとされる可能性が高いでしょう。先ほどの貸金返還請求の場合がそうです。もっとも、これについて公表された最高裁判決があるわけではなく、見解は分かれるというべきでしょう。
- S3: 既判力の標準時の更新に意味があるというのは、どんな場合でしょうか。
- T: たとえば、ある不動産の所有権確認請求が棄却された後で、前訴原告が再度同じ訴えを提起する場合です。原告が新たな所有権取得事由を主張している場合はもちろん、そうでなくても、後訴の口頭弁論終結時において原告に所有権がないとの判断に既判力を生じさせることに十分意味があるでしょう。訴え却下よりも、請求棄却の方がよいでしょう。ただ、それでも、新たな事由を主張することなく同じ訴えが10回も提起されると、被告も裁判所も迷惑でしょう。その時に、どうするか。新たな事由の主張がないことを確認した上で140条により口頭弁論を経ずに訴えを却下するか、それとも、口頭弁論を開いて最初の期日で弁論を終結して請求を棄却するか。意見は分かれるでしょうね。
参考判例
(2005年2月16日−2005年2月16日)
固有必要的共同訴訟
- T: 必要的共同訴訟とは、どのようなものですか。
- S1: 共同訴訟人間で判決の合一的確定が必要となる訴訟です。
- T: これには、2つの類型があるのでしたね。何と何ですか。
- S1: 類似必要的共同訴訟と固有必要的共同訴訟です。
- T: どのように違いますか。
- S1: 類似必要的共同訴訟は、各共同訴訟人が単独でも当事者適格を有するものです。固有必要的共同訴訟は、各共同訴訟人が単独では当事者適格を有さず、全員が共同訴訟人になることが法律上強制される訴訟です。
- T: 固有必要的共同訴訟の例を一つあげてくれますか。
- S1: 例えば、第三者が提起する婚姻取消訴訟では、夫婦を被告にすることが必要です。
- T: もう一つの例を、先日配布した判例資料集の中から見てみましょう。資料集の54頁にある、21番の判例です。最高裁判所平成10年3月27日第2小法廷判決(平成8年(オ)第1681号)です。要旨を読んでくれますか。
- S2: 「商法257条3項所定の取締役解任の訴えは、会社と取締役との間の会社法上の法律関係の解消を目的とする形成の訴えであるから、当該法律関係の当事者である会社と取締役の双方を被告とすべき固有必要的共同訴訟である」。
- T: 取締役を選任する株主総会決議の取消訴訟では、誰が正当な被告になりますか。
- S2: 会社だけです。
- T: そうですね。株主総会決議取消しの訴えの場合と、取締役解任の訴えの場合とで、取扱いが違うのですね。教科書では、両者が並列的に取り上げられていますが、気をつけてください。
- S3: 両者の取扱いを違える実質的な理由は何なのでしょうか。
- T: う〜ん。。。判例の説明は、次のようになっていますね。理由のところを見てくれますか。「商法二五七条三項所定の取締役解任の訴えは、会社と取締役との間の会社法上の法律関係の解消を目的とする形成の訴えであるから、当該法律関係の当事者である会社と取締役の双方を被告とすべきものと解される」。その次が重要ですね。「これを実質的に考えても、この訴えにおいて争われる内容は、『取締役ノ職務遂行ニ関シ不正ノ行為又ハ法令若ハ定款ニ違反スル重大ナル事実』があったか否かであるから、取締役に対する手続保障の観点から、会社とともに、当該取締役にも当事者適格を認めるのが相当である」。つまり、取締役選任決議の取消しの訴えの場合よりも解任の訴えの場合の方が、請求認容判決の取締役に与える影響が大きいと考えているのですね。よろしいですか。
- S3: なるほど。
問答の展開によっては、次の判例の紹介が必要となる場合もあろう。
- 最判昭和44.7.10民集23-8-1423
- 最判昭和36年11月24日民集15-10-2583
問題は、それをどのような形で用意しておくかである。
- 予め教材で配布しておく。 配布教材が多くなりすぎる可能性がある。
- ネットワーク上にデータをおいて、必要になった時点でプロジェクターを通してスクリーンに映し出す。 授業では、空白の時間が許されるのは、長くて2ないし3分であろう。この時間内に資料提示ができればよいが、できなければ、その場での資料提示はあきらめた方がよい。
(2005年1月11日)
訴訟脱退(1)
授業の後で
- S: 当事者参加訴訟において、原告又は被告が脱退した場合の判決の効力がよくわかりません。
- T: 学説が錯綜していますね。判例もない領域ですので、今は、一番覚えやすい説を一つ覚えておけばよいでしょう。一番わかりやすいのは、井上治典先生の見解でしょう。井上先生は、脱退を訴訟追行権の放棄と考えていますね。脱退者は、自己に関係する請求部分をこれまでに提出された訴訟資料と残存当事者が今後提出する訴訟資料とに基づいて審判することを認めて、訴訟から離れるのですね。
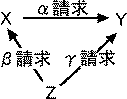 S: (黒板に図を書きながら)原告が被告に所有権確認の訴えを提起して、参加人が原告と被告の双方に所有権確認の訴えを提起した場合に、井上先生の見解ではどうなるのですか。
S: (黒板に図を書きながら)原告が被告に所有権確認の訴えを提起して、参加人が原告と被告の双方に所有権確認の訴えを提起した場合に、井上先生の見解ではどうなるのですか。 - T: 対抗要件の問題が絡まないとしますね。原告Xが脱退した場合に、裁判所が参加人Zに所有権があると判断すれば、γ請求とβ請求を認容し、α請求を棄却します。他方、裁判所が被告に所有権があると判断すれば、α請求もβ請求もγ請求も棄却されることになります。
- T: 被告が脱退した場合は、どうなりますか。
- S: 裁判所が原告に所有権があると判断すれば、α請求が認容され、β請求とγ請求が棄却されます。
- S: 兼子説だと空白域が生ずるというのがわかりません。
- T: 兼子先生の説というのは、自己の立場を全面的に参加人と相手方との間の勝敗の結果に委ね、これを条件として自己が関係する請求について予告的に放棄または認諾する性質をもつ訴訟行為であるとする見解ですね。原告が脱退して、裁判所がγ請求を棄却する場合は、どうなりますか。
- S: 原告は、勝訴した被告に対するα請求を放棄したことになります。β請求は、、、
- T: この場合に原告がβ請求を認諾したらおかしなことになりますね。参加人は、放棄していない。判決もなされない。
- S: これが空白域ですか。
- T: そう。では、原告が脱退して、裁判所がγ請求を認容する場合は、どうなりますか。
- S: 原告は、勝訴した参加人の自己に対するβ請求を認諾したことになります。α請求は、どうなるのですか。
- T: この場合には、α請求を放棄したことにしても不都合はないのですが、兼子先生の説では、脱退者は、勝訴者と自己との間の請求についてのみ放棄または認諾をすることになっています。
- S: そうなると、被告は、α請求について確定判決を得られないという不利益を受けますね。
- T: そう。その不利益は、脱退について相手方の同意が必要であるとすることによりに阻止されます。
- T: 逆に、井上説では、脱退に相手方の同意が必要であるとする理由がありません。それが井上説の難点と言えば難点になるでしょう。あまり重要な問題だとは思いませんが。
整理の段階で幾分補充した(特に問答10・15・16)。
(2005年1月3日)
訴訟脱退(2)
想定問答
- T: こんな問題はいかがですか。Xが、Yに対する売掛代金債権の取立訴訟を提起しました。その訴訟の係属前に係争債権を譲り受け、対抗要件も具備していると主張するZが訴訟に当事者参加をし、Yに対して支払請求、Xに対して債権の帰属確認請求を定立しました。Xは、Zに債権譲渡したことを認め、訴訟から脱退します。その直後にYが、当該債権には譲渡禁止特約があることを主張しました。裁判所は、審理の結果、当該債権が存在することを認め、譲渡禁止特約があり、Zはその点について善意であるが重過失があったと認定したとします。裁判所は、どのような判決をすべきでしょうか。その判決は、どのような効力をもちますか。
- S: 譲渡禁止特約があるので、債務者との関係では債権者はXですね。XとYとの間では、どう考えたらよいのですか。
- T: 迷いはありますが、債権はXに帰属するとしてよいでしょう。対価を伴う債権譲渡が無効であれば、ZはXに対して不当利得返還請求をすることができるから、債権の譲渡人と譲受人との関係は、それで調整されるでしょう。譲渡人の一般債権者との関係が問題となりますが、債務者に対抗できないのに第三者には対抗できる債権譲渡というのは、法律関係の混乱の元になりますので、それは否定してよいでしょう。それを前提にすると、井上先生の見解にしたがうと、どうなりますか。
- S: Zの請求はすべて棄却されて、Xの請求が認容されることになります。で、Xは、脱退しているのですよね。脱退者の請求が認容されるというのでよいのですか。
- T: 井上先生の見解だと、脱退者は自己の請求を放棄しているわけではないですね。自己の関係する請求についての判断を、これまでに提出された裁判資料と脱退後に残存当事者が提出する裁判資料に基づいて判断してくれと言っているにすぎないのですね。ですから、脱退した原告の請求が認容されることがあってもよいのです。
- T: では、兼子先生の見解ではどうなりますか。
- S: 参加人の被告に請求が棄却されます。参加人と被告間で被告が勝ったのですから、原告は被告に対する請求を放棄したことになります。
- T: そのとおり。この結論が妥当かどうかを評価していただけますか。
- S: 被告に対する債権が存在しているにもかかわらず、債権の譲受人も譲渡人も被告に対して支払請求ができなくなるのですから、妥当な結論とはいえません。
以下は、余録
- S: さきほどの井上説の結論ですが、脱退者の請求が認容されるという点が気になるのですが。。。
- T: 脱退者が訴訟に復帰する道を開いて、訴訟に復帰した場合にだけ請求を認容できるとする解決の方がわかりやすいかな。。。
- S: それだと、訴訟に復帰した時点で脱退者は自己の請求を追求する意思を明確にしたのですから、請求が認容されてもよいですね。先ほどの例では被告が譲渡禁止特約の抗弁を提出した時点で、原告は訴訟に復帰すべきだと思います。
- T: ただ、そうなると、訴訟の進行過程を脱退者に通知する必要が出てきますね。脱退を認めることにより訴訟手続を単純化しようとした趣旨が減殺されることになるでしょう。訴訟手続の単純化という視点からは、脱退原告は、訴訟追行の権利は放棄しているけれども、提出された訴訟資料に従い、自己の請求が棄却されることのみならず認容されることも意図して脱退したと考える方がよいでしょう。
(2005年1月4日)
定期金賠償
授業の後で
- S: 今日の授業とはまったく関係ないのですが、交通事故の被害者が一括賠償を求めているときに、裁判所が定期金賠償を命ずることはできるのでしょうか。
- T: 246条の問題ですね。無理だと思います。定期金賠償だと、被害者は、加害者の資力が低下した時のリスクを背負うことになりますね。リスク回避のために担保権の設定でもできればよいのですが。。。例えば、債務者の不動産に担保権の設定することを命じ、それがなされなければ一括賠償しなければならないという判決をすることも考えられますが、そうなると、債務者がそのような定期金賠償を望むかも問題となるでしょう。また、損害保険制度との関係では、保険会社が定期金賠償に応ずる態勢になっているかも、問題でしょう。2年ほど前にある損害保険会社の約款を見たときには、定期金賠償に応ずることができるような条項は見あたりませんでした。損害保険会社が定期金賠償に応ずるとしても、その原資を保険会社にプールしておくだけで足りるのか、それとも、信託銀行などに預託させるべきなのかも問題でしょう。金融不安の中では、いずれもパーフェクトとは言えず、被害者がなにがしかのリスクを背負うことになるでしょう。それを引き受けてもよいという意思が被害者つまり原告から表明されていない場合に、裁判所が定期金賠償を命じてそのリスクを原告に負わせることは、処分権主義の建前上難しいと思います。
- T: もっとも、介護費用については、被害者が他の原因で死亡した場合には、生存中の期間の介護費用のみを請求できると最高裁判例がしている関係で、定期金賠償を命ずる合理性が高いので、一括賠償を求めている場合でも、定期金賠償を命ずる余地はあります。ただ、その前提として、やはり訴えの変更は必要でしょうね。訴えの変更をさせておかないと、一つは、請求の趣旨として定期金の額が明示されていませんので、原告が求める定期金賠償額をどのように定めるのかが問題となります。さらに、適正な賠償額を算定するための算定の基礎資料が適切に得られるかどうかも問題でしょう。原告が一括賠償を求めているときに、裁判所が定期金賠償しか認められないから、訴えを変更せよ、それを前提にして訴訟活動をせよと言うことが許されるかの問題ですね。介護費用については、許す余地があると思います。
- S: いままでに、定期金賠償を命じた判決はあるのでしょうか。
- T: 逸失利益について一括賠償を命じ、介護費用について定期金賠償を命じた事例があります。これは、原告がそのように請求した事例です。伝聞でしかないのですが、死亡した被害者の両親が被害者の命日に定期金を支払うことを求めた事例もあるようです。
学生諸君の質問には、知っている範囲でその場で答え、知らないことは知らないと答えるのが正しい。
(2005年1月1日)
訴訟係属
授業の後で
- S: 訴訟係属は、訴状が被告に送達するときに生ずるんですよね。なのに、どうして訴え提起の効果とされるんですか。
- T: 確かに分かりにくいですね。ただ、訴訟係属は、一般にどのように定義されていますか。
- S: 「特定の裁判所が特定の事件について審理裁判している状態」といった形で定義されています。
- T: その状態をどのような行為の効果と位置づけるかの問題ですね。裁判所は、なぜ事件について裁判するのですか。
- S: それは、原告が訴えを提起したからです。
- T: 裁判所は、訴えに対する応答として、事件について審理し裁判するのですね。だから、訴訟係属、つまり特定の裁判所が特定の事件について裁判すべき状態は、訴え提起の効果と位置づけられるのです。ところで、訴状が被告に送達される以前は、誰が事件について処理しますか。
- S: 裁判長です。
- T: なぜ裁判所ではなくて、裁判長が処理するとされているのですか。
- S: 訴状送達前であるので、必要的記載事項が訴状に記載されているかどうかや、そもそも送達できるのかといった形式的な問題しか取り扱うことしかできないので、裁判長の処理に任されています。
- T: そうですね。それで、訴訟係属は訴え提起の効果と位置づけられるのに、そのような状態に入るのは訴状が被告に送達された時とされるのです。一般論として言えば、ある法律効果の原因と位置づけられる行為がなされる時と、その法律効果が生ずる時とが異なることは、それほど珍しいことではありません。その一つの例と見てよいでしょう。
整理の段階でかなり補充した。
(2005年1月1日)
補 足
- 明治23年民訴法は、「訴訟物の権利拘束は訴状の送達に因りて生す」(195条1項)と規定していた。「権利拘束」は現在の用語では「訴訟係属」であるから、上記の規定は、「訴訟物について裁判所が審理裁判すべき状態(以下「訴訟係属」という。)は訴状の送達により生ずる。」と言い換えることができる。したがって、訴訟係属を訴え提起の効果では訴状送達の効果と理解することも一つの考えてして成立しうる。
- 現行法の下でどのように考えるかは、いわば歴史的偶然である。すなわち、大正15年法改正時に、立案担当者が「訴訟係属は、訴えの提起により、訴え提起時に生ずる」との考えを採ったが、その後、裁判所内部における合議体と裁判長との役割分担等を考慮すると、やはり訴訟係属は訴状送達時に生ずると考えるべきであるとの考えが通説になったが、「訴訟係属は訴え提起により生ずる」との部分は維持された。
- 母法のドイツ法(1877年民事訴訟法法)では、当事者送達主義が採られ、かつ、「訴えの提起は書面(訴状)の送達によってする」(253条1項)ことを前提にして、「訴えの提起により訴訟事件の訴訟係属が生ずる」(261条1項)と規定されている。
(2016年9月4日)
職権調査と職権探知
授業の前に
- S: 職権調査と職権探知の区別がよくわからないのですが。。。
- T: 職権調査というのは、当事者からの申立や指摘がなくても裁判所が進んで判断することを意味します。職権探知は、判断資料を裁判所が収集することを意味します。
- T: 例えば、訴えの提起により、原告は、訴えが適法であることを前提にして、請求についての裁判を求めますね。原告は、訴えが適法であることについて裁判することを求めているのではありません。被告が、答弁をまったくしない場合はもちろん、「請求棄却判決を求める」という答弁をする場合でも、訴えの適法性について裁判を求めているわけではありません。それにもかかわらず、裁判所は、訴えの適法性について判断し、不適法であると判断すれば、訴え却下判決をします。両当事者ともそのような判決を求めていなくても、裁判所は、職権でそうしなければならないのです。他方、請求についての裁判、つまり本案判決は、原告がそれについての判決を求めるからするのです。これは、原告の申立てに基づいてする裁判です。
- T: 民事訴訟では、一定の事項を判断するということと、その判断資料の集め方とを区別します。判断資料の収集を当事者の責任と権限とする建前を弁論主義といい、それと対立するのが職権探知主義です。職権探知主義の下では、裁判所が進んで判断資料を収集することができます。
- S: だいたいわかりました。日常用語では、調査というと、判断材料を集めることを指すので混乱していました。職権調査というのは、判断資料の収集までは含まないのですね。
- T: そうです。職権調査あるいは職権調査事項と言うより、ストレートに、職権判断あるいは職権判断事項という方がわかりやすいですね。
- T: ちなみに、民事訴訟法や破産法で「調査」という言葉は、さまざまな意味で使われます。民事訴訟法320条の上告裁判所の調査の範囲における「調査」は、判断の意味ですね。他方、破産法8条の調査は、判断資料の収集、つまり事実の探知と証拠調べを意味します。裁判所がするものではありませんが、民事訴訟法186条の調査の嘱託における「調査」は、どうでしょうか。裁判所が報告を依頼した事項について、判断資料を集めて回答するのですが、資料をそのまま裁判所に送付すればよい場合もあるし、一定の判断をしてそれを報告する場合もあるでしょう。したがって、判断資料の収集と判断の双方を含むと言ってよいでしょう。
問答7は、整理段階での追加である。
(2004年12月31日)
必要的共同訴訟 一部の共同訴訟人がした上訴
- T: 民訴40条1項を読んでくれますか。
- S1: 「訴訟の目的が共同訴訟人の全員について合一にのみ確定すべき場合には、その1人の訴訟行為は、全員の利益においてのみその効力を生ずる。」
- T: 共同訴訟人の一人が上訴を提起するとどうなるかを見てみましょう。判例資料集の19番の事件を見てくれますか。47頁に載っている、最高裁判所
昭和58年4月1日 第2小法廷 判決(昭和57年(行ツ)第11号)の事件です。次の方、要旨の1aを読んでくれますか。
- S2: 「類似必要的共同訴訟たる住民訴訟にあっても、必要的共同訴訟人の一部が控訴を提起した場合に、控訴審は第一審の共同訴訟人全員を名宛人として一個の終局判決をすべきであり、控訴を提起した者のみを控訴人としてした判決は、違法である。(破棄理由。反対意見あり)」
- T: 共同訴訟人のうち一部の者がした上訴の効力が他の共同訴訟人にも及ぶのですね。では、判例資料集の20番の事件を見てくれますか。49頁の最高裁判所平成9年4月2日大法廷判決(平成4年(行ツ)第156号)ですね。次の方、その判旨の2aを読んでくれますか。
- S3: 「複数の住民が共同訴訟人として提起した住民訴訟において,共同訴訟人の一部の者が上訴すれば,それによって原判決の確定が妨げられ,当該訴訟は全体として上訴審に移審し,上訴審の判決の効力は上訴をしなかった共同訴訟人にも及ぶが,上訴をしなかった共同訴訟人は,上訴人にはならず,上訴をした共同訴訟人のうちの一部の者が上訴を取り下げた場合は,その者は上訴人ではなくなる。(判例変更)」
- T: 次の方、この判決において、共同訴訟人の一部のした上訴の効力のうち、他の共同訴訟人に及ぶとされたのは何で、及ばないとされたのは何ですか。
- S4: えぇ。。。
- T: じゃあ、上訴の効力を原判決の確定を遮断する効力と、上訴審の当事者となって訴訟行為をすることができるようにする効力とに分けて考えることにしましょう。判決の確定を遮断する効力は、116条のところで見ましたね。2項です。どうですか。
- S4: 判決の確定を遮断する効力は、他の共同訴訟人にも及ぶとされましたが、上訴審の当事者となる効力は及ばないとされました。
- T: そのとおり。資料集の53頁の最後の段落にその理由が書かれています。「ところで」以下です。自分で読んでおいてください。
- S10: この判旨は、住民訴訟にのみ妥当するのでしょうか、それともほかの類型の必要的共同訴訟にも妥当するのでしょうか。
- T: いい質問ですね。私は、類似必要的共同訴訟全般に妥当すると見ています。資料集の22番の判例を見てくれますか。55頁にある最高裁判所平成12年7月7日第2小法廷判決(平成8年(オ)第270号)です。要旨を次の方よんでくれます。
- S5: 「株主代表訴訟おいて、共同訴訟人の一部の者が上訴すればそれによって原判決の確定が妨げられ、当該訴訟は全体として上訴審に移審し、上訴審の判決の効力は上訴をしなかった共同訴訟人にも及ぶが、自ら上訴をしなかった共同訴訟人を上訴人の地位に就かせる効力までが民訴法40条1項によって生ずると解するのは相当でなく、自ら上訴をしなかった共同訴訟人たる株主は上訴人にはならないものと解すべきである。」
- T: このように、最高裁は、住民訴訟に限らずに、株主代表訴訟にも拡張していますね。ただ、これを固有必要的共同訴訟を含めてすべての必要的共同訴訟にまで拡張すると、40条4項が空文化してしまいます。
- S10: どういうことでしょうか。
- T: 40条4項を読んでくれますか。
- S10: 「第32条第1項 の規定は、第1項に規定する場合において、共同訴訟人の1人が提起した上訴について他の共同訴訟人である被保佐人若しくは被補助人又は他の共同訴訟人の後見人その他の法定代理人のすべき訴訟行為について準用する。」
- T: そこで引用されている32条1項を読んでくれますか。
- S10: 「被保佐人、被補助人(訴訟行為をすることにつきその補助人の同意を得ることを要するものに限る。次項及び第40条第4項において同じ。)又は後見人その他の法定代理人が相手方の提起した訴え又は上訴について訴訟行為をするには、保佐人若しくは保佐監督人、補助人若しくは補助監督人又は後見監督人の同意その他の授権を要しない。」
- T: その規定は、被保佐人等が被告となって訴訟行為をする場合には、保佐人等の同意は必要ないという規定ですね。一般化して言えば、被保佐人等が他人の行為により当事者となって訴訟行為をする場合には、保佐人等の同意は必要でないということになります。被保佐人が共同訴訟人の一人で、他の共同訴訟人が上訴を提起した場合に、被保佐人も上訴審の当事者の地位に就くことを前提にして、それが自らの意思によってそうなるのではなく、他の共同訴訟人の上訴行為によりそうなるので、32条1項が準用されているのです。固有必要的共同訴訟の場合にまで先ほどの判例法理を妥当させると、40条4項が作用する場面がなくなってしまいます。ですから、この規定を空文化させないためには、固有必要的共同訴訟には先ほどの判例法理を妥当させるべきではないことになります。
- S11: 先生、もう一回言ってください。
- T: 40条4項は、必要的共同訴訟人の一人である被保佐人等が他の必要的共同訴訟人の上訴により上訴審の当事者になることを前提にして、被保佐人等が訴訟行為をするには保佐人等の同意は必要ないとした規定ですので、これを空文化させないためには、必要的共同共同訴訟人の上訴により他の共同訴訟人が上訴人の地位に就く領域をどこかで認める必要があり、その領域として固有必要的共同訴訟を残すのが適当でしょう。したがって、平成9年判決の法理は、類似必要的共同訴訟の領域にのみ適用されると理解するのがよい。
判例の射程距離を問うという意味でも、教師が話したいことをうまく誘導しているという意味でも、問答12の質問がよい。
時間があれば、次の展開もありうる。
- S: 類似必要的共同訴訟と固有必要的共同訴訟とで、そのように取扱いを異にする実質的理由は何なのでしょうか。
- T: 類似必要的共同訴訟と固有必要的共同訴訟との違いはなんでしたか。
- S: 固有必要的共同訴訟の場合には、共同訴訟人となるべき者全員がそろわないと当事者適格を欠き、訴えが却下されます。他方、類似必要的共同訴訟の場合には、各共同訴訟人は単独でも当事者適格を有しますが、共同訴訟となった以上は、全員に判決効が拡張されるために、その訴訟は必要的共同訴訟となります。
- T: その取り扱いの差異の上訴審における反映として、必要的共同訴訟人の一部の者のみが上訴した場合に、他の共同訴訟人が上訴人の地位に就くかどうかについて差異が生ずると説明できそうですね。更に遡れば、訴訟物たる権利関係に対する利害関係の強さが異なるということができるでしょう。それは、第三者が提起する婚姻取消しの場合と、株主代表訴訟の場合を思い浮かべればわかりやすいでしょう。
演習などでは次のような展開もありえよう。
- T: 必要的共同訴訟において、共同訴訟人の一部の者のみが上訴したときに、他の共同訴訟人が上訴人の地位に就くとすることと、上訴人の地位に就かないとすることとの具体的な差異は何ですか。
- S: 上訴審の当事者にならない者には期日の呼出は行わなくてもよく、また、その者は上訴審の訴訟費用は負担しません。
- T: 上訴を提起しなかった者も上訴人の地位に就くとした場合に、その者が原判決の確定を望む旨を上訴審で申述したときは、裁判所はどうすべきですか。
- S: 判例を前提にすると、固有必要的共同訴訟の場合に問題になることですね。その場合でも、上訴人の地位に就いている以上、期日への呼出しは必要だと思います。そのことは、その者が訴訟の途中で考えを変えて、原判決の変更を求めて訴訟行為をしようとするときに重要だろうと思います。訴訟費用の問題は、例えば、第三者の提起する婚姻取消訴訟において、被告の一人のみが請求棄却判決を求めて訴訟活動をして、請求認容判決が出された場合にも生じます。人事訴訟ですので、請求認諾をしても効力はありませんが、訴訟費用に関しては、請求を争わなかったことを考慮してもよいと思います。ですから、それは、65条1項後段の問題として扱えばよいと思います。
(2004年12月31日)
相殺の再抗弁(1)
- S: 相殺の再抗弁を許容するとした場合に、相殺は、どの順序でなされるべきなのでしょうか。時間的順序なのでしょうか。論理的順序なのでしょうか。
- T: 論理的順序というのは、相殺の再抗弁を適法とする以上、できるだけそれが生きるように、原告の相殺の再抗弁を考慮しなければ被告の相殺の抗弁に理由があるという場合には、再抗弁について優先的に判断するという立場ですね。
- T: 最高裁判所平成10年4月30日第1小法廷判決(平成5年(オ)第789号)民集52巻3号930頁は、原告の相殺の再抗弁は許されないとしており、私もそれに賛成ですので、私にとっては難しい質問ですね。ただ、この事案を用いた練習問題の答案としては、最初に判例の立場を書いてください。次に、もし皆さんが判例の立場に賛成できないのであれば、時間的順序で相殺の判断をすべきであるとの立場をとっても、再抗弁を優先的に判断すべきであるとの立場を書かれても、どちらでも結構です。
この質問は、応答に苦慮する種類の質問ではない。しかし、それでも、私の場合には、この日のコンディションが悪かったため、質問の趣旨をよく理解できなかった。私の回答が遅いのを見かねて、他の学生が補足説明してくれたが、まだ飲み込めないまま、問答3の回答をした。相当の不調である。問答1は、おそらくそのような趣旨の質問であったであろうということで記したものである。おそらく学生は、この回答では不満であったであろう。なお、問答2は、整理の段階で、補充として記したものである。
(2004年12月27日)
相殺の再抗弁(2)
- S: 最高裁判所平成10年4月30日第1小法廷判決(平成5年(オ)第789号)民集52巻3号930頁の「仮定の上に仮定が積み重ねられて」の意味がよく解りません。
- T: 訴訟上の相殺ですので、相殺の意思表示により確定的に相殺の効果が生ずるのではなくて、裁判所が相殺すべきであると判断することを条件として相殺の効力が生ずるのですね。判旨を文言通りに読めば、「仮定の上に仮定を積み上げる」というのは、その条件付相殺に対抗して更に条件付相殺をすることを指します。ただ、それに続く「当事者間の法律関係を不安定にし」という部分をどのように理解すべきかは、迷います。
- 一般に訴訟外での形成権行使に条件を付すことは許されないことの理由として、相手方の地位が不安定になることが挙げられていますね。それと同じ意味での不安定であるとすれば、妥当でないでしょう。相殺の効力は、それを認める判決が確定することを条件に生ずるのであり、訴訟終了時には当事者の地位は既判力のある判断により明確になっています。訴訟は遠からず終了するのですから、訴訟上の相殺の抗弁により相手方当事者の実体法上の地位が不安定になるというのは、適当ではありません。だからこそ、訴訟上の相殺という条件付相殺が許されるのですね。
- 他方、自働債権についてせっかく審理しても無駄になる可能性がある、つまり既判力ある判断が得られないことがあるという意味で当事者の地位が不安定になるというのは、理解できます。例えば、第一審裁判所が訴求債権の存在を認めて被告の自働債権について審理を進め、その存在を認めてさらに原告の自働債権について審理を進め、その存在も認めて、最後に請求認容判決をするとします。この判決に対して被告が控訴し、控訴審で、原告の訴求債権は存在しないと判断されると、被告の自働債権についても、原告が相殺の再抗弁に供した別口債権についても、判断する必要がなかったことになりますね。最初の仮定が崩れることにより、次の仮定も崩れ、審理が無駄になります。
- T: 私は、「当事者間の法律関係を不安定にし」の部分を、後者の意味に理解しています。ただ、判決文自体は、前者の意味、つまり条件付相殺の抗弁が出されること自体により相手方当事者の実体法上の地位が不安定になるという趣旨かもしれません。このあたりは、判決の理解のしかたの問題でしょう。
- T: ともあれ、相殺の抗弁を判断する必要がなくなる場合を確認しておきましょう。訴えが不適法であるとして却下される場合には、相殺の抗弁の判断の余地がないことは当然ですので、これは除外しておきます。
- 被告の相殺の抗弁については、次の場合があります。第1に、相殺の抗弁が予備的に提出されているときに、訴求債権の不存在又は消滅が認定される場合。第2に、相殺の抗弁が時機に後れたものであるとの理由で却下される場合があります。相殺の抗弁が判断されのは、これらのいずれにも該当しないという仮定が満たされる場合です。
- 原告の相殺の再抗弁が当然には不適法にならないことを前提にして、それを判断する必要がなくなる場合を見ますと、第1に、訴求債権の不存在により被告の相殺の抗弁について判断する必要がなくなる場合。第2に、被告の相殺の抗弁が時機に後れたものとして却下される場合。第3に、被告の反対債権が不存在と認められる場合。第4に、原告の相殺の再抗弁が時機に後れて提出されたものとして却下される場合です。これらのいずれにも該当しないという仮定が満たされる場合に、初めて相殺の再抗弁について判断することになります。
- T: ただ、訴えが不適法であるとして却下されることや、相殺の抗弁・再抗弁が時機に後れた攻撃防御方法として却下されることを例外として見るならば、相手の債権を争いつつ相殺の抗弁を提出するという予備的相殺の抗弁において問題となる仮定、つまり相手の債権が存在するという仮定が、「仮定の上に仮定を積み重ねる」という言葉における「仮定」の中核になります。
- T: なお、原告・被告とも相手の債権の存在を認めた上で相殺の抗弁を提出する場合には、その意味での「仮定の上に仮定を積み重ねる」ことにはなりません。だから、魅力的な表現ではありますが、その適用範囲はあまり広くないと考えています。
- T: むしろ重要なのは、相殺に供する反対債権は、訴求債権との関連性を要求されませんので、再抗弁としてさらに相殺を許すと、審理裁判の対象がどんどん拡散してしまい、収拾がつかなくなることでしょう。再抗弁としての相殺に供する自働債権は、訴求債権と請求の基礎を同一にするのであれば、訴えの追加的変更により追加すればよいでしょう。そうでなければ別訴により訴求させて、審判対象の複雑化を防止すべきであるというのが、もっとも重要な理由だと思います。
上記の発言のうちで、2から5の部分は、この問答集の整理の段階で大幅に補充したものである。授業時の説明が、不十分であったことを反省している。
発言6の末尾の「その適用範囲はあまり広くないと考えています」というのは、少し表現が強すぎたかもしれない。多くの相殺の抗弁が予備的相殺の抗弁であることを考慮すると、「それが妥当しない場合もあることにも注意すべきでしょう」のあたりがよいであろう。
次の事項は、質問があれば答えるに留めてよいであろう。
- 原告の相殺の再抗弁が不適法で判断されると、原告は当該自働債権について訴えを提起する必要があり、訴え提起の手数料を納付しなければならない。これに対して、相殺の再抗弁が許されれば、その必要がない。
- 被告の訴訟上の相殺の抗弁の陳述の直前あるいは直後に原告が訴訟外の相殺をすると共に、それを再抗弁として提出する場合にどうなるか。
- 最高裁判所判例解説・民事編・平成10年度(上)519頁(長沢幸男)に、「本判決は、訴訟上の相殺の抗弁に対する訴訟上の相殺の再抗弁を不適法とするものであり、いずれか一方が訴訟外の相殺である場合にまで相殺の再抗弁を不適法とするものではない」とあるが、これは、被告が訴訟外の相殺の抗弁を提出した場合についてどのように理解したらよいか。前記の言明をこの場合に当てはめると、「被告の訴訟外の相殺の抗弁に対する原告の訴訟上の相殺の再抗弁を不適法とするものではない」となるが、これは、「原告の訴訟上の相殺の再抗弁は適法である」という趣旨に理解してよいか。
- 一部請求の事案において、残部の債権を自働債権とする相殺の再抗弁は適法か。適法になりうるとする見解もあるが、この問題は、おそらく、明示の一部請求に対する相殺の抗弁について外側説をとることにより解消されよう。
(2004年12月12日−2004年12月27日)
選択的併合(1)
- S: 教科書の「同一の目的を有し法律上両立することができる複数の請求を、そのうちの一つが認容されることを他の請求の審判申立ての解除条件とした併合態様をいう」という説明がよくわからないのですが。
- T: 例えば、バスの転落事故で負傷した乗客がバス会社に損害の賠償を求める場合に、まず、不法行為を理由とする損害賠償請求権が考えられますね。ほかに、どんな請求権が考えられますか。
- S: 民法415条の債務不履行を理由とする損害賠償請求権です。
- T: 乗客の損害額が1000万円である場合に、不法行為による損害賠償請求権を行使して1000万円の賠償金を得た後で、債務不履行による損害賠償請求権を行使してさらに1000万円を得ることができるかというと、
- S: それはできません。
- T: なぜですか。
- S: すでに賠償金を得ているからです。
- T: そうですね。2つの請求権は、乗客に生じた損害の回復という同じ目的に向けられています。一方でその目的を達成すると、他方も達成すべき目的を失って消滅すると考えます。このような関係を請求権競合といいます。先ほどの事例では、教科書の「一の目的」は、乗客に生じた損害の回復です。「複数の請求」は、不法行為による損害賠償請求と債務不履行による損害賠償請求です。
- T: 一方の請求について認容判決が確定すると、それで満足を受けることができるので、他方の請求についてまで認容判決をえる必要はあまりありませんね。それで、どちらか一方が認容されると、他方の請求については審理・判断を求めないという条件を付して複数の請求を併合するのが選択的併合です。
1から8が授業時の問答である。再度読み直してみると、説明不十分に気づく。9は、整理段階での補充である。さらに、教科書の説明文が、日本語として不完全であることに気づく。「同一の目的を有し法律上両立することができる複数の請求を」に対応する動詞がない。質問の趣旨は、そこにあったのかも知れない。次のいずれかに改めるべきだろう。
- 選択的併合(択一的併合) 同一の目的を有し法律上両立することができる複数の請求を併合するにあたって、そのうちの一つが認容されることを他の請求の審判申立ての解除条件とした併合態様をいう。
- 選択的併合(択一的併合) 同一の目的を有し法律上両立することができる複数の請求を、そのうちの一つが認容されることを他の請求の審判申立ての解除条件にして併合する態様をいう。
(2004年12月6日−2004年12月31日)
選択的併合(2)
授業後の質問
- S: 請求権競合の関係にある複数の請求を単純併合にした場合に、一方が認容されると、他方はどうなりますか。
- T: 普通は、裁判所からの釈明権行使を受けて、原告は選択的併合にするでしょうが、原告が単純併合を押し通せばどうなるかですね。一方が認容されれば、他方は却下でしょう。
- S: 請求棄却ではまずいでしょうか。
- T: 例えば、債務不履行を理由とする損害賠償請求権を認容する判決が確定した後で債務者が反対債権で相殺する場合を考えると、債権者は不法行為による損害賠償請求権があるから相殺は許されないと主張したくなりますね。その場合に、不法行為による損害賠償請求権を否定する判決が確定していたのでは、その主張ができなくなるでしょう。
- S: 他方について訴えを却下する理由は何なんでしょう。
- T: 一方の請求について認容判決を得ているので、同じ目的に向けられた他方の請求について認容判決を得る利益はないということで、訴え却下。
- S: 既に確定判決を得ている請求権について再度訴えを提起した場合の取り扱いと同じ論理ですか。
- T: 訴えの利益がないとする点で、共通していますね。
現在の実務ではほとんどあり得ない想定問題であるが、理論的にはありうることである。私も学生時代はよく考え込んでいた。なお、考え方としては、上記の外に、両請求とも認容した上で、判決主文において請求権競合の関係にあることを明示することも考えられる。
(2004年12月6日)
判決の主観的効力(1)
- T: 115条1項の規定を順番に見ていきます。「判決の効力は、当事者以外の者にも及ぶというのが原則である」というのは、正しいでしょうか。
- S1: 間違いです、「判決の効力は、当事者にのみ及ぶのが原則です」。
- T: その理由は?
- S1: 当事者は、自分に有利な事実を主張し、証拠を提出して、自分に有利な判決を得る地位を与えられています。そのような手続保障のない第三者に判決の効力を及ぼすことは、許されません。
- T: そうですね。そして、私人間の紛争の多くは、紛争当事者間で相対的に解決すれば足り、紛争をそのように相対的に解決しても、混乱が生ずることは少ないということも理由の一つになります。紛争の相対的解決では混乱が生ずる場合には、判決の効力の拡張が必要となり、その場合には、必要に応じて、さまざまな措置が執られます。
最初の質問は、いわゆる○×式の質問であり、私が中学・高校の頃には軽蔑されるべき種類の問題とされていた。その影響か、この種類の質問を出すことには、心理的抵抗が強い。しかし、問答の糸口にしやすい質問である。
司法試験の短答式の問題でよく出る誤文選択問題も、本質は、○×式の問題である。一つの文を読んでその正誤を問うのではなく、複数の文のなかから一つを選択させるために、ランダム回答の場合の正解率が下がるので、表面上はより良い問題形式となる。しかし、個々の文の正誤を判断できることが基本であることには変わりはない。
ちなみに、ランダム回答の正解率を下げるためだけであれば、誤文ゼロの回答の可能性を認めることも可能であるし、複数の文を1グループして、それらの文の全部について正誤を判定させ、全部が正しく判定できた場合にのみ得点を与えるとする問題形式もありうる。しかし、問題が難しくなりすぎるので(ないし、得点が困難となるので)、この形式の問題が採用されることは少ない。
このように、個々の文の正誤を正しく判断できることが誤文選択問題の基本であることを考慮すると、ダイアローグにおいて、一つの文の正誤を問うことをためらう必要はないであろう。
対話を問答1の質問で始めるのと、下記のような質問で始めるのと、どちらがよいかは、授業時間や学生の学習進捗度等に依存しよう。
- T: 既判力の相対性の根拠について説明してください。
(2004年12月1日)
判決の主観的効力(2)
- T: 115条1項2号が適用される例を挙げてください。
- S: 例えば、成年被後見人とその配偶者との離婚訴訟があります。
- T: 成年被後見人が当事者になるのですか。
- S: はい。
- T: 人事訴訟法のもとでは、成年被後見人も意思能力があれば自ら訴訟追行することができることにはなっていますが、今は115条1項2号を説明する場合ですので、それは例外としましょう。成年被後見人が意思能力を欠いていて、自ら訴訟行為をすることができないことを前提にすると、誰が訴訟を追行しますか。
- S: 成年後見人です。
- T: その訴訟における成年後見人の地位は?
- S: 代理人です。
- T: 身分行為は、代理に親しみますか。
- S: いいえ、親しみません。
- T: となると、訴訟を追行する成年後見人の地位は?
- S: 訴訟代理人ではなく、当事者です。
- T: この事例で、115条1項2号の「その他人」は、誰ですか。
- S: 被後見人です。成年後見人が当事者として追行した離婚訴訟の判決の効力が被後見人に及びます。
- T: そうですね。民法の世界における「身分行為は代理に親しまない」という強固な観念を受けて、人事訴訟法では、・・・六法を見てくれますか・・・14条が置かれているのですね。
問答5は、整理段階で若干補充がなされた。
学生の質問に対して学生に納得のいく答えを言うことができることは、教師の重要な能力である。そして、説明の中で、関係する条文を正確に素早くすぐにあげることができることは法学教師に必要な基本的能力である。ということは理解しているが、条文番号を正確に覚えていない場合には、六法で確認してから番号を言うことになる。視力が低下して、それに手間取ることが多くなってきた。
(2004年12月1日−2005年2月20日)
判決の主観的効力(3)
- T: 115条1項2号が適用される例として、今度は問題のある例を挙げてくれますか。
- S: 債権者代位訴訟があります。
- T: 例えば、
- S: Xが債務者で、Yが債権者で、
- T: 債権者がYになるのですか。。。むしろ、XとYとZがいて、XがYに対してα債権を有していて、YがZに対してβ債権を有していることにしましょう。YがXに債務を弁済しないので、Xがどうするのですか、
- S: Xが、自分のα債権の保全のために、Yに代位してYのZに対するβ債権を代位行使します。
- T: 訴訟物は、何ですか。
- S: YのZに対する債権です。
- T: 請求棄却判決が確定すると、どのような判断に既判力が生じますか。
- S: β債権が存在しないという判断に既判力が生じます。
- T: その既判力がYにも及ばないとすると、誰が困りますか。
- S: Zです。
- T: どのように困りますか。
- S: 債務者のYから再度訴えられると、それに応訴しなければなりません。
- T: そうですね。その理由により、判例は、代位債権者敗訴判決の既判力が債務者に拡張されることを肯定しているのですね。では、今日配布した判例の1番目、大審院
昭和15年3月15日 第5民事部 判決を見てください。要旨の1番を読んでくれますか。
- S: 「債権者代位訴訟において債権者が受けた判決は、債務者が訴訟に参加したか否かにかかわらず、民事訴訟法第201条第2項(現115条1項2号)により債務者に対しても効力を有する」。
- T: これは、戦争前の大審院判決です。そろそろ、これを変更する最高裁判決が出てもよい頃かとは思いますが、まだ出ていませんので、現在もこれが判例の立場であるとされています。では、この判例に従い判決効が債務者Yにも拡張されると、誰が困りますか。
- S: 債務者です。彼は、自己の債権を失なうことになります。
- T: 債務者に不利益が生じないようにするために、どのような見解が主張されていますか。
- S: 例えば、債務者に訴訟告知がなされた場合にのみ既判力が生ずるとか、彼が参加することを既判力拡張の要件とする見解があります。
- T: そうですね。債務者の立場をさらに尊重した立場として、固有適格説があります。代位債権者は、自分の債権の満足のために債務者の債権を代位行使しているのであり、債務者のために訴訟をしているのではない。請求が棄却された場合に、代位債権者は当該債権から満足を受けることができなくなるだけであり、債務者の他の財産から満足を受けることは可能であるのに、債務者は自己の債権を失う結果になる。この差は、非常に大きいから、債務者に既判力を拡張すべきではないというのです。先ほどの先例は、この点をどのようにか考えているかというと、要旨2を読んでくれますか。
- S: 「債権者は代位権行使について善管注意義務を負うから、訴訟追行に過失のある場合(例えば債務者に訴訟告知をなさなかったため債務者の手に存する訴訟資料を利用することができなかった場合)には、債務者に対し損害賠償の責を負う。」
- T: ご苦労様でした。
(2004年12月6日)
判決の主観的効力(4)
- S: 教科書に書いてある、「口頭弁論終結前の承継人については、既判力が拡張されず、訴訟承継の問題として扱われる」というのがよく解りません。
- T: 口頭弁論終結前に訴訟物たる権利関係について承継があった場合については、2つの立法の仕方があります。一つは、被承継人に引き続き訴訟をさせて、その判決の効力を承継人に及ぼすというやり方です。これを当事者恒定主義といいます。「恒定」は、恒に定まっているという意味での恒定です。恒久平和の「恒」と一定の「定」です。もう一つは、承継人に訴訟を引き継がせるというやり方です。これを訴訟承継主義といいます。この場合には、被承継人が訴訟を引き続き追行して判決を受けても、その判決の効力は承継人には及ばないことが原則となります。
- T: 日本法は、訴訟承継主義を採用しています。例えば、貸金請求訴訟の途中で、原告である債権者が債権を他に譲渡した場合には、譲受人は、民訴49条により訴訟に参加します。承継人が訴訟に参加せずに訴訟が進行した場合には、原告はもはや債権を有していないという理由で請求が棄却されることになるでしょう。他方、訴訟が被告に有利に進行している場合には、被告は、請求棄却判決を得て、その判決の効力を債権の譲受人に及ぼしたいと思うでしょう。しかし、判決効が拡張されるのは、口頭弁論終結後の承継人であり、終結前の承継人には拡張されません。被告は、51条・50条によって、債権の譲受人に訴訟を引き受けさせて、譲受人を当事者とする判決を得なければならないというのが訴訟承継主義です。
- T: ちなみに、当事者が死亡した場合にはどうなるかというと、124条1項の柱書きをと1号を読んでください。
- S: 次の各号に掲げる事由があるときは、訴訟手続は、中断する。この場合においては、それぞれ当該各号に定める者は、訴訟手続を受け継がなければならない。第1号。当事者の死亡。相続人、相続財産管理人、その他法令により訴訟を続行すべき者
- T: その規定によって、相続人が当事者となって訴訟を追行します。相続の時点で当事者の地位を当然に承継するのですが、すぐに訴訟行為をすることができるとは限らないので、中断するのでしたね。それで宜しいですか。
- S: はい。わかりました。ありがとうございます。
「はい。わかりました」という返事をいただいたものの、振り返ってみれば冷や汗ものである。問答2は、授業では説明し忘れ、対話集の整理の段階で追加したものである。問答4から6は、訴訟承継主義が意味がよくわからないという質問に対する回答としては、不要であった。
(2004年12月6日)
調査の嘱託
法務省「民事裁判所からの不起訴事件記録の文書送付嘱託等について」を紹介した後で
- T: このように裁判所から目撃者の特定のための情報について調査の嘱託がなされた場合でも、検察庁はそれに常に応ずるわけではないのですね。教科書では、内国の官庁は嘱託に応ずる公法上の義務を負うと説明されています。それがよくある説明ですが、少し言葉を補った方よいでしょう。君なら、どのように補いますか。
- S: 「但し、調査の嘱託に応ずることにより関係者の名誉・プライバシーを侵害するおそれがある場合はこの限りでない」と補います。
- T: なかなかよいところまでいっていますね。ただ、もう少し抽象的な文言にして、義務免除の範囲を広げておく方がよいでしょう。私なら次のようにします。「日本の官庁または公署は、正当な拒絶理由がない限り、調査の嘱託に応える義務を負う」、と。
- S: なるほど。
- T: 私的な団体は、そうした公法上の義務を負うわけではありません。私立大学は、学生諸君の成績について調査の嘱託あるいは文書送付嘱託がなされた場合には、成績が重要なプライバシー情報でありますので、学生本人の同意あるいはその他の特段の事情のない限り、嘱託に応じないでしょう。嘱託に応じなければ、次は文書提出命令になりますが、発令されても最高裁まで争うことになるでしょう。もちろん、最高裁判例が固まれば、その判例に従うことになるでしょう。
(2004年11月24日)
連帯債務と既判力
- T: Y1とY2が、Xに対して、100万円の連帯債務を負っているとします。Xは、Y1に対していくら請求できますか。
- S: 100万円。
- T: Y2に対しては、
- S: 100万円。
- T: Xは、Y1から100万円、Y2から100万円、合計200万円受け取ることができますか。
- S: だめです。連帯債務ですので、Xは、各連帯債務者に対して、その100万円の支払を同時にあるいは順次にすることができますが、Xは、全部で100万円を受け取ることができるだけです。
- T: では、XがY1とY2とを同時に訴える場合に、請求の趣旨はどうなりますか。
- S: 「被告らは、原告に、金100万円を支払え」との判決を求めます。
- T: それだと分割債務の原則によりXは、Y1に対して50万円、Y2に対して50万円を請求していることになります。もう少し言葉を補ってください。
- S: う〜ん。。。
- T: 連帯債務なんだから
- S: 「被告らは、原告に、連帯して金100万円を支払え」、ですか?
- T: そのとおり。「連帯して」に代えて、「各自」でもよいんですね。かつては、「連帯して」の意味で「各自」という言葉が使われることが多かったのです。では、ダイヤの帯留め事件を見てください。判例資料集の54頁の12番の事件(最高裁判所
昭和32年6月7日 第2小法廷 判決(昭和28年(オ)第878号))です。要旨の2番を読みますと、「ある金額の請求を訴訟物(分割債務)の全部として訴求して、その全部につき勝訴の確定判決をえた後、その請求は訴訟物(連帯債務)の一部にすぎなかった旨を主張して残額を訴求することは、許されない」となっています。この事件では、原告は、「被告らは原告に対し45万円支払え」との判決を求める訴えを提起し、その旨の判決を得たのですね。「連帯して」あるいは「各自」という言葉を入れなかったために、分割債務となりました。このため、各被告は、その半額を支払えば、それで債務を免れることになったのです。その後で、実は連帯債務であるとして訴えを提起することは許されません。その点で、訴訟ミスがあります。弁護士がこうしたミスをすれば、弁護過誤になります。この判決は、まず、前訴で分割債務として確定されたものを後訴で連帯債務であると主張することは許されないとした点に意義があります。法律関係の性質決定についての拘束力です。教科書の457頁ですね。そこに、昭和32年判決があがっていますね。次に、各被告との関係では、前訴で各被告が22万5000円の債務を負っていることが確定したのに、後訴で各被告が45万円の債務を負っていると主張することは許されないとしたのですから、黙示の一部請求認容判決が確定すると、残部の追加請求が許されとした先例としても意義があります。
5の質問は、幾分初歩的すぎるかも知れない。次の質問に置き換えることも考えられる。
- XがY1とY2とを別個に訴えて、それぞれに対して100万円支払えとの判決を得て、強制執行によりY1から100万円の弁済を得たにもかかわらず、Y2に対してもさらに強制執行により取り立てようとする場合に、Y2はどうしたらよいですか。
あるいは
- XがY1とY2とを別個に訴えて、それぞれに対して100万円支払えとの判決を得て、強制執行によりY1から100万円の弁済を得たにもかかわらず、XがさらにY2に対しても強制執行をして100万円取り立てた場合に、Y2はどうしたらよいですか。
13の説明中で、実際の授業では、単純化のために、金額は100万円にして説明していた。また、ダイヤの帯留め事件の債務が連帯債務になることを適切に説明しなかったようである。次回、説明の補正が必要である。連帯債務の発生原因:合意、民719条、民44条2項、商511条など。
(2004年11月24日)
既判力
- T: 既判力について説明してくれますか。
- S: 判決の主文中の判断について、口頭弁論終結の時に生ずる効力で、、、
- T: 既判力が発生するのは、何時ですか。
- S: あっ、判決確定の時です。
- T: どういう事柄について既判力が生じますか。
- S: 判決の主文で判断された請求を根拠づける事実です。
- T: 裁判所は、どのようなことについて判断しますか。
- S: 246条により、当事者が申し立てた事項です。
- T: 当事者が申し立てた事項というのは、
- S: 請求です。あっ、わかりました。事実ではなく、法律関係・権利関係について既判力が生じます。
- T: 既判力は、原告が訴えを以て主張した法律関係に関する裁判所の判断について生ずるのですね。法律関係は時の経過の中で変化していきますので、何時の時点での法律関係についての判断かが問題となりますね。既判力の標準時の問題ですが、それは何時ですか。
- S: 事実審の口頭弁論終結時です。
- T: 既判力はどのような効力ですか。
- S: 効力って。。。
- T: 誰に対する拘束力ですか。
- S: 裁判所を拘束します。
- T: 具体的には。
- S: 後の訴訟の裁判所は、前の訴訟の裁判所の判断と異なる判断をしてはならないという拘束力です。積極的効力です。
- T: 当事者に対する効力はありませんか。
- S: 当事者は、既判力の標準時前に存在した事由を主張して既判力ある判断を争うことを禁止されます。消極的効力です。
- T: では、既判力の基礎はだいたい解っているようなので、教科書の5頁分はこれで終ることにしまして、次に、標準時後の形成権行使の問題に入っていきます。
- 学生達: えぇぇ。そんなあぁぁ。。。
- T: 大丈夫だよ。
対話の前半では躓いたが、後半は順調に答えている。いくぶん強引な進行であったが、なにしろ時間が足りないからやむ得ない。ただ、簡単な設例を一つ取り上げた方がよかったかな、とは反省はしている。例えば、
- T: Xが占有している建物について、XがYを被告にして所有権確認の訴えを提起し、その請求を認容する判決が確定したとします。その後で、YがXに対してその建物の明渡しの訴えを提起すると、どうなりますか。
- S: 標準時後の新たな事由は主張されていないことを前提にすると、後訴の裁判所はXに所有権があるとの判断に拘束されますから、明渡請求は棄却されます。
- T: もう少し丁寧に見ていくと、どうなりますか。Yの所有権は、Yの明渡請求権の
- S: 先決問題です。
- T: 先決問題であるYの所有権と、Xの所有権とは
- S: 矛盾関係に立ちます。
- T: まとめていうと、
- S: 後訴の裁判所は、前訴判決のXに所有権があるという判断と矛盾する判断を禁じられるので、Yに所有権があるという判断をすることができません。したがって、Yの所有権を先決関係とする明渡請求を認容することができません。
上記の想定問答は、上記の設例が先決関係と矛盾関係の複合事例であることを認識させようとするものである。それを認識させることに時間を費やす必要はないと考えれば、問答2で打ち切ることになる。
(2004年11月20日)
建物買取請求権の標準時後の行使
- T: 判例資料集の77頁を開いてください。そこにある22番の判例・最高裁判所
平成7年12月15日 第2小法廷 判決の要旨を読んでくれますか。
- S1: はい。「借地上に建物を所有する土地の賃借人が、賃貸人から提起された建物収去土地明渡請求訴訟の事実審口頭弁論終結時までに建物買取請求権を行使しないまま、賃貸人の右請求を認容する判決がされ、同判決が確定した場合であっても、賃借人は、その後に建物買取請求権を行使した上、賃貸人に対して右確定判決による強制執行の不許を求める請求異議の訴えを提起し、建物買取請求権行使の効果を異議の事由として主張することができる」。
- T: そこにある「請求異議の訴え」はわかりますか。
- S1: 。。。えぇぇ!。。。
- T: 説明した方がよいかな。
- S1: お願いします。
- T: まず、民事執行法35条よんでください。
- S2: 請求異議の訴え。「債務名義に係る請求権の存在又は内容について異議のある債務者は、その債務名義による強制執行の不許を求めるために、請求異議の訴えを提起することができる」
- T: はい、ありがとう。その条文を理解する上で重要なキーワードは、執行力です。執行力は、債務名義に認められる効力です。民事執行法22条を読んでください。
- S3: 「強制執行は、次に掲げるもの(以下「債務名義」という。)により行う。 1号 確定判決 」
- T: 債務名義に表示された請求権を強制執行により実現することができるという効力を執行力といいます。わかりやすく言えば、給付判決をもって執行機関のところに行き、強制執行してくださいと言えば、必ず強制執行してくれるという効力です。そのことは、25条によく現れています。25条を読んでくれますか。
- S4: 「強制執行は、執行文の付された債務名義の正本に基づいて実施する」。
- T: 執行文は、26条です。2項を読んでくれますか。
- S4: 「執行文の付与は、債権者が債務者に対しその債務名義により強制執行をすることができる場合に、その旨を債務名義の正本の末尾に付記する方法により行う」。
- T: ありがとう。執行文は執行力の存在を証明する文言ですが、「その債務名義により強制執行をすることができる」という文言に執行力の本質がよく出ています。
- T: このような執行力を排除するための訴えが請求異議の訴えです。請求異議を認容する判決の主文では、「別紙目録記載の債務名義による強制執行は、これを許さない」と書かれます。その判決が確定すると、その債務名義に基づく強制執行は許されない、つまり、執行力が排除されたことになります。既判力は影響を受けません。例えば、土地の所有者が借地人に対して、賃貸借契約の終了を理由に、建物収去・土地明渡請求の訴えを提起し、認容判決が確定したとします。その後で、借地人が建物買取請求権を行使すると、どうなりますか。建物は、誰のものになりますか。
- S5: 土地の賃貸人のものになります。
- T: そうすると、借地人の建物収去義務はどうなりますか。
- S5: 。。。
- T: 借地人は、もう建物所有者ではありませんね。建物を収去する義務はどうなります。
- S5: 収去義務はなくなります。
- T: 前訴の口頭弁論終結時には存在していた建物収去・土地明渡義務が、その後の建物買取請求権の行使により消滅したのですね。債務名義に表示されている口頭弁論終結当時の権利関係と、現在の権利関係との間にズレがあるのですね。借地人は、債務名義に表示された請求権の存在又は内容について異議があると言って、請求異議の訴えを提起することができます。この場合に、前訴判決の既判力ある判断は、前訴の口頭弁論終結時において借地人が土地の賃貸人に対して建物収去・土地明渡義務を負っているということですので、そのままでよいですね。では、建物所有者になった土地の賃貸人は、建物を占有している借地人に対して何を要求できますか。
- S5: 。。。
- T: 土地所有者は、建物所有権に基づいて建物の明渡しを請求できませんか。
- S5: できると思います。
- T: ただ、借地人は、留置権により、建物の代金を受領するまでは建物を留置することができますね。既判力の標準時前に存在した建物買取請求権を標準時後に行使することを認めますと、このように展開することになります。これでは、土地の賃貸人にとっては、せっかく建物収去土地明渡請求を認容する判決を得たのに、「また訴訟なのか」ということになりますね。最高裁は、建物収去土地明渡請求認容判決が確定した後で借地人が建物買取請求権を行使することを認めましたか。
- S5: 認めました。
- T: その判例について、教科書ではどのようなコメントが書かれていますか。
- S6: 教科書では、(以下略)
請求異議の訴えについて説明する必要があることを前提にして、対話のリズムを整える意味で3番の質問をしたのであり、「よく解りませんので、説明してください」との返事を期待していたのだが、その返事はすぐには帰ってこなかった。授業の進行上は、3番の応答の前後にある沈黙の時間の長さが重要である。学生の個性にもよるが、このような場合には「請求異議の訴えについて説明した方がよいかな?」という質問をして、沈黙の時間ができるだけ短くなるようにすべきであろう。
教科書で説明されていないことを説明したためもあって、モノローグが多くなった。モノローグは、退屈で疲れる。性格なのだろう。上記の問答中の教師の発言も、実際の授業ではもっと乱れた日本語になっていたであろうが、少し整理し、また補正した。執行文に関する部分(13から15)は、実際の授業では言い忘れた部分である。
学生に判例や条文を音読させる場合には、一人の音読の分量が多くならないようにしている。音読している本人は、聴いている者よりも、文章の意味を取ることに神経を集中させることができないからである。
(2004年11月20日)
相殺の抗弁に供した反対債権の存否の判断に既判力が生ずる根拠
- T: 既判力は、判決主文中の判断について生ずるのが原則ですね。理由中の判断には既判力が生じないのが原則です。その例外が114条2項ですね。その根拠は、なんですか。
- S: 相殺の抗弁が反訴的なものであること、それから、相殺により訴求債権を消滅させるという形で1度利益を得て置きながら、次に、反対債権の弁済を得るという形で二重に利用することは許すべきではないからです。
- T: そうですね。教科書ではそのように説明されていますが、私の学生の頃には、「反対債権の存否を巡る紛争を通して訴求債権の存否に関する紛争が蒸し返されることを防ぐために、反対債権の不存在の判断に既判力が生ずる」と説明されていました。それがどういう意味だがわかりますか。
- S: 前訴で相殺の抗弁を提出して勝訴した被告が、そのあとで、反対債権の弁済を求めるのですね。
- T: そう。その時、被告は何と主張しますか。
- S: 前訴原告の訴求債権は口頭弁論終結前から存在していなかったと主張します。
- T: そう。だから、反対債権が相殺によって消滅するはずがない。だから、
- S: 反対債権は、存在するから支払えとなります。
- T: これを許したのでは、前訴の訴求債権の存否に関する争いが、反対債権の存否を巡る争いとして蒸し返されることになりますね。それを禁止するために114条2項がある、という説明が私の学生の頃は多かったのですが、最近の教科書ではその説明があまり見られなくなっています。そのような説明もあることに、注意してください。
授業の後で、一人の学生が質問に来て、
- S: 相殺の抗弁のところで出てきた「反対債権の存否を巡る紛争を通して」なんとかという説明がよく解らなかったのですが、あれはどういうことなのでしょうか。
- T: 教科書にのっている以外の説明もあるということです。
- S: はぁ。教科書の説明だけでは不十分でしょうか。
- T: まあ、そういうわけではないが、少し前の教科書などではそのような説明もあるから、その説明に出会ったときに戸惑わないようにという程度の意味での追加です。
- S: 被告が反対債権との相殺で訴求債権を消滅させたのですよね。その後で、さらに反対債権の支払を求めるのですよね。
- T: そう。それが反対債権の二重利用として不当であるというためには、前訴原告の訴求債権が存在し、相殺によって消滅したということが必要ですね。前訴原告の訴求債権が相殺前から存在していなかったのであれば、反対債権の二重利用になりませんね。後訴ではその点が争われているのですから、反対債権の二重利用になるから反対債権の弁済請求は許されないと言っても、説明にならないでしょう。既判力の問題ですので、どこかで「紛争の解決」ないし「紛争の蒸し返しの禁止」が出てこないと、説明にならないはずなのに、「反対債権の二重利用が不当である」という実体法的な説明にとどまっているのは適当ではないということを言いたかったのですが、ただ、いくつかのスタンダードな教科書で採用されている説明をこの授業で非難するのは適当ではないから、こういう説明もあるというところで止めているのです。迷うんですけどね。
- S: わかりました。ありがとうございます。
言いたいことを言い切っていない、と感じとられたのかもしれない。そうであれば、鋭敏な感性だ。
(2004年11月20日)
当事者尋問
授業の後で
- S: 当事者尋問はなぜ職権でもすることができるのですか。
- T: 答えにくい質問ですね。教科書にも特に説明はのっていませんね。第一に、費用がかからないことが理由になりそうですね。第二に、当事者は、裁判所に自分の言い分を聴いてもらいたい立場にあり、それは弁論に限らず、当事者尋問によっても実現されてよいでしょう。第三に、弁論主義とか職権証拠調べの禁止といっても、絶対的なものと考える必要はなく、真実に即した裁判の要請との調和のなかで、その領域が確定されると考えよいのでしょう。その調整の結果として、当事者尋問は職権でできるとされたと考えることができるでしょう。
- S: なんとなくわかりました。費用があまりかからないという説明がわかりやすい感じです。
(2004年11月5日)
主張責任と証明責任
- T: 証明責任というと、普通は客観的証明責任を指しますね。これについて説明してくれますか。
- S: 事実が存否不明の場合に、その事実を要件とする規定が適用されないことにより、その規定が定める法律効果が認められない不利益を言います。
- T: 証明責任と主張責任とはどのような関係がありますか。
- S: えぇぇ?
- T: 質問がわかりにくいですか。じゃ、変えましょう。証明責任の分配が主張責任の分配に従うのか、それとも主張責任の分配が証明責任の分配に従うのか、どちらでしょうか。
- S: 前者だと思います。当事者が事実を主張して、争いがある場合に証明責任が問題となるのですから、主張責任の分配がまず問題になり、それに従って証明責任が分配されるからです。
- T: そうですね。私も学生時代、そのようになるはずだと思っていました。しかし、一般には、「主張責任の分配は、証明責任の分配に従う」と説かれています。なぜでしょう。まず、主張責任は、弁論主義の領域のみで問題となりますか、それとも職権探知主義の領域でも問題となりますか。
- S: 弁論主義の領域で問題となります。
- T: そのとおり。では、証明責任は、どうですか。
- S: 真偽不明と言うことは、職権探知の場合にも生じます。
- T: そうすると、証明責任と主張責任とどちらが普遍的ということになるでしょうか。
- S: 証明責任です。
- T: そのとおり。そこで、「特殊なものが普遍的なものに従う」と考えて、「主張責任の分配は、証明責任の分配に従う」と説明するのです。
こうした対話の形で授業を進めることの得失は次の点にある。
- (損失) 知識教授のスピードが低下する。
- (利得) その反面、学生には、その知識を授業中に理解して飲み込む時間的余裕ができる。また、どちらかといえば、対話形式の方が印象に残りやすと思われる。
要するに、一長一短であり、「教師と学生とのダイアローグ」と「教師のモノローグ」とをうまく組合わせることが必要なのであろう。
問答1と2は、整理の段階で追加した。主観的証明責任の概念があることを考慮すると、議論の対象を特定するために、これらは必要であろう。
上記の対話の最後の部分は、次のようにすることもできるが、このあたりは、限られた時間の使い方の問題であろう。
- T: そうですね。そこで、「特殊なものが普遍的なものに従う」と考えると、最初の質問の答えはどうなりますか。
- S: 「主張責任の分配は、証明責任の分配に従う」ということになります。
- T: そのとおり。
(2004年11月5日−2005年1月7日)
証明責任の分配
- T: 証明責任の分配について、民法の規定を挙げて説明していただけますか。最初は簡単な例がよいですね。貸金返還請求を例にして説明してくれますか。
- S: 民法587条ですね。「消費貸借は、当事者の一方が種類、品等、数量の同じき物を以て返還をなすことを約して、相手方より金銭その他の物を受け取るによりて其効力を生ずる」と規定されていますので、返還約束と金銭の授受について原告に証明責任があります。
- T: そのとおり。では、債務不存在確認訴訟の場合は、どうですか。債権者が貸した金を返せといってくる。債務者は、「そんな借金はした覚えはない」、といって債務不存在確認請求の訴えを提起した場合には、誰がどの要件事実について証明責任を負いますか。
- S: この場合は、原告が金銭の授受のなかったこと、あるいは返還約束のなかったことについて証明責任を負います。
- T: 原告というのは、債務者ですね。債務者が金銭の授受のなかったことや返還約束のなかったことについて証明責任を負うのですね。
- S: はい。
- T: よかった。。。答えがよかったという意味ではなくて、授業で教えてよかったという意味で。
- S: え、違うんですか。
- T: 民法587条の適用を求めるのは誰ですか。
- S: 債権者です。
- T: そうですね。債務不存在確認訴訟の場合でも、債権者が587条の適用を求めるのです。ですから、彼がその要件とされている事実を証明する責任を負います。この点は、とても大事ですので、間違えないでくださいね。特に、強制執行の場面で重要となります。例えば、「賃借人が賃料の支払いを3回怠った場合には、賃貸人は直ちに賃貸借契約を解除して、賃借人に対して直ちに明渡しを請求することができる」という裁判上の和解が成立したとします。賃貸人が強制執行を申し立てる場合に、賃借人が賃料の支払いの事実について証明責任を負うことに変わりはなく、賃貸人は賃料不払いの事実を証明することなく強制執行の申立てをすることができるのです。
最後の設例の説明は、準備不足であることを否めない。まず、弁済の証明責任について説明し、それから民執法174条3項について説明し、その類推適用を説明するのが本来である。ただ、民執法174条3項やその類推適用まで説明する余裕はないから、上記のように端折った説明をすることになったが、わかりにくいであろう。この設例を挙げて説明することは、我慢した方がよかったと反省している。
(2004年11月5日)
本案判決の要件としての訴訟要件
- T: 訴訟要件は、訴訟係属の要件でしょうか。
- S: はい、そうだと思います。
- T: 訴訟係属は、いつ発生しますか。
- S: 原告が訴状を裁判所に提出したときです。
- T: 訴訟係属の定義のしかたはいくつかありますが、東京大学の伊藤眞先生の「裁判所と原告と被告の3者間に訴訟法律関係が生じている状態」という定義がわかりやすいでしょう。原告が訴状を裁判所に提出しただけだと、まだ、原告と裁判所との間に訴訟法律関係があるだけですね。
- S: 訴状が被告に送達された時に訴訟係属が発生します。
- T: そのとおり。この段階で訴訟要件の具備が必要であるとすると、誰がどの段階がそれを確認するのですか。
- S: 裁判長が訴状審査の段階で確認します。備わっていなければ、補正命令を発します。
- T: 訴訟要件には、慎重な判断を必要とするものがありますので、裁判長が一人で判断するのは無理でしょう。訴状審査の段階で裁判長が審査するのは、基本的に、133条2項に規定されている必要的記載事項、つまり当事者や請求の趣旨・原因が記載されているかです。
- S: 本案の審理の要件だと思います。
- T: 本案の審理というのは、裁判所が本案についての判断資料を収集する過程、つまり口頭弁論と考えてよいでしょうか。
- S: はい。
- T: 訴訟要件の中には、要件が具備されて初めて審理を進めることが許されるものも確かにあります。75条以下で規定されている訴訟費用の担保の提供がそうですね。日本に住所等を有しない者が日本で訴えを提起して、敗訴したら負け逃げして、被告が訴訟費用の償還をしてもそれに応じないという事態を避けるために、被告は、日本に住所等を有しない原告に担保の提供を命ずることを裁判所に申し立てることができ、その申立てをした被告は、原告が担保を提供するまで応訴を拒むことができるとされています。このように、訴訟要件の具備まで応訴(手続の進行)を拒むことができるタイプの抗弁を妨訴抗弁といいます。一般の訴訟要件には、そのような効果は、認められていません。訴訟要件の具備を確認しないまま、本案の審理つまり判断材料集めを進めることも許されています。
- S: 訴訟要件は、基本的に、本案判決の要件です。
- T: その通り。その点からすると、教科書で「訴訟要件と本案要件の審理の順序」という見出しが書かれていますが、私が書くとすれば、「訴訟要件と本案要件の判断の順序」となります。
訴訟要件が本案審理の要件でないことの実質的説明が不十分である。事例をあげて、もう少し説明した方がよかった。
(2004年11月6日)
訴訟要件の審理と本案の審理との並行
- S: 先生、本案の審理と並行して訴訟要件の審理をすることができるということがよくわかりません。
- T: 例えば、XがYに対して債権を有していて、YがZに対して債権を有していて、YがXに債務の弁済をしないので、Xが、民法423条により、Yに代わって、YのZに対する債権の取立訴訟を提起するとします。ここまではよいですか。
- S: はい、なんとか。
- T: XがYに代わって取立訴訟をするためには、XのYに対する債権が存在することが必要ですね。それが、Xの当事者適格を根拠付けます。他方、訴訟物は、YのZに対する債権ですね。その債権の存否が本案の問題となります。裁判所は、XのYに対する債権の存否に関する資料を集めつつ、YのZに対する債権の存否に関する判断資料を集めることができます。つまり、訴訟要件に関する判断材料を集めつつ、したがって、訴訟要件の具備を確認する前に、本案の問題について審理するのです。それが許されているのです。わかった?
- S: はい。
裁判所を除く登場人物(当事者等)が3以上になると、口頭だけでの説明が難しくなり、黒板に図を書くことが必要になることが多い。その点で、口頭での説明だけで理解してもらえたのか、一抹の不安は残る。しかし、わからなければ、「よく解らなかったので、もう一度説明してください」と学生が言える雰囲気になっており、そのように言うことができる学生が少なくとも数人はいると思うので、大丈夫であろう。
一切板書せずに口頭でのみ説明する理由は、次の点にある。(α)スピードが上がる。 (β)法廷では口頭主義であり、黒板が使用されることは通常はない。口頭でのやりとりで、相手の説明を理解し、自分の考えを表明することに慣れておく必要がある。
(2004年11月6日)
確定した請求認容判決の存在と訴えの利益
- T: XがYに対して金1000万円の支払請求の訴えを提起し、その請求認容判決が確定したとします。その1年後に、Xが同じ債権について、支払請求の訴えを提起すると、どうなりますか。
- S: 二重起訴になると思います。
- T: 二重起訴というのは、何条ですか。
- S: 142条です。
- T: 読んでみてください。
- S: 裁判所に係属する事件について
- T: はい、そこでストップ。訴訟事件の「係属」は、いつ生じますか。
- S: 訴えが提起された時ですから、訴状が裁判所に提出された時です。
- T: 訴訟が裁判所に提出された段階では、裁判所と原告との法律関係しかありませんね。裁判所は、両当事者の言い分を公平に聴いて判決するのですから、裁判所と原告と被告の3者の間で訴訟法律関係が生じたときに、訴訟係属が生ずると考えます。そうすると、何時ですか。
- S: 訴状が被告に送達された時です。
- T: そうですね。その時から裁判所が事件に対して判決で応答すべき状態が生じます。では、訴訟係属が終了するのは何時ですか。
- S: 判決が確定したときです。
- T: そうすると、判決確定後に再度同じ訴えを提起した場合に、142条の適用はありますか。
- S: ありません。
- T: そうですね。学期末試験では、この点を誤解した答案がよくみられます。今日間違えたから、もう、間違えることはないでしょう。では、XがYに対して金1000万円の支払請求の訴えを提起し、その請求認容判決が確定し、その1年後に、Xが同じ債権について支払請求の訴えを提起すると、どうなりますか。
- S: わかりません。
- T: あなたが裁判官だったら原告に、「どうして同じ訴えを提起するのですか。原告は、もうほしいものを手に入れているのではいるのではないですか」と尋ねませんか。
- S: つまり、訴えの利益がないということですか。
- T: そうです。では、XがYに対して金1000万円の支払請求の訴えを提起し、その請求認容判決が確定したとします。その9年9ヶ月後に同じ債権について、支払請求の訴えを提起すると、どうなりますか。
- S: やはり訴えの利益がない。。。
- T: 民法174条の2を見てください。
- S: 消滅時効の期間が10年になると書いてあります。
- T: ですから、前の判決が確定しているから、9年9ヶ月が過ぎているので。。。
- S: もうじき時効が完成するおそれがあります。
- T: そう。だから、
- S: 時効中断のために訴えを提起する必要がある。
- T: そのとおり。通説では、今のような形で、訴えの利益を問題にし、再度の訴えの適否を判断するのです。
問答がいくぶん長すぎた。限られた時間の中で教えるのであるから、内容を減らすことなく問答に要する時間を短縮するために、質問を工夫しなければならない。また、この問答については、工夫の余地があった。再度の訴え提起の時期として、最初に請求認容判決確定後から9年9ヶ月目を取り上げ、次に1年目を取り上げると、少しだけ時間を節約することが期待できそうに思える。
- T: XがYに対して金1000万円の支払請求の訴えを提起し、その請求認容判決が確定したとします。その9年9ヶ月後に同じ債権について、支払請求の訴えを提起すると、どうなりますか。仮に裁判長が原告に、「原告は、前訴でほしいものをすでに手に入れているのに、どうして同じ訴えを提起するのですか」と質問したら、原告はどのように答えたらよいですか。
- S: えぇぇぇ。
- T: 民法174条の2を見てください。
- S: 消滅時効の期間が10年になると書いてあります。
- T: ですから、前の判決が確定しているから、9年9ヶ月が過ぎているので。。。
- S: もうじき時効が完成するおそれがあります。
- T: そう。だから、
- S: 時効中断のために訴えを提起する必要がある。
- T: そのとおり。では、前訴判決が確定してから1年目に同じ訴えを提起した場合は、どうなりますか。
- S: 時効中断の必要は当分ありませんので、訴えの利益は否定されることになりそうです。
- T: そのとおり。
上記のような問答をすることは、教師にとっては楽なことである。安住したくなるほどに楽であるが、安住は許されない。次の目標を立てて、それに移行することを心掛けなければならない。次の目標は、学生の知識が教師と対等な水準にまで近づき、学生が自分の意見を長く述べるようにすることである。学生たちは成長しているのであり、1月ごとにレベルが上昇し、基本的な知識の点では間もなく自分と対等になるであろうことを想定して授業に望むべきであると自戒したい。
(2004年11月6日)
中間判決をすることができる事項
- T: 中間判決をすることができる「その他の事項」を、何でもよいからあげてくれませんか。
- S: そうですね、管轄とか。。。
- T: じゃ、それについて考えてみましょう。訴えが提起された事件について裁判所が国内管轄権を有しないと被告が考えたとしましょう。被告は、どうしたらよいですか。被告は、移送の申立てをすることになりますね。何条ですか。
- S: 16条です。
- T: 管轄権を有しないと判断した裁判所は、どうしますか。
- S: 管轄権を有する裁判所に移送します。
- T: 受訴裁判所が管轄権を有すると判断した場合は、どうしますか。
- S: 移送の申立てを決定で却下します。
- T: それで一応問題は解決されそうですね。裁判所が国内管轄権の有無について中間判決をする必要は、普通はないでしょう。
- S: はい。
- T: では、国際裁判管轄権が争われた場合は、どうですか。日本の裁判所が国際裁判管轄権を有しないと判断した場合には、日本の裁判所は外国の裁判所に移送することができますか。
- S: 外国の裁判所への移送の制度はなかったと思います。
- T: そうすると、日本の裁判所が国際裁判管轄権を有しないと判断した場合には、どのような判決をしますか。
- S: 訴え却下判決をします。
- T: 日本の裁判所が国際裁判管轄権を有すると判断した場合には、受訴裁判所は国際裁判管轄権の有無を巡る争いについてどのような形で決着をつけたらよいですか。
- S: 中間判決で決着をつけ、本案について審理を続けます。
- T: そのとおり。
(2004年11月8日)
[目次]
2004年11月5日−2005年2月16日
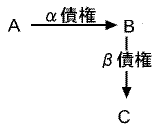 S: 「Aが、Bに対する債権(α債権)に基づいて、BのCに対する債権(β債権)を行使する債権者代位訴訟を提起した。α債権の存在を争うBは、どうしたらよいか」という問題についてですが、これは最判昭和48年4月24日民集27巻3号596頁を基にした事例問題で、その判旨で解決されるとは思いますが、いくつか質問したいことがあります。
S: 「Aが、Bに対する債権(α債権)に基づいて、BのCに対する債権(β債権)を行使する債権者代位訴訟を提起した。α債権の存在を争うBは、どうしたらよいか」という問題についてですが、これは最判昭和48年4月24日民集27巻3号596頁を基にした事例問題で、その判旨で解決されるとは思いますが、いくつか質問したいことがあります。
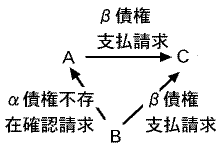 S: AB間で、α債権の不存在を確認する判決が確定すると、AC間の訴訟はどうなるのでしょうか。
S: AB間で、α債権の不存在を確認する判決が確定すると、AC間の訴訟はどうなるのでしょうか。 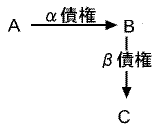 S: 「Aが、Bに対する債権(α債権)に基づいて、BのCに対する債権(β債権)を行使する債権者代位訴訟を提起した。α債権の存在を争うBは、どうしたらよいか」という問題についてですが、これは最判昭和48年4月24日民集27巻3号596頁を基にした事例問題で、その判旨で解決されるとは思いますが、いくつか質問したいことがあります。
S: 「Aが、Bに対する債権(α債権)に基づいて、BのCに対する債権(β債権)を行使する債権者代位訴訟を提起した。α債権の存在を争うBは、どうしたらよいか」という問題についてですが、これは最判昭和48年4月24日民集27巻3号596頁を基にした事例問題で、その判旨で解決されるとは思いますが、いくつか質問したいことがあります。
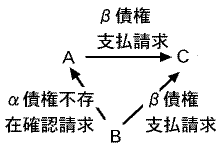 S: AB間で、α債権の不存在を確認する判決が確定すると、AC間の訴訟はどうなるのでしょうか。
S: AB間で、α債権の不存在を確認する判決が確定すると、AC間の訴訟はどうなるのでしょうか。 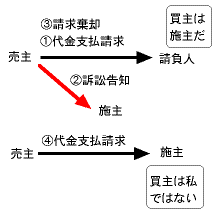 黒板の図を見てくれますか。売主は、請負人に対する第一訴訟では、買主は施主であるとの理由で敗訴しました。施主に対する第2訴訟では、買主は請負人であるという理由で敗訴する可能性があるのですね。矛盾した理由による両負けです。そのリスクを回避するために、売主の訴訟代理人は、施主に対して訴訟告知をして、施主が「買主は自分ではない」と主張することを封じようとしたのです。しかし、予期に反して、最高裁は、この場合には判決理由中の「買主は施主である」との判断には参加的効力が生じないとしたのです。
黒板の図を見てくれますか。売主は、請負人に対する第一訴訟では、買主は施主であるとの理由で敗訴しました。施主に対する第2訴訟では、買主は請負人であるという理由で敗訴する可能性があるのですね。矛盾した理由による両負けです。そのリスクを回避するために、売主の訴訟代理人は、施主に対して訴訟告知をして、施主が「買主は自分ではない」と主張することを封じようとしたのです。しかし、予期に反して、最高裁は、この場合には判決理由中の「買主は施主である」との判断には参加的効力が生じないとしたのです。 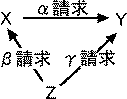 S: (黒板に図を書きながら)原告が被告に所有権確認の訴えを提起して、参加人が原告と被告の双方に所有権確認の訴えを提起した場合に、井上先生の見解ではどうなるのですか。
S: (黒板に図を書きながら)原告が被告に所有権確認の訴えを提起して、参加人が原告と被告の双方に所有権確認の訴えを提起した場合に、井上先生の見解ではどうなるのですか。